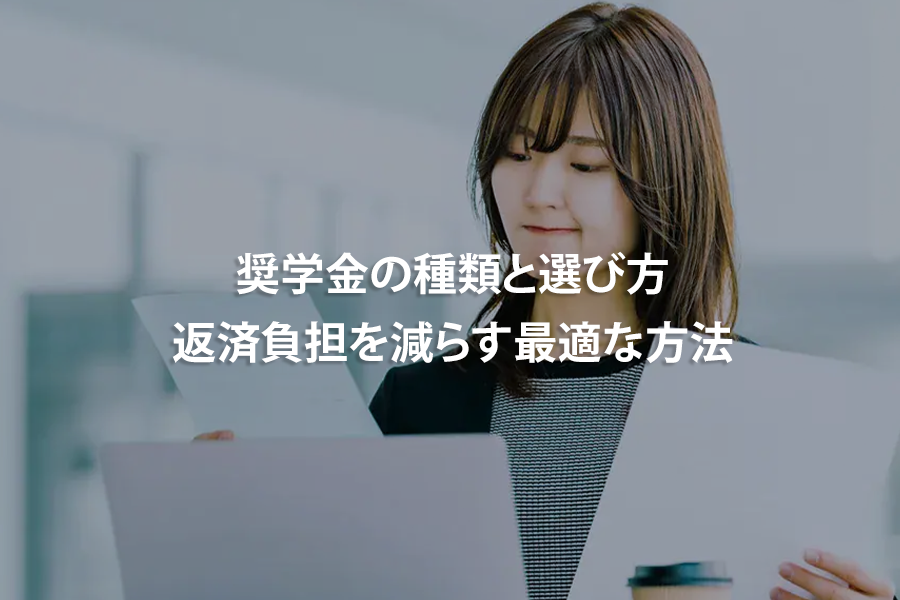
奨学金には、給付型や貸与型など、さまざまな種類があります。どの奨学金を選べばよいのか迷う方も多いでしょう。本記事では、奨学金の基本知識を解説し、自分に適した制度の選び方や申し込みの流れについて紹介します。
奨学金の基礎知識を押さえよう
そもそも奨学金とはどのような制度なのでしょうか?ここでは、奨学金の仕組みや目的、利用するメリットなどの基本情報を解説します。
奨学金とは?基本的な仕組みと目的
奨学金は、経済的な理由で進学が難しい人を支援するための制度です。学費や生活費の補助を目的とし、国や地方自治体、大学、企業、公益法人などが提供しています。
特に、日本学生支援機構(JASSO)は代表的な奨学金制度を運営しています。それ以外にも、民間団体や自治体が独自の奨学金を用意しており、それぞれ申請手続きが必要です。審査に通過すれば、給付や貸与を受けられます。
給付型と貸与型の違いを理解する
奨学金は大きく「給付型」と「貸与型」の2種類に分かれます。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを選びましょう。
給付型奨学金(返済不要)
- 返済の必要がない奨学金
- 成績や家計状況など厳しい審査基準がある
- 採用枠が少ないため、競争率が高い
貸与型奨学金(返済必要)
- 学校卒業後に返済が必要
- 比較的審査が緩く、利用しやすい
- 「無利子」と「有利子」の2種類がある
特に貸与型の奨学金を利用する場合、卒業後の返済計画をしっかり立てることが重要です。
奨学金を借りる理由とそのメリット
奨学金を利用する最大のメリットは、経済的な負担を軽減しながら学業に専念できることです。家庭の事情や収入の制限にかかわらず、進学の夢を諦める必要がなくなります。
- 給付型奨学金 → 返済不要で、社会人になってからの負担がない
- 貸与型奨学金 → 低金利または無利子で借りられ、金融機関の教育ローンよりも負担が少ない
ただし、貸与型の場合は卒業後の返済が必要になるため、計画的に利用することが求められます。
奨学金の種類と特徴
日本国内で最も利用者が多い奨学金制度は、日本学生支援機構(JASSO)によるものです。JASSOでは、第一種奨学金(無利子)、第二種奨学金(有利子)、給付型奨学金の3種類を提供しています。さらに、地方自治体や企業、民間団体が独自の奨学金制度を運営しており、選択肢は多岐にわたります。
ここでは、それぞれの奨学金の種類と特徴について詳しく見ていきましょう。
第一種奨学金(無利子)
第一種奨学金は、利息のない貸与型奨学金です。成績優秀でありながら、家庭の経済状況が厳しい学生に向けた支援制度となっています。
上限支給金額
支給される金額は、学校の種類や通学形態によって異なります。
| 通学形態 | 国公立大学 | 私立大学 |
|---|---|---|
| 自宅通学 | 20,000円 / 30,000円 / 45,000円 | 20,000円 / 30,000円 / 54,000円 |
| 自宅外通学 | 20,000円 / 30,000円 / 40,000円 / 51,000円 | 20,000円 / 30,000円 / 40,000円 / 64,000円 |
奨学金を申し込む際に、上記の金額の中から希望額を選択することができます。
対象者と申込条件
対象者:
- 大学・短期大学・専門学校(専門課程)・高等専門学校・大学院で学ぶ学生
- 進学前(予約採用)または進学後(在学採用)で申請可能
学力基準:
- 大学・短期大学・専門学校:高等学校での全履修科目の評定平均値が5段階評価で3.5以上または、高卒認定試験の合格者
- 大学院:大学で優れた成績を修めた者
家計基準:
- 生計維持者(保護者など)の収入が基準額以下であること(例:給与所得者の場合、貸与額算定基準額が189,400円以下)
第一種奨学金は、学力や家計状況に関する厳しい基準をクリアする必要があるため、希望する方は事前にJASSOの公式サイトで詳細を確認しましょう。
返済時のメリット
第一種奨学金の最大のメリットは無利子であることです。貸与型奨学金の中では最も負担が軽減される制度といえます。
返済について
- 返済開始時期:貸与終了月の翌月から7か月後
- 返済方法:定額返還方式または所得連動返還方式
定額返還方式
- 毎月の返済額が一定
- 計画的に返済しやすい
- 返済期間は最大20年
所得連動返還方式
- 前年の課税所得に応じて毎月の返済額が変動
- 収入が低い場合は返済額が減額されるため、生活が安定するまで負担を軽減できる
- 収入が増えると返済額も増える
- 返済期間は、所得や貸与総額によって異なる
第二種奨学金(有利子)
第二種奨学金は、利息が発生する貸与型奨学金です。第一種奨学金(無利子)と比べると、審査基準が緩やかであり、多くの学生が利用できる点が特徴です。ただし、卒業後は借りた金額に加えて利息も返済する必要があるため、申請時にはしっかりと計画を立てることが重要です。
返済時の利率の算定方法
第二種奨学金の利息は、上限3.0%と定められていますが、実際の適用金利は貸与終了時の市場金利によって決まります。返済時の利率を決定する方式には、「利率固定方式」と「利率見直し方式」の2種類があり、奨学金の申請時にどちらかを選択する必要があります。
利率固定方式
- 貸与終了時に決定した利率が、返済終了まで適用される方式
- 市場金利の変動の影響を受けないため、計画的に返済しやすい
- 市場金利が上昇した場合でも、貸与時の低い金利を維持できるのがメリット
- 一方、市場金利が低下しても、契約時の金利が適用され続けるため、低金利の恩恵を受けられない可能性がある
向いている人:
- 市場金利の変動を気にせずに安定して返済したい人
- 長期間にわたる返済計画をしっかり立てたい人
利率見直し方式
- おおむね5年ごとに金利が見直される方式
- 市場金利が下がれば低い金利が適用されるが、市場金利が上がるとより高い金利が適用されるリスクがある
- 5年ごとに利率が変わるため、月々の返済額が変動する可能性がある
- 将来的な金利を予測するのは難しいため、慎重な判断が必要
向いている人:
- 低金利のチャンスを活かしたい人
- 市場金利の動向に柔軟に対応できる人
利率の算定方式の変更について
奨学金の申請時にどちらの方式を選ぶか決める必要がありますが、貸与終了年度内であれば変更が可能です。そのため、市場金利の状況を見ながら、卒業前に一度見直してみるのも良いでしょう。
給付型奨学金
給付型奨学金は、返済不要の奨学金制度で、経済的な理由で進学が難しい学生を支援することを目的としています。この制度の最大の魅力は、卒業後に返済義務が一切ないことです。これにより、学業に専念できるだけでなく、将来的な経済的負担を軽減できるメリットがあります。
給付型奨学金の支給額
給付額は、家庭の所得状況(第1区分~第4区分)によって異なります。たとえば:
- 第1区分(最も支給額が高い)
- 自宅通学:月額38,300円(国公立大学)、月額46,000円(私立大学)
- 自宅外通学:月額66,700円(国公立大学)、月額75,800円(私立大学)
支給額は、世帯収入が低いほど高額になるため、経済的に困難な家庭の学生ほど多くの支援を受けられます。
給付型奨学金のメリット
- 返済義務なし
- 卒業後の返済負担がないため、将来の生活設計をしやすい
- 奨学金の返済を気にせず、キャリア形成に専念できる
- 毎月の安定した給付
- 一定額を毎月受け取れるため、学費や生活費の補填ができる
- アルバイトに頼りすぎることなく、学業に集中できる
- 利息なし
- 第二種奨学金(有利子)のように利息の負担が発生しない
- 卒業後の経済的リスクを低減できる
給付型奨学金のデメリット
- 選考基準が厳しい
- 学業成績が一定基準以上であることが求められる
- 家計基準(世帯収入や資産の条件)を満たす必要がある
- 採用人数が限られている
- 第一種奨学金(無利子)や第二種奨学金(有利子)よりも狭き門
- 成績が優秀かつ経済的困難な学生のみが対象
給付型奨学金の応募条件
① 学業基準
- 進学前(予約採用)の場合
- 高校での評定平均値が3.5以上(5段階評価)
- または、高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)の合格者
② 家計基準
- 本人および生計維持者の市町村民税所得割が非課税
- 資産額の合計が2,000万円未満
- 世帯の年間収入が一定基準以下であること
給付型奨学金はこんな人におすすめ
- 家庭の経済状況が厳しく、進学が難しいと感じている人
- 成績優秀で学業に対する意欲が高い人
- 卒業後に奨学金の返済を負担に感じたくない人
地方自治体の奨学金
地方自治体(都道府県や市区町村)では、給付型奨学金や貸与型奨学金など、独自の奨学金制度を提供していることがあります。地域ごとに制度の内容は異なるため、まずは自分の居住地や進学予定の地域で利用できる奨学金があるかを調べてみましょう。
地方自治体の奨学金の特徴
- 地域密着型のサポート
- その地域の学生を支援するため、地元の高校・大学に進学する場合に優遇されることがある
- 地方の活性化を目的として、特定の分野(医療・福祉・農業など)で働く学生を対象とする奨学金もある
- 就職・勤務条件付きの奨学金
- 卒業後に一定期間、地元の企業や公務員として勤務することを条件に、学費が免除される場合がある
- 特に、医療・教育・介護分野では、地方で働く人材確保のために奨学金を支給する制度が充実している
- 小中学生向けの奨学金
- 家庭の経済状況によっては、小学生や中学生のうちから利用できる奨学金がある
- 学習支援や給食費の補助を行っている自治体も存在する
- 奨学金の返還支援制度
- 地方自治体の中には、奨学金の返済を肩代わりする制度を用意しているところもある
- 経済的な理由で返済が難しくなった場合に、一定の条件を満たすことで自治体が返済を支援する
地方自治体の奨学金の探し方
- 自治体の公式サイトを確認する
- 「◯◯県 奨学金」「◯◯市 奨学金」などで検索すると、制度の詳細を確認できる
- 役所や教育委員会に問い合わせる
- 県庁、市役所、区役所の窓口で奨学金制度の情報を提供してもらえる
- 学校の奨学金担当窓口に相談する
- 高校や大学に奨学金の担当者がいる場合があるので、進学予定の学校にも相談してみる
民間団体や企業の奨学金
地方自治体だけでなく、民間の団体や企業も奨学金を提供しており、特定の分野で活躍する学生や経済的に困難な状況にある学生を支援しています。
民間団体・企業の奨学金の特徴
- 特定の条件を満たす学生を支援
- 例:あしなが育英会奨学金
- 病気や事故、自死などで親を亡くした学生や、障がい者の親を持つ学生を対象
- 無利子貸与型奨学金を提供し、月額30,000円~50,000円を支給
- 例:特定分野支援奨学金
- 理工系、芸術系、スポーツなど、特定の分野で活動する学生を対象に奨学金を支給
- 一部企業では、大学卒業後に関連業界へ就職することを条件とするケースもある
- 例:あしなが育英会奨学金
- 企業による奨学金返済支援制度(代理返還)
- 日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金を利用している社員を対象に、企業が返済を支援
- 企業が奨学金の一部または全額を肩代わりして返済する制度
- 人材確保のために福利厚生として導入する企業が増加している
企業の奨学金返済支援制度(代理返還)のメリット
- 奨学金の負担を軽減
- 企業が毎月の返済額の一部または全額を負担してくれるため、自己負担が減る
- 安定した職場環境
- 企業側も長期的な雇用を目的としているため、奨学金支援を受けることで安定した職場に就職しやすい
- 業界特化のキャリア形成
- 企業の奨学金制度を利用することで、特定の分野でのキャリア形成をしやすくなる
奨学金を探す際のポイント
- 公的機関(JASSO、地方自治体)と民間の奨学金を比較する
- 給付型の奨学金を優先的に検討し、無利子・低利子の貸与型を必要に応じて活用する
- 勤務条件や返済条件を確認する
- 「卒業後に◯年間勤務することが条件」などの制約がないかチェック
- 公式サイトや窓口で最新情報を確認する
- 自治体の公式サイトや企業の奨学金ページを確認し、募集要項をよく読む
奨学金の選び方|自分に合った制度を見つけるために
奨学金にはさまざまな種類があり、自分に合ったものを選ぶのは簡単ではありません。どの奨学金が最適なのかを見極めるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、奨学金を選ぶ際に重要なポイントを紹介します。
学費と生活費を正確に見積もる
奨学金を申し込む前に、学費と生活費の総額を把握することが重要です。
学費の試算
- 入学金
- 授業料
- 教科書代
- 実習費(学部・学科による)
- その他の学習に必要な費用
生活費の試算
一人暮らしをする場合は、奨学金でどこまで生活費を補う必要があるのかを考慮し、以下のような支出を試算してみましょう。
- 家賃
- 光熱費
- 食費
- 通信費
- 交通費
- 日用品・雑費
奨学金の支給額を決める際には、学費と生活費を合計し、アルバイトや家族のサポートなど他の収入源も考慮しながら、必要な金額を割り出すことが大切です。
返済方法を考慮する
奨学金を利用する際には、将来の返済計画を事前に立てておくことが重要です。
返済の仕組みを理解する
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の場合、貸与が終了した翌月から7か月後に返済が開始されます。奨学金の種類によって返済方式が異なるため、自分に合った方法を選びましょう。
- 定額返還方式:毎月一定額を返済する方法。計画的な返済がしやすい。
- 所得連動返還方式:収入に応じて返済額が変動する方式。収入が少ない時期は負担が軽減されるが、増えた場合は返済額が増える可能性がある。
延滞リスクを回避する
奨学金の返済が滞ると、以下のようなリスクがあります。
- 延滞金の発生(未納が続くと、利息が加算される)
- 信用情報機関への登録(ブラックリスト入りし、クレジットカードやローンの利用が困難になる)
奨学金の滞納を防ぐためにも、無理のない金額を借りることが大切です。また、返済が困難になった場合の対策として「減額返還制度」や「返還期限猶予制度」がある奨学金を選ぶのも一つの方法です。
選考基準を確認する
奨学金にはそれぞれ学力・経済状況・社会貢献活動などの選考基準があります。
主な選考基準
- 学力基準:一定の成績を維持しているか(例:評定平均値3.5以上など)
- 家計基準:家庭の所得が一定以下であるか
- 社会貢献活動:ボランティアや研究活動に積極的に関わっているか
選考基準を満たしていなければ、採用される可能性は低くなります。そのため、事前に募集要項をよく確認し、自分の状況と照らし合わせることが大切です。
自分に合った奨学金を探すコツ
- メモを取る:自分の学力、家計状況、希望条件を整理する
- リストアップする:希望条件に合う奨学金をリスト化する
- 優先順位を決める:自分にとって最も重要な条件を明確にする
給付型奨学金を最優先に考える
奨学金を選ぶ際には、返済不要の給付型奨学金を最優先に検討するのが理想的です。
給付型奨学金のメリット
- 返済義務なし → 将来の経済的負担がない
- アルバイト時間を減らせる → 学業に集中しやすい
給付型奨学金のデメリット
- 選考基準が厳しい → 成績や家計基準を満たす必要がある
- 募集人数が限られる → 競争率が高く、狭き門
給付型奨学金を選ぶポイント
- 応募基準と受給条件をチェック
- 必要な書類を早めに準備
- 他の奨学金とも併用可能か確認
給付型奨学金は条件が厳しいものが多いですが、利用できる可能性があるなら積極的に申請するのがおすすめです。
奨学金を申し込むための準備とステップ
奨学金を利用するためには、事前の準備と正確な手続きが必要です。申し込みのスケジュールを確認し、必要書類をそろえておくことで、スムーズに申請を進められます。
ここでは、奨学金の申し込みの流れについて詳しく解説します。
申し込みスケジュールを確認する
奨学金には申込期限が設けられており、期限を過ぎると申請ができなくなるため、早めにスケジュールを確認しましょう。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の申込スケジュール
JASSOの奨学金には、予約採用と在学採用の2つの申し込み方法があります。
- 予約採用(進学前に申し込む)
- 第一種奨学金(無利子) → 進学前年の春頃
- 第二種奨学金(有利子) → 進学前年の春と秋の年2回
- 申込場所:在学している学校の奨学金窓口
- 在学採用(進学後に申し込む)
- 申込時期:春と秋
- 対象:進学後に奨学金を希望する人、予約採用で不採用になった人
- 申込場所:在学している学校の奨学金窓口
他の奨学金制度のスケジュール
地方自治体や企業の奨学金は、募集時期が異なります。多くは年度の初めや秋頃に募集を行うため、公式サイトや募集要項を定期的に確認しましょう。
必要書類の準備
奨学金の申請には、さまざまな書類を用意する必要があります。早めに確認し、必要なものをそろえましょう。
一般的に必要な書類
- 申込用紙
- 所得証明書(保護者の収入証明)
- 成績証明書
- 奨学金希望理由書(作文)
- マイナンバー提出書(日本学生支援機構の場合)
日本学生支援機構の奨学金に必要な書類
- スカラネット申込用紙
- 保護者の所得証明書類
- 特別控除に関する証明書類
- スカラネットのユーザID・パスワード
ポイント:
- 記入ミスや漏れがあると審査に影響を及ぼす可能性があるため、複数回見直すことが大切です。
- 音読しながら確認するのもミス防止の方法の一つです。
インターネットでの申込方法(JASSOの奨学金)
JASSOの奨学金は、オンラインでの申し込みが可能です。以下の手順に従って手続きを進めましょう。
申し込み手順
- スカラネットのユーザIDとパスワードを取得
- 申し込み前に、学校の奨学金窓口でユーザIDとパスワードを受け取る。
- スカラネットにログイン
- 指定された期限内にスカラネットへアクセスし、必要事項を入力する。
- マイナンバーの提出
- 申込時に、マイナンバーの提出が必要。
- 提出用封筒を利用し、指定の窓口へ郵送する。
- 学校への書類提出
- 提出書類一覧表
- 給付奨学金確認書 などの必要書類を学校へ提出する。
奨学金を選ぶ際のよくある質問とその回答
奨学金を選ぶ際に、多くの人が疑問に思うポイントを整理しました。適切な奨学金を見つけ、無理なく活用するための参考にしてください。
奨学金の返済が不安です。どうすればいいですか?
貸与型奨学金は卒業後の返済義務があるため、返済計画を立てることが重要です。
対策として考えられる方法
- 返済シミュレーションを行う:月々の返済額や期間を確認し、将来の負担をイメージする
- 繰上返済を活用する:早めに返済すれば、利息の負担を減らせる
- 減額返還・返還期限猶予を検討する:収入が少ない時期は返済額を減らす、もしくは返済を一時的に停止することも可能
- 奨学金返還支援制度を活用する:企業によっては、社員の奨学金返済をサポートする「代理返還制度」がある
ポイント 卒業後の収入やライフプランを考えながら、無理のない範囲で計画を立てることが大切です。
奨学金が複数ある場合、どれを選べばいいですか?
奨学金には併用可能なものがあり、複数の奨学金を組み合わせて利用することができます。
選び方のポイント
- 給付型を最優先にする(返済不要で負担が少ない)
- 第一種奨学金(無利子)を検討する(貸与型の中でも負担が少ない)
- 第二種奨学金(有利子)は最終手段(できるだけ利息の負担を減らす)
注意点
- 借りすぎると返済負担が大きくなる
- 生活費まで賄うと、返済が長期化する可能性がある
- 学費と生活費を見積もり、必要な額だけ借りる
無計画に借りすぎると、卒業後の生活に支障をきたすこともあるため、慎重に選びましょう。
奨学金の選考に落ちた場合、どうすればいいですか?
奨学金の選考基準は、学力・世帯収入・書類の正確性などによって決まります。不採用になった場合、まず理由を確認することが重要です。
主な落選理由
- 学力基準を満たしていない
- 世帯収入が基準を超えている
- 申請書類に不備がある
- 募集枠が限られていて競争が激しい
対策
- 他の奨学金を探す:民間団体、企業、地方自治体など、JASSO以外にもさまざまな奨学金制度がある
- 翌年の募集に再チャレンジする:一度落ちても、翌年度に再応募できる制度もある
- 教育ローンを検討する:どうしても資金が足りない場合は、日本政策金融公庫などの低利子教育ローンを活用する
一つの奨学金に落ちても、他に応募できる奨学金がないか探してみましょう。
まとめ|最適な奨学金を選び、計画的に活用しよう
奨学金を利用すれば、経済的な理由で進学を諦める必要はありません。日本では、多くの学生が奨学金制度を活用しており、自分に合った奨学金を見つけることが大切です。
奨学金の選び方のポイント
- 給付型奨学金を最優先に検討
- 貸与型は無利子の第一種奨学金を選ぶ
- 有利子の第二種奨学金は最終手段として考える
- 必要な金額だけ借りて、返済計画をしっかり立てる
奨学金の返済は卒業後の負担になるため、無理なく返済できる範囲で借りるようにしましょう。適切な奨学金を選び、学業に集中できる環境を整えることが大切です。










