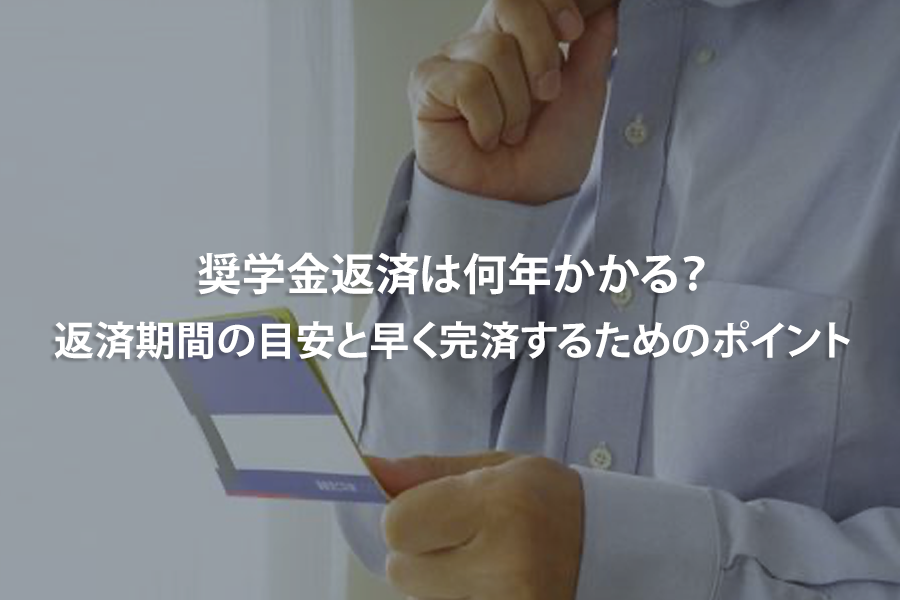
奨学金返済は何年かかる?返済期間の目安と早く完済するためのポイント
多くの学生にとって必要不可欠な奨学金ですが、その借入額は数百万円単位にものぼることが多いです。
そのため、「奨学金を借りられるのは助かるけれど、返済までに何年かかるの?」と不安を抱えている方もいるでしょう。
この記事では、奨学金返済は何年かかるのか基本的な期間の目安をお伝えしたうえで、早く完済するためのポイントや奨学金返済に役立つ支援制度について解説します。
奨学金返済の基本的な期間の目安とは?
奨学金は、原則として返還する必要のあるお金です。
基本的に支払いが免除されることはなく、就職後などに得られる給与から返済しなければなりません。
ここからは、奨学金の返済期間を決める要素など、返済に何年かかるのかについての基礎を解説します。
奨学金返済期間を決める要素
奨学金の返済期間を決める要素は次の通りです。
<奨学金返済期間を決める要素>
・奨学金の借入総額
・返還方式(定額返還方式または所得連動返還方式)
・金利の有無と利率
・救済制度活用の有無
・繰り上げ返済利用の有無
奨学金の借入総額が多いほど返済期間が長くなることが一般的です。
返還方式や金利の有無によって、元金の返済割合が変化するため、これも返済期間を決める要素になります。
また、一部の救済制度を活用すると、返済期間が延長されるため、これも返済期間を決める要素の一つです。
第一種奨学金と第二種奨学金の違い
日本学生支援機構(JASSO)では、「第一種奨学金」と「第二種奨学金」を提供しています。
いずれも返済の必要がある「貸与型」の奨学金ですが、利子の有無と審査基準が異なります。
第一種奨学金は無利子の奨学金です。
元金のみを返済するため、返済期間も短縮できます。
ただし、学力・家計いずれの選考基準も厳しく、審査通過率は低くなります。
一方の第二種奨学金は、元金に利子が付く奨学金です。
第一種奨学金と比較して返済額が増え、返済期間も延びる傾向にありますが、学力・家計いずれの基準も比較的緩やかに設定されています。
平均的な返済期間は何年?具体例で紹介
日本学生支援機構(JASSO)によると、令和3年度末時点における奨学金の平均返済期間は14.6年間です。
なお、返済期間の最長は20年間(240ヶ月)と決められています。
JASSOの場合、貸与総額に応じて返還日数を決めており、これは「奨学金返還年数算出表」から確認できます。
一例として貸与総額が100万円の場合の返済期間は9年間(108回)、貸与総額が200万円の場合の返済期間は15年間(180回)です。
奨学金返済にかかる年数を短縮する方法とは?
先述した通り、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を利用している方は、平均して14.6年間をかけて奨学金を返済しています。
つまり、22歳で就職した場合、36歳〜37歳までは月々数万円の返済が続くことになります。
奨学金返済にかかる年数を短縮したい場合は、ここでご紹介する対処法の活用を検討しましょう。
繰り上げ返済の仕組みとメリット
繰り上げ返済とは、月々に定められている奨学金返済額とは別に、元金を追加して返済する方法です。
元金が減るまでの速度が早まるため、返済期間を短縮できる可能性があります。
また、利息は元金に対して発生するため、元金を減らすことにより利息も減り、支払総額が安くなることもメリットです。
副収入を活用した返済方法
奨学金の返済に副収入を充てる対策も有効です。
近年は副業を認める企業が増えており、本業に支障が生じない範囲でアルバイトをしたり、クラウドソーシングで副収入を得たりする人も増えています。
また、株式などの投資を通じて副収入を得る人もいます。
こうして得た副収入を活用して繰り上げ返済を行い、返済期間の短縮を図るのも良いでしょう。
節約して返済資金を確保するコツ
副収入を得られない場合は、無駄遣いを減らして節約し、浮いたお金を奨学金の返済に回す方法も有効です。
節約を目指す場合は、まず月々の収入と支出を整理しましょう。
支出の内訳を確認し、無駄が生じている箇所を見つけて改善に努めるのがコツです。
特に家賃や水道光熱費といった固定費は高額になるため、家賃が安い賃貸物件に引っ越したり、電気会社やガス会社を乗り換えたりして節約を図ると良いでしょう。
利用していない、もしくは利用頻度が低いサブスクリプションを解約するなどの対策も節約につながります。
奨学金返済期間を延長する場合のメリットとデメリット
日本学生支援機構(JASSO)では、さまざまな支援制度を用意して奨学金の支払いをサポートしています。
月々の返済負担を減らしたい場合は、返済期間を延長する制度の活用も検討しましょう。
この制度を利用する場合のメリットやデメリット、そして制度活用後は完済まで何年かかるのか、その目安についてご紹介します。
返済期間を延長する制度とは?
日本学生支援機構(JASSO)では、奨学金の返済期間を延長する制度として「減額返還制度」を導入しています。
これは、月々の奨学金返済額を減額する代わりに返済期間を延長する制度です。
減額返還制度を活用することにより、月々の返済額を通常の2分の1、3分の1、4分の1のいずれかに減額できます。
また、減額返還制度の適用中は、元金に対する利息が発生しません。
そのため、経済的に困窮したとしても、奨学金の返済を続けやすくなります。
減額返還制度を利用できるのは、なんらかの事情によって経済的に困窮している人物です。
災害による被災や傷病による入院といった理由により就業が難しいと判断された方だけが利用できます。
延長による月々の負担軽減効果
減額返還制度などの返済期間を延長する制度を利用することにより、月々の返済額を減らせるため、返済による経済的な負担を軽減できます。
一例として、月々10,000円を借りている場合の返済額を見てみましょう。
<減額返還制度の利用例>
・2分の1に減額した場合…月々5,000円
・3分の1に減額した場合…月々3,333円
・4分の1に減額した場合…月々2,500円
減額により、奨学金の支払いに充てていた金額の一部を手元に残せるため、生活を立て直しやすくなります。
延長による総返済額増加のリスク
日本学生支援機構(JASSO)の減額返還制度を利用する場合、先述した通り、減額を適用している期間中に利息が発生しないため、返済総額が上がるリスクはありません。
ただし、その他の債権者が実施する延長制度を利用すると、利息が発生する期間が増えるため、返済総額が増加する可能性があります。
利用している機関の規約を細かく確認し、返済総額増加のリスクがあるか調べておきましょう。
返済期間を決める際に知っておくべき注意点
奨学金を借りる場合、原則として借入額が大きくなるほど返済期間が長くなります。
返済期間から逆算して借入額を決めたい場合に知っておくと良い注意点は、これからお伝えする3つです。
将来の生活を破綻させないために、綿密な返済計画を立てたうえで奨学金の利用を申請しましょう。
収入状況を考慮した返済計画の重要性
収入状況を考慮して返済計画を立てるべき理由は、将来の奨学金滞納リスクを減らすためです。
万が一奨学金の滞納を続けてしまうと、個人信用情報機関に滞納情報が登録されてしまいます。
いわゆるブラックリストに載ると、住宅ローンを組めなくなったり、クレジットカードの発行ができなくなったりといった影響が生じかねません。
また、将来的には結婚や出産、住宅の購入、老後の生活といったライフイベントの発生も考慮する必要があります。
奨学金の返済ができたとしても、これらのライフイベントの発生に伴い、必要な資金を捻出できない状態は生活の質が高いとは言えないでしょう。
このような問題を避けるために、収入状況を考慮した返済計画を立てることが大切です。
金利が返済期間に与える影響
奨学金の金利が高ければ高いほど、返済額を占める利息の割合が増えるため、元金の返済が遅れます。
その結果として、返済期間が長くなることが注意点です。
変動金利型の奨学金を利用する場合、社会情勢の影響により返済途中で金利が上昇する可能性があり、これが原因で返済額が増えたり、返済期間が延びたりする場合があることにも注意しましょう。
無理のない返済計画を立てるポイント
無理のない返済計画を立てるうえで重要なのは、奨学金の返済状況や収入と支出を正確に把握することです。
無理なく支払える奨学金の返済額は、手取りの10%が理想とされています。
仮に手取りの月収を20万円と想定する場合は、月々の奨学金返済額を2万円以内に抑えると良いでしょう。
奨学金返済期間をシミュレーションする方法
奨学金の返済期間は、借入総額や利息などの複雑な要素の影響を受けて決まるため、手動で計算することは困難です。
ここでは、奨学金返済期間を簡単にシミュレーションする方法として、シミュレーションツールの活用方法や具体的なシミュレーション例、そして返済計画を立てるコツを解説します。
シミュレーションツールの活用方法
日本学生支援機構(JASSO)では、奨学金の返済に何年かかるのかを可視化するためのシミュレーションツールを提供しています。
シミュレーションツールの活用方法は次の通りです。
<シミュレーションツールの活用方法>
・ステップ1:JASSOの公式ホームページから「奨学金貸与・返還シミュレーション」を開く
・ステップ2:入学粘度や奨学金の種類、金利などの情報を入力する
・ステップ3:「シミュレーション結果を確認する」ボタンをクリックする
・ステップ4:総貸与額、月々の返済額、返済期間、総返済額が表示される
必要事項を入力するだけで、自動的に返済に何年かかるのかの目安が表示されるため、誰でも簡単にシミュレーションできるでしょう。
具体的なシミュレーション例を紹介
実際に日本学生支援機構(JASSO)のシミュレーションツールを利用して、返済までに何年かかるのかをシミュレーションしてみます。
今回は以下の内容でシミュレーションを実行しました。
【シミュレーション例】
学校の種類:大学(学部)
奨学金の種類:第二種奨学金(利息型・貸与型)
入学年度:2025
入学時特別増額貸与奨学金:200,000円
賞与明細:2025年4月〜2028年3月
返還開始年月:2028年10月
月額:50,000円
貸与利率:1.641%
機関保証制度:利用しない
上記の場合、返還期間は2028年10月〜2024年9月までの14年間です。
借入総額は200万円ですが、利息を含めた返還総額は225万9,144円です。
返還回数は168回で、通常1万3,447円、最終月は1万3,495円となります。
シミュレーション結果をもとに計画を立てるコツ
資金計画を立てるコツは、シミュレーション結果で表示された月々の返済額が無理なく支払える金額かどうかを考えることです。
先ほどのシミュレーションでは、14年間にわたり毎月1万3,447円を支払うことになります。
無理なく返済できる金額は手取りの10%以内なので、約14万円以上の月収を見込める場合は、奨学金を無理なく返済できると考えて良いでしょう。
奨学金返済に役立つ支援制度や相談窓口
綿密なシミュレーションを行って返済計画を立てても、突発的な事情により奨学金の返還が難しくなる可能性があります。
その場合に利用できる支援制度や相談窓口について知っておきましょう。
奨学金返済支援制度を活用する方法
奨学金返済支援制度とは、奨学生の返済負担を軽減することを目的に、企業や団体が実施する支援制度です。
「企業による奨学金返還支援(代理返還)制度」が代表的な例であり、利用すると月々の奨学金返済を企業に肩代わりしてもらえます。
ただし、これはあくまでも企業が用意する福利厚生の一環です。
すべての企業が用意する制度ではないため注意しましょう。
返済が困難な場合の相談窓口
奨学金の返済が困難になった場合は、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金相談センターに連絡しましょう。
ここでは、返済負担を軽減する制度の案内や必要書類を集めるためのアドバイスなどを受けられます。
奨学金の滞納が発生し、一括返済などの請求を受けた場合は、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談しましょう。
法テラスを利用すると、借金問題全般の無料相談ができるほか、弁護士費用などの立て替え制度を利用できます。
条件変更や猶予制度の利用方法
支援制度を利用したい場合は、滞納が発生する前に日本学生支援機構(JASSO)の奨学金相談センターに連絡しましょう。
利用する制度が決まった場合は、スカラネット・パーソナルを利用したオンライン申請、または郵送で条件変更・猶予制度適用の申し込みができます。
奨学金返済期間を見直すタイミングとは?
奨学金の返済期間を見直すことにより、月々の返済額を軽減したり、支払期間を短縮させて将来の負担を減らしたりすることが可能です。
ここでは、奨学金返済を見直すのに適したタイミングをご紹介します。
収入が変化した場合の見直し方法
当初の予定よりも収入が増えた場合は、繰り上げ返済を検討しましょう。
返済総額を減らせることに加えて、返済期間を短縮できる場合もあり、奨学金の完済を早められます。
反対に休職や失職、退職などにより収入が減った場合は、返済期間を延長して支払総額を減らすことがおすすめです。
家計状況の変化を考慮した見直しポイント
結婚や出産、住宅購入といったライフイベントが発生したタイミングは家計状況が変化しやすくなります。
これらのタイミングでは、将来的に発生する可能性のある出費を計算に含めて、奨学金の返済額が無理のない範囲内に収まるかシミュレーションしましょう。
奨学金の返済負担が大きい場合、返済期間を延長し、月々の返済額を抑える対策を採ると効果的です。
長期的な返済計画を立てる重要性
先述したライフイベントに加えて、将来的には老後資金が必要です。
また、病気や会社の倒産といったトラブルにより、計画通りの返済が困難になる可能性もあるでしょう。
そのため、奨学金は長期的な返済計画を立てることが重要です。
特に繰り上げ返済をする場合は、預貯金を使い果たすことは避けて、緊急用に3ヶ月〜6ヶ月分の生活費を手元に残しておきましょう。
まとめ
奨学金の返済期間が何年かかるのかは、さまざまな要素によって決まるため一概には言えません。
日本学生支援機構(JASSO)が公開した令和3年度のデータによると、平均的な返済期間は14.6年間です。
奨学金の返済は長期間にわたって続きます。
その間にさまざまなライフイベントが発生する可能性があるため、長期的な返済計画を立て、状況に応じて支援制度の利用も検討しましょう。










