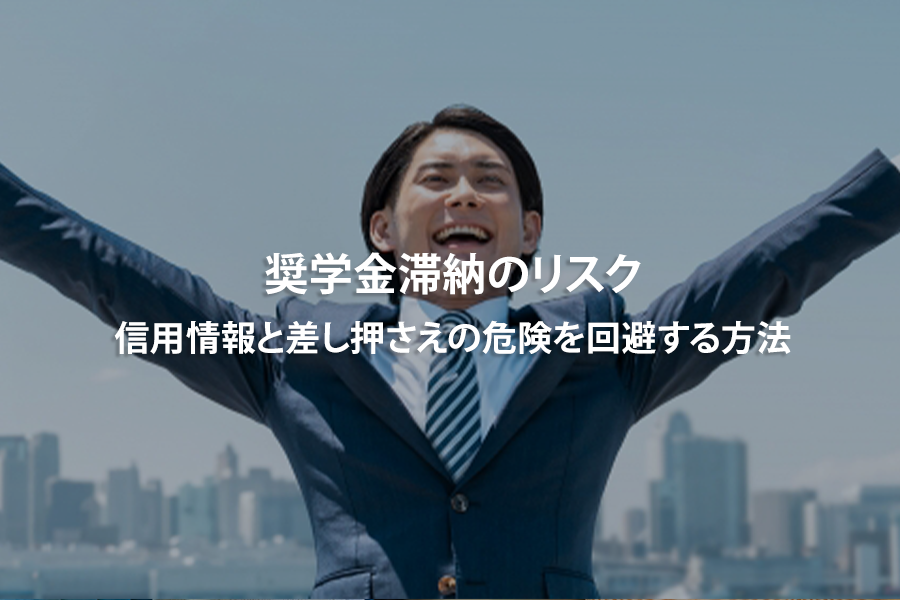
奨学金は給付金とは異なり、返済義務のあるお金です。そのため、滞納してしまうと信用情報に大きな影響を与え、最悪の場合は裁判や給与の差し押さえにまで発展する可能性があります。本記事では、奨学金滞納のリスクや対策、計画的な返済のコツについて解説します。
奨学金の滞納とは?基本を押さえよう
奨学金を滞納すると、さまざまな不利益を被る可能性があります。まずは、滞納の定義やその影響について理解しましょう。
奨学金の返済期限と滞納の定義
奨学金の返済期間は最長20年と決まっています。この期間内に、借りた奨学金を完済する必要があります。
- **第一種奨学金(無利子)**の場合、利息がかからないため、返済期間を長めに設定しても負担が増えることはありません。
- **第二種奨学金(有利子)**の場合、返済期間が長くなるほど利息の総額が増えるため、早めの完済を目指す方が経済的な負担を減らせます。
滞納の定義
奨学金の滞納とは、決められた期日までに支払うべき金額を支払わないことを指します。滞納が発生すると、督促が行われ、その後の状況によっては信用情報機関に記録されることになります。
滞納するとどうなる?段階的な流れを解説
万が一、奨学金を支払えずに滞納してしまった場合、次のような流れで進行します。
- 振替不能(1回目)
- 翌月の振替日に、未納分と当月分をまとめて引き落としされる。
- この時点では、遅延金は発生しない。
- 振替不能(2回目)
- 遅延金が発生する。
- 奨学金を借りた本人と連帯保証人の両方に督促の電話・書面が送られる。
- 振替不能(3回目以降)
- 債権回収会社(サービサー)による強制徴収が開始。
- 信用情報機関(いわゆる「ブラックリスト」)に延滞情報が登録される。
この状態になると、クレジットカードの新規作成や住宅ローンの審査に通らなくなる可能性が高くなります。
第一種・第二種で滞納時の扱いは違うのか?
第一種奨学金(無利子)であっても、滞納の扱いは第二種奨学金(有利子)と同じです。
滞納すると、個人信用情報機関に延滞情報が記録され、保証機関が代理で返済を行う「代位弁済」が発生すると、さらに信用情報に悪影響を及ぼします。
奨学金を滞納すると発生するリスク
奨学金はクレジットカードやローンと同じように、滞納すると重大なリスクを伴います。放置すれば、延滞金の発生や信用情報の悪化、最悪の場合は裁判や給与差し押さえといった事態に発展する可能性があります。ここでは、奨学金を滞納した場合の具体的なリスクについて解説します。
延滞金が発生し、返済額が増加する
奨学金の返済が1回目の振替不能であれば遅延金は発生しませんが、2か月連続で滞納すると遅延金が発生します。
特に**第二種奨学金(有利子)**の場合、もともと利息が付くため、滞納による遅延金が加算されると、さらに返済総額が増加してしまいます。
また、奨学金の遅延金はすぐにストップするわけではなく、次回の引き落とし日まで発生し続けます。
仮に滞納を解消するために途中で全額支払ったとしても、その期間分の遅延金が請求されることになるため、負担が大きくなってしまいます。
信用情報(ブラックリスト)に登録される可能性
奨学金の滞納が4か月以上続くと、信用情報機関に金融事故として記録され、いわゆる「ブラックリスト」に登録される可能性があります。
ブラックリストに登録されると、個人信用情報機関(CICやJICCなど)に金融事故として記録され、あらゆる金融取引に影響を及ぼします。
信用情報に記録されるまでの流れ
- 1~3か月の滞納 → 督促状や電話連絡が届くが、信用情報には影響なし
- 4か月以上の滞納 → 信用情報機関に延滞情報が記録される(ブラックリスト入り)
- 5か月以上の滞納 → 記録が5~10年間残り、各種ローンやクレジットカードの審査が厳しくなる
一度ブラックリストに登録されると、仮に滞納分を全額支払ったとしても、一定期間は信用情報に記録が残ってしまいます。
クレジットカードや住宅ローンの審査に影響する
奨学金を滞納すると、新規のクレジットカード発行や住宅ローンの審査に悪影響を及ぼします。
クレジットカードの審査
クレジットカードの申請時には、信用情報機関を通じて過去の延滞履歴がチェックされます。
ブラックリストに登録されると、クレジットカードの審査に通らなくなる可能性が高まります。
※ただし、信用情報の基準はカード会社ごとに異なるため、一部のカード会社では審査を通過できるケースもあります。
住宅ローンや自動車ローンの審査
住宅ローンや自動車ローンは高額な借入となるため、クレジットカード以上に信用情報が厳しくチェックされます。
そのため、奨学金の滞納履歴があると、審査に落ちる、または希望通りの融資額が受けられないといった事態になる可能性があります。
ブラックリストから情報が消えるまで5~10年かかるため、滞納が原因で住宅購入のタイミングを逃してしまうケースもあります。
最悪の場合、裁判や給与差し押さえの可能性も
奨学金を長期間滞納すると、最終的には裁判や給与差し押さえに発展する可能性があります。
1~2か月程度の滞納であれば、返済を再開すればすぐに大きな問題にはなりません。
しかし、2か月以上滞納すると、日本学生支援機構(JASSO)から督促状が届き、電話による催促も行われるようになります。
滞納を放置するとどうなる?
- 3か月以上の滞納 → 本人・連帯保証人・保証人に対して催促が強化される
- 6か月以上の滞納 → 裁判所を通じた「支払督促申立て」が行われる可能性が高まる
- 最終的に裁判へ発展 → 給与の差し押さえや財産の差し押さえが実行される場合もある
支払督促を受けた場合、異議申し立てを行わなければ、そのまま裁判で確定し、給与差し押さえなどの強制執行が行われることになります。
滞納の初期段階で適切に対応すれば、こうした最悪の事態を避けることが可能です。
奨学金を滞納しないための対策
奨学金を滞納すると、最悪の場合、裁判や給与の差し押さえといった深刻な事態に発展してしまいます。そうならないためには、あらかじめ対策を講じることが大切です。ここでは、奨学金の滞納を防ぐための具体的な方法を紹介します。
減額返還制度を活用し、返済負担を軽減する
仕事が思うようにいかず、収入が減って返済が困難になった場合は、減額返還制度の利用を検討しましょう。この制度を活用すると、毎月の返済額を最大で1/2または1/3まで減額することができます。
- 申請期間:1回の申請で最長12か月適用
- 最大利用期間:通算15年まで適用可能(再申請が必要)
減額返還制度を利用すれば、収入が回復するまでの間、無理のない金額で返済を続けられます。ただし、適用期間中に2回連続で返済が滞ると、ペナルティとして遅延金の発生や減額返還の取り消しといった措置が取られることがあるため、注意が必要です。減額返還を利用する際も、必ず口座に必要な金額を確保しておきましょう。
返済猶予制度で一時的に支払いを停止する
突然の病気やケガで長期間働けなくなるなど、減額返還制度を利用しても支払いが厳しい場合は、返済猶予制度の利用を検討しましょう。この制度を利用すると、一定期間、返済を先送りすることが可能です。
- 申請期間:1回の申請で最長12か月適用
- 最大利用期間:通算10年まで適用可能(再申請が必要)
例えば、病気や入院で長期間療養が必要になった場合、猶予期間中は奨学金の返済が免除されます。ただし、返済が免除されるわけではなく、支払いが先延ばしになるだけなので、利用する際は注意が必要です。
奨学金返済支援のある企業に転職する
奨学金の返済が負担になっている場合は、奨学金返済支援制度(代理返還)を導入している企業に転職するという選択肢もあります。これは、企業が社員の奨学金返済をサポートする制度で、企業が日本学生支援機構(JASSO)に直接支払いを行う仕組みです。
- 支援方法:企業が奨学金返済額の一部または全額を負担
- 対象企業:一部の大手企業や成長企業、福利厚生が充実している企業など
この制度を利用すれば、自身の負担を軽減しながら着実に奨学金を完済できるため、転職を考えている人は、奨学金返済支援制度を導入している企業を探してみるのも良いでしょう。
滞納してしまった場合の対処法
奨学金の返済を滞納しないことが理想ですが、万が一支払いができなくなった場合は、早急に対応することが重要です。焦ってしまうかもしれませんが、適切な対処を行うことで、裁判や給与差し押さえといった最悪の事態を防ぐことができます。ここでは、滞納時の具体的な対処法について解説します。
滞納に気づいたらすぐにJASSO(日本学生支援機構)へ相談する
「支払期日をうっかり忘れてしまった」「来月も支払いが厳しそう」――このような状況になった場合は、できるだけ早くJASSO(日本学生支援機構)に相談しましょう。
重要なのは、滞納を放置せずに自ら対処することです。
- 最初の1か月の滞納では、すぐにブラックリスト入りすることはありません。
- しかし、滞納が続くと信用情報に影響を与え、将来のローン審査や賃貸契約に悪影響を及ぼす可能性があります。
- JASSOに相談すれば、返済猶予制度などの救済措置を案内してもらえます。
JASSOは、奨学金返済に関する相談を受け付けており、対応も柔軟です。相談したからといって責められることはありませんので、滞納に気づいた時点で迷わず連絡するようにしましょう。
分割払い・一括払いの交渉方法
奨学金の滞納が続いてしまった場合は、JASSOに連絡し、分割払いや一括払いの交渉を行うことが可能です。その際には、できるだけ事前に支払いの準備をしておくことが大切です。
交渉のポイント
- 一括払いが可能であれば、できる限り早めに支払うのが理想的。
- 分割払いを希望する場合は、JASSOに状況を説明し、具体的な返済プランを提案する。
- 返済期間猶予制度の適用条件を確認する。
返済期間猶予制度の適用条件
JASSOの返済期間猶予制度は、以下のようなやむを得ない事情がある場合に適用されます。
- 病気やケガで長期間の療養が必要
- 失業や収入減少により経済的困難がある
- 自然災害などの影響で返済が難しい
注意点:
- ギャンブルや浪費による支払い不能の場合、制度の適用は難しい可能性があります。
- 滞納後に交渉する場合、減額返還制度の利用はできないため、返済期間猶予制度を活用するしかありません。
JASSOの担当者に自分の状況を正直に伝え、可能な範囲で返済計画を立てることが大切です。誠実に対応すれば、多少の柔軟な対応をしてもらえるケースもあります。
債務整理(任意整理・自己破産)を検討する場合の注意点
奨学金の返済が困難なだけでなく、ほかのローンや借金も抱えている場合、債務整理を検討するのも一つの選択肢です。ただし、債務整理には信用情報への影響や一定のデメリットがあるため、慎重に判断する必要があります。
まずは弁護士や司法書士に相談し、自分に合った解決策を見つけることが大切です。
任意整理を選択する場合
「官報に掲載されたくない」「利息をなくせば返済できそう」――このような場合は、任意整理を検討すると良いでしょう。
任意整理とは?
- 利息をカットし、元本のみの返済計画を立て直す手続き
- 裁判所を通さずに債権者(JASSOなど)と交渉して和解する
- 遅延損害金が発生している場合、それを減額または免除してもらえる可能性がある
- ブラックリスト(信用情報機関への登録)にはなるが、官報には載らない
ただし、任意整理はすべてのケースに適用できるわけではありません。特に、奨学金のように比較的低金利の借り入れには、任意整理のメリットが少ない可能性があります。
また、裁判所を通す手続きではないため、強制執行(給与差し押さえなど)を止めることはできません。すでに裁判手続きが進んでいる場合、任意整理では解決が難しいことを理解しておきましょう。
個人再生や自己破産を選択する場合
すでに仮執行宣言付支払督促(強制的な一括返済請求)を受けており、返済の見込みがない場合は、個人再生または自己破産を検討することになります。
個人再生
- 裁判所を通じて、借金を最大で1/10程度まで減額
- 3〜5年の計画で返済を行う
- 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを残すことが可能
- 安定した収入が必要(正社員や継続的な収入のあるフリーランスなど)
個人再生は、奨学金の元本が大きい場合に有効な手段となりますが、正社員や安定収入がないと利用できない可能性があるため注意が必要です。
自己破産
- 裁判所の手続きによって借金がすべて免責(返済不要)
- 奨学金も支払い義務がなくなる
- 財産(自宅や車など)がある場合、手放す必要がある
- 官報に氏名が掲載される
- 信用情報(ブラックリスト)に10年程度登録され、新規ローンやクレジットカードが作れなくなる
自己破産は、借金をゼロにできる最終手段ですが、それに伴うデメリットも非常に大きいため、慎重に判断することが求められます。
債務整理を検討する際の注意点
- 安易に自己破産を選ばず、まずは任意整理や個人再生を検討する
- 弁護士や司法書士に相談し、最適な方法を見極める
- 信用情報や財産への影響を考慮した上で決断する
債務整理は「生活を立て直すための手段」ですが、信用情報に与える影響が長期にわたるため、慎重な選択が必要です。弁護士への相談を早めに行い、自分にとって最適な解決策を見つけましょう。
奨学金の返済を計画的に行うために
奨学金の返済を深く考えずにいると、万が一正社員として働けなくなった場合や収入が減った時に大きな負担となります。
そのため、早い段階から計画を立てておくことが重要です。以下のポイントを押さえて、計画的な返済を心がけましょう。
収入と支出を見直し、返済計画を立てる
まずは、自身の収入と支出のバランスを確認し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
支出の内訳を把握する
- 固定費(家賃、光熱費、通信費、保険料など)
- 変動費(食費、交際費、娯楽費など)
- 特別支出(年に1回の税金や冠婚葬祭費用など)
特に変動費は時期によって増減があるため、年間を通して支出を見直すことがポイントです。
返済シミュレーションを活用する
自分で計算するのが難しい場合は、**日本学生支援機構(JASSO)の「返還シミュレーション」**を活用してみましょう。
借入額や返済方法を入力することで、具体的な返済計画を確認できます。
JASSO公式サイトの「返還シミュレーション」を活用することで、毎月の返済額や返済総額の目安を把握できます。
副業や節約で返済資金を確保する
返済負担を軽減するために、支出の見直しや副業による収入アップも検討しましょう。
節約のポイント
- 外食の回数を減らし、自炊を心がける
- 電気・ガス・水道の使用を見直す
- 携帯電話のプランを見直し、格安SIMに変更
- 無駄なサブスクリプション(動画配信・音楽サービスなど)を解約
- 買い物の際にポイントやキャッシュレス決済を活用する
月に1万円の節約ができれば、年間で12万円の余裕が生まれます。
副業で収入を増やす
節約だけでは不十分な場合、副業で収入を増やすのも有効です。
- 隙間時間にできるアルバイトや短期の仕事
- スキルを活かしたオンライン副業(ライティング・デザイン・動画編集など)
- フリマアプリで不要なものを売る
- ブログやYouTubeで収益化を目指す
月に2~3万円でも追加収入があれば、返済負担を大幅に軽減できるでしょう。
家族と相談し、援助を受けることも検討する
奨学金の返済が厳しくなった場合、家族に相談することも選択肢の一つです。
- 「家族に迷惑をかけたくない」と思うかもしれませんが、最悪の事態(裁判・給与差し押さえなど)になる前に相談することが大切です。
- 一時的に支援を受けて、収入が安定したら少しずつ返済する方法もあります。
- 金銭的な支援が難しい場合でも、家賃や食費のサポートを受けることで返済資金を確保できる可能性があります。
家族と話し合い、無理のない範囲で支援を受けることも検討してみましょう。
まとめ|滞納リスクを理解し、計画的な返済を心がけよう
奨学金を滞納してしまうと、信用情報(ブラックリスト)に登録される可能性があるだけでなく、最悪の場合は裁判や給与の差し押さえに発展するリスクもあります。
滞納による負担を避けるために、以下のポイントを意識しましょう。
滞納に気づいたらすぐにJASSO(日本学生支援機構)へ相談する
減額返還制度や返済猶予制度を活用し、負担を軽減する
支出を見直し、節約や副業で返済資金を確保する
家族と相談し、必要に応じて援助を受けることも検討する
奨学金は計画的な返済が何よりも重要です。
将来の負担を減らすためにも、早めの対策と適切な返済計画を心がけましょう。










