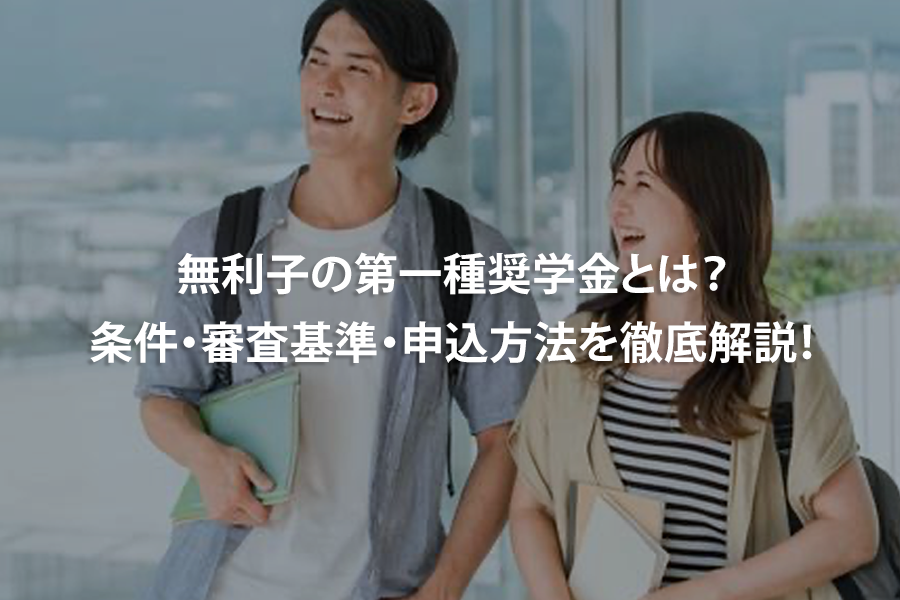
奨学金を借りた場合、卒業後には返済が必要になります。
返済の負担を軽減したい人は、無利子の「第一種奨学金」の利用を検討すると良いでしょう。
本記事では、第一種奨学金の基本情報・審査基準・申込方法について詳しく解説します。
返済方法や上手な活用方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
第一種奨学金とは?基本を理解しよう
まずは、第一種奨学金の特徴や、他の奨学金との違いを解説します。
無利子のメリットや注意点についても確認しましょう。
第一種奨学金の特徴と他の奨学金との違い
第一種奨学金は、日本学生支援機構(JASSO)が提供する「貸与型奨学金」です。
家庭の経済的事情により進学が困難な学生を支援することを目的としており、無利子で学費や生活費を借りることができます。
他の奨学金との違い
| 項目 | 第一種奨学金(無利子) | 第二種奨学金(有利子) | 給付型奨学金 |
|---|---|---|---|
| 利子 | なし | あり(年利上限3.0%) | なし |
| 返済義務 | あり | あり | なし |
| 審査基準 | 学業・家計基準が厳しい | 学業基準は緩め | 世帯収入・学力基準あり |
第一種奨学金は、無利子で借りられる点が最大のメリットですが、審査基準が厳しいという特徴があります。
特に、学業成績や家計基準を満たしていないと申請が通らないため、注意が必要です。
無利子であることのメリットと注意点
✅ 第一種奨学金のメリット
- 利息が発生しないため、返済負担が軽い
- 借りた金額のみを返済すれば良い(第二種のように利息が増えない)
- 卒業後の返済計画が立てやすい
⚠ 第一種奨学金の注意点
- 審査基準(学業・家計基準)が厳しい
- 貸与金額が限られている(私立の学費全額を賄えない可能性あり)
特に、第一種奨学金の学業基準・家計基準は細かく定められており、条件を満たさないと申請が通りません。
事前に自分が該当するか確認しておくことが重要です。
誰が対象となるのか?第一種奨学金の条件をチェック
第一種奨学金を受けるには、JASSOが定める「学業基準」と「家計基準」を満たす必要があります。
また、申し込み時期によって「予約採用(進学前)」と「在学採用(進学後)」に分かれるため、条件が異なります。
第一種奨学金の審査基準(予約採用・在学採用)
1. 予約採用(高校在学中の申し込み)
高校3年生の間に申し込む「予約採用」は、進学前に奨学金の可否が決まるため、計画が立てやすいというメリットがあります。
学業基準
- 高校の評定平均が3.5以上(5段階評価)
- 高等学校卒業程度認定試験の合格者
- 以下の条件を満たす場合は評定平均不問
- 生計維持者(親など)の貸与額算定基準が0円
- 生活保護受給世帯
- 社会的養護が必要な人(児童養護施設出身など)
家計基準
- 生計維持者(親など)の貸与額算定基準額が189,400円以下
- 第一種+第二種を併用する場合は164,600円以下
2. 在学採用(大学入学後の申し込み)
大学入学後に申し込む「在学採用」は、高校時点で予約しなかった人向けの制度です。
ただし、進学後に申し込む場合でも、審査基準は予約採用とほぼ同じです。
学業基準
- 高校最終2年間の評定平均が3.5以上
- 専門学校(専門課程)の場合は3.2以上
- 高等学校卒業程度認定試験の合格者
- 以下の条件を満たす場合は評定平均不問
- 生計維持者(親など)の貸与額算定基準が0円
- 生活保護受給世帯
- 社会的養護が必要な人(児童養護施設出身など)
- 入学者選抜試験の成績が上位50%以内
- 将来自立し活躍する意欲を有していると判断される場合
家計基準
- 生計維持者(親など)の貸与額算定基準額が189,400円以下
- 進学先や年度によって基準額が変わるため、最新の情報をJASSOの公式サイトで確認することを推奨
第一種奨学金の審査を通過するポイント
第一種奨学金は、申請すれば必ず受給できるわけではありません。
事前に審査を通過しやすくするための対策を考えましょう。
✅ 学業成績を向上させる
- 評定平均3.5以上が基本のため、定期テストや課題の成績を意識する
✅ 家計基準の確認
- 自分の家庭の収入が基準額を満たしているか事前にチェック
✅ 申請時期を間違えない
- 予約採用は高校3年生の5月~6月が申請期間
- 在学採用は大学入学後の4月~7月 or 10月が申請期間
第一種奨学金の申込方法とスケジュール
第一種奨学金を受けるためには、決められたスケジュールに沿って申し込みを行う必要があります。
また、高校生と大学生では申込方法が異なるため、手続きの流れを事前に確認しておきましょう。
ここでは、申込方法・必要書類・申込期限を守るポイントを詳しく解説します。
高校生と大学生で異なる申込方法
高校生(予約採用)
対象者:進学予定の高校3年生(最大2浪まで申し込み可)
- 申込方法:在籍している高校で必要書類を受け取る
- 募集時期:春募集(4月下旬~7月下旬)/秋募集(10月頃)
- 進学先が決まっていなくても申し込み可能
✅ 2浪までであれば、在籍していた高校で申し込むことができます。
ただし、申し込みの可否は高校ごとに異なるため、事前に確認しましょう。
大学生(在学採用)
対象者:大学・短期大学・専門学校に在学中の学生
- 申込方法:在籍している大学で必要書類を受け取る
- 募集時期:春募集(4月上旬~6月下旬)/秋募集(9月~11月)
- 申込期間は大学ごとに異なるため、事前確認が必須
申し込みの流れと必要書類
第一種奨学金の申し込みは、以下の流れで進めます。
手続きをスムーズに行うため、事前に必要書類を準備しておきましょう。
📌 申し込み手順
- 学校で奨学金説明会に参加(参加が必須)
- 必要書類を受け取り、内容を確認
- スカラネット(JASSOのオンライン申請システム)で申し込み
- 必要書類を準備し、各機関へ提出
- 審査結果の通知を待つ
- 採用決定後、奨学金の受け取り開始
📌 申請に必要な書類
申し込みには、以下の書類が必要です。
🔹 JASSOに提出する書類
- マイナンバー提出書
- 番号確認書類
- 身元確認書類
🔹 学校に提出する書類
- 提出書類一覧表
- 奨学金確認書(給付型・貸与型)
- 個人信用情報の取扱いに関する同意書
🔹 必要に応じて提出する追加書類
- 在留資格の証明書類(外国籍の方)
- 施設等の在籍証明書
- 年収等の実績計算書
- 収入証明書
- 海外居住者のための収入等申告書
スカラネットでの申し込み方法
スカラネットは、日本学生支援機構(JASSO)が提供する奨学金のオンライン申請システムです。
申し込みはスカラネットを通じて行うため、必ず利用方法を確認しておきましょう。
📌 スカラネットの申請手順
- ユーザーID・パスワードを登録し、ログイン
- 必要事項を入力(希望する奨学金の種類・世帯収入・学業成績など)
- 入力が完了すると「受付番号」が表示されるのでメモを取る
- 書類を準備し、学校またはJASSOに提出
- 審査結果の通知を待つ
スカラネットに初めてログインする場合は、アカウントの登録が必要になります。
申し込み後は、受付番号を忘れずに控えておきましょう。
申込期限を守るためのポイント
第一種奨学金は、申込期限を過ぎると次回の募集まで待つことになるため、期限管理が重要です。
✅ スカラネットの入力期限を厳守
➡ 期限内に入力を完了しないと申し込みが無効になる
✅ JASSOへの書類提出期限を確認
➡ マイナンバー提出書などは郵送期限があるため、余裕をもって準備する
✅ 学校への提出期限をチェック
➡ 学校ごとに期限が異なるため、説明会の際に確認
💡 申込期限を忘れないための対策
- カレンダーに記入してリマインダーを設定
- 目立つ場所に期限を書いたメモを貼る
- スマホのアラームやスケジュールアプリを活用する
申し込み期限を守るためには、スケジュール管理を徹底することが大切です。
第一種奨学金の審査基準を詳しく解説
第一種奨学金を受けるには、厳格な審査基準を満たす必要があります。
主に「学業成績」と「家計状況」が評価されるため、申請前に確認しておきましょう。
審査で重視される基準とは?
第一種奨学金の審査では、以下の2つの基準が特に重要視されます。
📌 1. 学業基準
- 予約採用(高校在学中):評定平均 3.5 以上(5段階評価)
- 在学採用(大学入学後):高校最終2年間の評定平均 3.5 以上
- 専門学校(専門課程)の場合は 3.2 以上
- 高等学校卒業程度認定試験の合格者も対象
⚠ 例外措置
以下の条件を満たす場合、成績基準を満たしていなくても申請可能です。
- 生計維持者(親など)の貸与額算定基準が 0 円
- 生活保護受給世帯
- 社会的養護が必要な人(児童養護施設出身など)
📌 2. 家計基準
- 生計維持者(親など)の貸与額算定基準額が 189,400 円以下
- 収入の上限目安(2人世帯の場合)
- 給与所得者:716万円以下
- 給与所得者以外(自営業など):546万円以下
家計の収入状況に基づき、奨学金の貸与額が決まります。
審査基準を満たしているかどうか、事前にJASSOの公式サイトで最新情報を確認しましょう。
審査の詳細と選考プロセス
第一種奨学金を利用するには、申し込み時点で審査基準を満たしていることが必須です。
学業成績や家計状況のいずれかが基準を超えている場合、不採用となる可能性があります。
📌 選考プロセス
- 申し込み(スカラネット経由)
- 学校での審査・推薦
- JASSOによる審査
- 結果通知(申請から約2ヶ月後)
- 春申請:6月~8月頃
- 秋申請:11月~1月頃
- 採用決定後の手続き
- 「返還誓約書(借用証書)」を提出(期限厳守)
📌 申請書類に不備があると審査に時間がかかるため、事前にしっかり確認しましょう。
選考に落ちた場合の対処法
第一種奨学金の選考結果は、学校を通じて書面で通知されるほか、スカラネットでも確認可能です。
📌 再申請の方法
- 予約採用で不採用だった場合 → 在学採用で再申請
- 家計基準で落ちた場合 → 家計急変時の特別申請が可能
📌 他の奨学金を検討する
第一種奨学金が利用できない場合、以下の選択肢を検討しましょう。
- 第二種奨学金(有利子)を申請する
- 地方自治体や民間企業の奨学金を探す
- 教育ローンを利用する(日本政策金融公庫など)
第一種奨学金の返済方法と返済開始時期
第一種奨学金は、無利子で借りられる貸与型奨学金ですが、卒業後の返済義務があります。
ここでは、返済の開始時期や返済方法、返済計画の立て方について解説します。
返済が始まるタイミングと返済方法
📌 返済開始時期
- 貸与終了後の 7 ヶ月目から返済開始
- 例:3月卒業の場合 → 10月から返済開始
- 返済期間は最大20年(貸与額により変動)
📌 返済方法
第一種奨学金の返済は、以下の2つの方式から選択できます。
| 返済方式 | 特徴 |
|---|---|
| 定額返還方式 | 毎月の返済額が一定 |
| 所得連動返還方式 | 前年の所得に応じて毎月の返済額が変動 |
- 一定額を毎月支払いたい場合 →「定額返還方式」
- 収入に応じて返済額を調整したい場合 →「所得連動返還方式」
⚠ 所得連動返還方式は、一定の所得額を超えると返済額が増加するため注意が必要です。
無利子であることの返済面でのメリット
第一種奨学金は無利子であるため、第二種奨学金と比較すると返済負担が軽くなります。
📌 返済額の目安
- 毎月の返済額は貸与金額によって異なるが、1万~2万円程度が目安
- 利息が発生しないため、返済額が明確で計画が立てやすい
返済計画の立て方と返済のコツ
第一種奨学金の返済は、口座振替(自動引き落とし)で行われます。
引き落とし日に口座残高が不足していると、延滞扱いとなるため注意しましょう。
📌 返済遅延のリスク
- 延滞すると遅延損害金が発生
- 延滞が続くとブラックリスト(信用情報機関に登録)に載る可能性あり
- 連帯保証人に一括返済の請求が行く場合もある
📌 返済をスムーズに進めるコツ
✅ 返済スケジュールを把握し、事前に貯蓄をしておく
✅ 家計簿をつけて、収支を管理する
✅ 生活費を見直し、無駄な出費を減らす
✅ 厳しい場合は「返還期限猶予制度」や「減額返還制度」を活用する
無理のない返済計画を立てることが、奨学金の負担を軽減するポイントです。
第一種奨学金の返済に関する制度と特例
第一種奨学金は無利子の貸与型奨学金ですが、卒業後の返済義務がある点に注意が必要です。
しかし、病気や失業などの事情で返済が困難になった場合、返済猶予制度や減額返還制度を利用することで負担を軽減できます。
ここでは、返済制度の詳細と返済免除の条件について解説します。
返済猶予・減額返還制度の利用方法
奨学金の返済は、原則として毎月行わなければなりませんが、所得の減少や失業、病気などで支払いが困難になった場合、救済制度を活用できます。
📌 返済猶予制度
- 奨学金の返済期限を最長10年(120か月)延長できる制度
- 1年ごとに更新申請が必要
- 申請には、返済困難な理由を証明する書類が必要
- 例:医師の診断書、雇用保険受給資格者証 など
申請方法は、郵送またはスカラネット・パーソナル(オンライン)で手続き可能です。
この制度を利用すれば、一時的に返済をストップできるため、生活が安定するまで負担を軽減できます。
📌 減額返還制度
- 毎月の返済額を半額に減らし、返済期間を延長できる制度
- 1回の申請で最大1年間適用(最長15年まで延長可能)
- 住民税非課税証明書、所得証明書などの提出が必要
減額返還制度を利用すると、毎月の負担が軽くなるため、収入が低い時期でも計画的に返済が進められます。
ただし、返済期間が延びる分、長期間にわたって返済義務が続く点に注意しましょう。
どちらの制度も、延滞が発生していない状態であれば申請可能です。
支払いが厳しいと感じたら、早めに手続きを行いましょう。
返済免除制度の概要と条件
第一種奨学金の返済が免除される制度もあります。
JASSOでは、以下の特定の条件を満たす場合に、奨学金の全額または一部が免除される制度を設けています。
📌 特に優れた業績による返還免除制度
- 対象者:第一種奨学金を受けた大学院生
- 成績が特に優秀で、研究や学業で顕著な成果を上げた場合、奨学金の全額または半額が免除
- 各大学の推薦を経て審査が行われる
📌 教員免除制度
- 教職大学院修了者・教職課程認定の大学院修了者が、教員採用試験に合格し正規教員として採用された場合、奨学金の全額が免除
- 「特に優れた業績をあげたと認められる者」が対象
📌 医療・福祉職に従事した場合の免除制度
- 特定の医療職・福祉職に一定期間従事することで、奨学金が免除される制度
- 地域医療を支援する奨学金制度なども対象
奨学金を返済する負担を減らしたい場合、これらの制度が利用できるか確認しておきましょう。
第一種奨学金を上手に活用する方法
奨学金を受けることで、経済的な負担を軽減しながら学業に専念できます。
しかし、第一種奨学金だけでは生活費や学費を全てカバーできない場合もあるため、他の支援制度と併用するのも一つの方法です。
第一種奨学金と他の支援金を組み合わせる方法
第一種奨学金の貸与額は、第二種奨学金(有利子)よりも低く設定されています。
そのため、第一種奨学金だけでは足りない場合、以下の支援制度を併用すると負担を軽減できます。
✅ 給付型奨学金(JASSO・地方自治体・民間団体)
➡ 返済不要のため、卒業後の負担を抑えられる
✅ 第二種奨学金(有利子)との併用
➡ 月額の増額が可能だが、利息が発生するため慎重に検討
✅ 大学独自の奨学金制度を活用
➡ 大学によっては成績優秀者向けの奨学金がある
✅ 教育ローンの利用
➡ 日本政策金融公庫などの低金利の教育ローンを活用
第一種奨学金だけで不十分な場合は、他の支援金と組み合わせて、無理のない学費計画を立てましょう。
将来のキャリアに活かすための奨学金活用術
奨学金をただ学費に充てるだけでなく、将来のキャリア形成に役立てることも重要です。
✅ 海外留学を経験する ➡ 第一種奨学金(海外大学院学位取得型)を利用し、海外大学院で学ぶことでキャリアの幅を広げる
✅ 資格取得に活用する ➡ 奨学金を使って国家資格や専門資格の勉強費用を補助し、就職後の年収アップにつなげる
✅ インターンシップや研修に参加 ➡ 奨学金を活用して企業の研修やインターンに参加し、実務経験を積む
奨学金を計画的に活用することで、卒業後の収入を増やし、返済の負担を軽減できる可能性があります。
まとめ|第一種奨学金を賢く活用し、無理なく返済を進めよう
第一種奨学金は、無利子で借りられるメリットがある一方で、卒業後の返済義務もあります。
無理なく返済するためには、計画的な利用が重要です。
✅ 返済が厳しい場合は、「返済猶予制度」や「減額返還制度」を活用
✅ 学業が優秀な人は「返済免除制度」を検討
✅ 第一種奨学金だけで足りない場合、他の支援金と組み合わせる
✅ 奨学金を活用し、将来のキャリア形成につなげる
奨学金は、ただ借りるだけでなく「どのように活用するか」が大切です。
計画的に活用し、無理のない返済プランを立てましょう。










