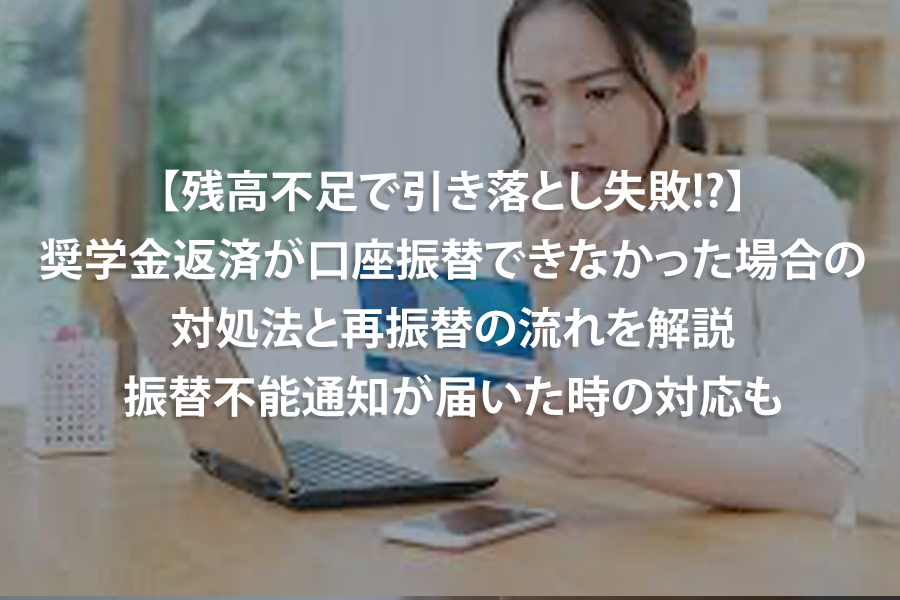
奨学金の返済は、大学卒業の6ヶ月後からはじまり、最長で20年以上にわたって毎月続きます。
そのため、残高不足による意図せぬ滞納といったトラブルが発生する可能性があるでしょう。
また、就職状況など不測の事態により、無理なく返還できるはずだった奨学金の引き落としに失敗する可能性も否定できません。
この記事では、奨学金返済が口座振替できなかった場合の対処法を解説します。
再振替の流れもお伝えするため、まずは焦らずにこの記事を確認し、しかるべき対応へと移りましょう。
奨学金返済の基本は「口座振替」方式
奨学金の返済は、日本学生支援機構(JASSO)が指定する金融機関の口座から毎月自動的に引き落とされる「口座振替」を利用することが基本です。
口座振替は便利な支払方法ですが、ケアレスミスにより引き落としに失敗するリスクがあります。
そのため、まずは口座振替の概要や口座振替に失敗する主な理由を知っておきましょう。
口座振替(自動引き落とし)とは?
口座振替とは、指定した銀行口座から、毎月の返済額が自動的に引き落とされる支払方法です。
JASSOの奨学金返済方法は口座振替と決められています。
引き落としが行われるタイミングは原則として毎月27日で、土日祝日の場合は翌営業日に引き落としが行われます。
通販などの支払方法には「払込票」がありますが、これは請求される度にコンビニエンスストアや郵便局などの窓口に出向いて手続きをしなければならない支払方法です。
口座振替は、指定した口座に支払額が入金されていれば自動的に支払いが完了するため、手間がかかりにくい便利な支払方法と言えます。
支払いができなかった場合の主な理由
口座振替は便利な支払方法ですが、引き落としに失敗して支払いができなくなるケースもあります。
口座振替に失敗する原因はいくつか考えられますが、その多くは以下のいずれかです。
・残高不足
・口座の不備
引き落とし当日の口座に必要な金額が入金されておらず、残高不足で口座振替に失敗するケースが目立ちます。
その他の引き落としが想定以上に多かった場合や残高の確認ミス、入金忘れなどの原因で残高不足が起こります。
口座の不備として考えられる理由は、長期間取引がない口座の凍結、金融機関の合併、システムトラブルなどです。
振替依頼書の記入不備や提出遅れにより、口座登録が完了していなかった場合も引き落としができません。
口座振替ができなかった場合に届く「振替不能通知」とは?
奨学金の口座振替ができなかった場合、JASSO(日本学生支援機構)から「振替不能通知」という書類がJASSOに登録している住所に郵送されます。
これは極めて重要な書類であるため、どのような内容の書類なのかを知っておき、自宅に届いた場合は放置せずに必ず内容を確認しましょう。
「振替不能通知」とは何か?
振替不能通知とは、奨学金の返済が引き落としできなかったことを知らせる重要な種類です。
この通知が届くのは、毎月27日の引き落としが失敗した翌月の5日~10日までの間が目安となります。
この通知を無視すると、奨学金を延滞したとみなされてさまざまなリスクが発生するため、必ず内容を確認して速やかに対応しましょう。
通知の確認ポイント
振替不能通知が届いたら、以下の点を必ず確認しましょう。
・返還金額
・再振替の有無
・支払期限
・振替不能になった理由
特に重要なのは「再振替の有無」です。
再振替が行われる場合、指定された日時までに返還金額を入金しておくと、自動的に再度引き落としが行われます。
再振替がない場合は、支払期限を確認し、期限までに指定された方法で支払いを行わなければなりません。
また、振替不能になった理由も振替不能通知に記載されている場合があります。
振替不能になった理由を把握しておくと、翌月以降に同様の問題で口座振替に失敗するリスクを減らせるでしょう。
奨学金の口座振替ができなかった時の対処法
引き落としができずに奨学金返済が遅延した場合は、その後のトラブルを避けるために早急な対策が必要です。
ここでは、奨学金返済の口座振替に失敗した場合の対処法をご紹介します。
残高不足だった場合の対応
引き落とし失敗の原因が残高不足だった場合は、まずスカラネット・パーソナルにアクセスして、振替不能の事実と不足した金額を確認しましょう。
JASSOの奨学金返済は、原則として再振替が行われません。
そのため、翌月まで放置するのではなく、振替不能通知に記載された方法で、未払い分を自分で支払う必要があります。
再振替が行われない場合の支払方法
再振替が行われない場合は、振替不能通知に同封されている「払込用紙」を利用して奨学金返済を行うのが基本です。
払込用紙を使った支払いは、全国のコンビニエンスストアや銀行・信用金庫などの金融機関、郵便局の窓口などで行えます。
通知には支払期限が記載されているため、期限内に必ず手続きを完了させましょう。
手続きが間に合わないとどうなる?
振替不能通知に記載された期限までに支払いを行わなかった場合、未払いの奨学金は延滞扱いとなります。
延滞とみなされると、未払い分の奨学金返済額に遅延損害金が加算されるため、当初の予定よりも支払総額が増えてしまいます。
また、目安として3ヶ月以上にわたって延滞を続けると、CICやJICCといった信用情報機関に「事故情報」として記録されかねません。
これは、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態で、その後のローン審査などに多大な悪影響を及ぼします。
残高不足で引き落としできなかった理由を明確にする
残高不足は誰にでも起こり得るミスです。
早急に対応することにより、ブラックリスト入りなどのトラブルは避けられます。
しかし、口座振替に何度も失敗すると、JASSOとの信頼関係に亀裂が入る可能性は否定できません。
残高不足で奨学金返済に失敗した場合は、その理由を明確にして、再発防止に努めましょう。
ここでは、具体的な対処法をご紹介します。
よくあるケースと再発防止策
残高不足が原因で奨学金返済に失敗する原因として特に多いのは次の3つです。
・月末払いの別支出と重なっていた
・給与の振り込みが遅れた
・家族が同じ口座を共有していた
家賃や公共料金、クレジットカードの引き落としが重なると、想定外の出費により残高が不足することがあります。
この場合は、奨学金返済日となる毎月27日をカレンダーにマークしておき、引き落とし前日までに必要な金額が入金されているか確認する対処法が有効です。
また、家族で同じ口座を共有している場合も、想定外の引き落としや現金の引き出しによって残高不足が起こる可能性があります。
反対に、奨学金返済の引き落としが家計に影響を与える可能性もあるため、奨学金返済専用の口座を用意して対策すると良いでしょう。
引き落とし日の前に口座残高を確認する習慣を
引き落とし日の27日を意識し、その数日前に口座残高をチェックする習慣をつけましょう。
スマートフォンのリマインダー機能や銀行の残高通知アプリなどを活用するのも効果的です。
なお、引き落としは原則として27日の未明に行われます。
そのため、遅くても26日の夜までには、引き落としに必要な金額を入金しておきましょう。
奨学金返済ができなかった時のリスクと影響
奨学金返済ができなかった場合は、単純に延滞として処理されるだけではなく、さまざまな影響が生じるリスクがあります。
深刻なリスクも含まれるため、口座振替に失敗しないように細心の注意を払いましょう。
この項目では、奨学金返済に失敗することによって生じる具体的なリスクについて解説します。
延滞扱いになるとどうなる?
奨学金返済が延滞扱いになると、以下の問題が起こるため要注意です。
・年5%の延滞金が加算される
・督促状や電話が届く
奨学金を延滞すると、未払い分に対して年5%の延滞金が日割りで加算されます。
これにより、奨学金の返済総額が増加することに注意しなければなりません。
また、JASSOや債券の委託会社から自宅に督促状が届いたり、登録している電話番号に電話がかかってきたりする場合があります。
法外な請求や取り立て行為が行われるわけではありませんが、これも精神的なプレッシャーや負担としてのしかかることになるでしょう。
長期間延滞すると信用情報に登録される可能性も
奨学金の延滞が3ヶ月以上続くと、信用情報機関に延滞情報が登録されます。
これは、いわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態です。
信用情報機関に登録された延滞情報は、たとえ未払いの奨学金を全額返済したとしても、目安として延滞情報が登録された日から5年~7年間は削除されません。
これによる問題は、将来の信用情報に大きな傷が付くことです。
たとえば、住宅ローンやマイカーローン、教育ローンを組む場合は金融機関の審査を受ける必要があります。
この際の審査で参照されるのが、申込者の信用情報です。
この時、奨学金を延滞した事実が記録されていると、審査が極めて不利になると言わざるを得ません。
クレジットカードの新規申し込みや契約更新に伴う審査でも、信用情報は参照されています。
そのため、奨学金の滞納を続けてしまうと、各種ローンやクレジットカードを利用できなくなるおそれがあるのです。
保証人や連帯保証人への請求リスク
奨学金の利用者本人が長期間にわたって奨学金を滞納した場合、JASSOは利用者本人ではなく、契約時に指定した保証人や連帯保証人に請求を行う場合があります。
保証人に両親などの家族や親族、友人・知人を指定している場合は、それらの人物に多大な迷惑をかけてしまいかねません。
特に、連帯保証人は、利用者本人と同じ責任を背負うことになり、本人の支払いが困難とみなされた場合は、奨学金残債の全額が連帯保証人に請求される可能性が高いです。
また、奨学金を滞納している事実を近しい人物に知られてしまうことも、本人にとって大きな精神的負担となるでしょう。
困った時の相談先と再発防止のポイント
奨学金の返済に困った時は、一人で悩まずに早めに相談することが大切です。
JASSOでは、なんらかの事情により奨学金の返済が困難になった人物に向けた救済的な制度を用意しています。
資金難により口座振替の失敗を繰り返す可能性が高い場合は、担当窓口に相談して、活用できる制度があるか調べてもらいましょう。
反対に、手元の資金に余裕がある場合は、自動引き落としではなく「繰上返還」を行うことにより、口座振替の失敗を確実に防ぐことが可能です。
ここでは、JASSOが用意している救済制度と繰り上げ返済の概要をご紹介するほか、引き落とし口座の見直しも含めた再発防止のポイントを解説します。
JASSO(日本学生支援機構)の返還相談窓口
JASSOでは、奨学金返済に関するトラブルを抱えている利用者を対象とする、奨学金相談センターを設けています。
たとえ奨学金返済を延滞したとしても、個々の事情に応じた有効な対処法を教えてもらえるため、奨学金返済に困った時はできるだけ早く奨学金相談センターに連絡しましょう。
奨学金相談センターの連絡先は次の通りです。
・電話番号:0570-666-301または03-6743-6100
・受付時間:平日9:00~20:00(土日祝日・年末年始を除く)
経済的な事情により、事前に取り決めた月々の返済額を支払うことが難しくなった場合は、次の制度を活用できる可能性があります。
・減額返還制度
・返還期限猶予制度
減額返還制度とは、奨学金の返還期間を延長する代わりに、月々の返済額を2分の1または3分の1に減額する方法です。
たとえば、月々2万円を返済している方が月々の返済額を2分の1に減額すると、月々の返済額を1万円に半減させられます。
返還期限猶予制度とは、最大10年間にわたり、奨学金返済が猶予される制度です。
原則として1年単位で申請し、猶予期間中は新たな利息も発生しません。
返還総額が減ることはありませんが、猶予期間中に生活を立て直すことができれば、無理なく奨学金返還を再開できるでしょう。
なお、減額返還制度や返還期限猶予制度を活用できるのは、なんらかの事情により収入が減少した方や被災や病気などの特別な事情がある方のみです。
制度の適用に向けた審査があり、これに通過できなかった場合は、上記の制度を利用できません。
まずは奨学金相談センターに問い合わせを行い、これらの制度を利用できるか確認しましょう。
自動引き落とではなく「繰上返還」も検討可能
手元の資金にゆとりがある場合は、口座振替を中止して、繰り上げ返済で奨学金を完済する対処法も有効です。
月々の返済額に任意の金額を追加して完済することにより、口座振替の失敗を強制的になくすことができます。
また、返済期間を短縮できるため、将来的に支払う利息が減り、返還総額が安くなることも繰り上げ返済のメリットです。
「想定以上のボーナスが入った」「遺産相続により預貯金が増えた」といったケースでは、繰り上げ返済も検討すると良いでしょう。
ただし、預貯金の大半を使い切るといった、無茶な繰り上げ返済はおすすめできません。
資金繰りが悪化して、冠婚葬祭などの突発的な出費に対応できなくなるリスクがあるためです。
特に結婚や出産、引っ越しに伴うマイホームの購入といったライフイベントを控えている場合は、繰り上げ返済を行うかどうか慎重に判断しましょう。
引き落とし口座の見直しも有効
残高不足を防ぐためには、引き落とし口座を見直す対策も有効です。
普段から利用しているメインバンクや給与が振り込まれる口座に奨学金の引き落とし口座を変更すると、残高不足が発生しにくくなるでしょう。
普段からよく利用する口座を引き落とし口座に指定すると、残高や引き落としの結果を確認する手間も省けます。
また、口座凍結などのリスクも減るため、安心して長期間の奨学金返済と向き合えるでしょう。
まとめ
奨学金返済の口座振替に失敗したとしても、焦らずに適切な対処をすれば、深刻な事態を避けられます。
重要なポイントは、引き落としに失敗したとわかった時点で、すぐに支払いに向けて動くことです。
JASSOから通知が届いた場合は、支払期日を確認して、期日までに払込票を使って奨学金返済を完了させましょう。
また、経済的な事情により奨学金返済が困難になった場合は、JASSOの窓口に相談し、適用できる救済制度があるか調べてもらいましょう。










