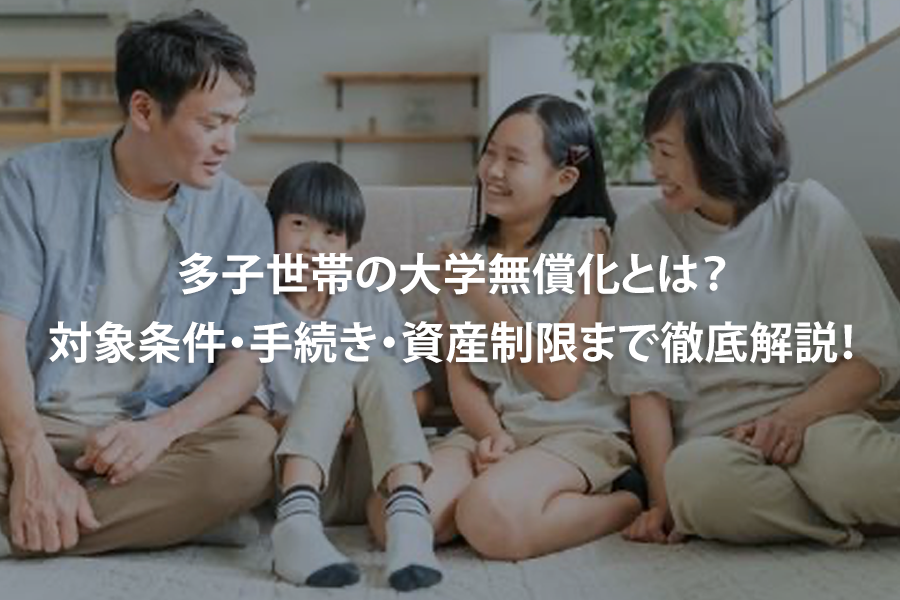
2025年度にスタートした「多子世帯の大学無償化」は、少子化対策の一環として注目される制度です。
しかし、「どのような制度なのか」「対象となるのはどのような世帯で、自分は制度の対象者なのだろうか」といった疑問を抱えている方も多いでしょう。
この記事では、多子世帯の大学無償化について、対象条件や手続きの方法などを解説します。
多子世帯の大学無償化とは?
多子世帯の大学等授業料等無償化とは、扶養する子どもが3人以上いる世帯(多子世帯)を対象に、所得制限なしで大学などの授業料や入学金を免除する制度です。
まずは多子世帯の大学無償化が始まった理由や制度の詳細について解説します。
背景と政策の目的
多子世帯の大学無償化がスタートした背景には少子高齢化があります。
日本では急速な少子化が進んでおり、これを解消するためには子育て世帯の経済的負担を軽減する政策が不可欠です。
子どもを産み、育てやすい環境を整えることは急務であり、その上で大きな障壁となっていたのが大学などの授業料や入学金といった学費です。
仮に進学できたとしても、学生がアルバイトをして学費を稼ぐ必要に迫られ、学業が疎かになるケースは珍しくありません。
結果として、裕福な家庭とそうでない家庭との間で教育格差が広がることも危惧されています。
多子世帯の大学無償化は、このような教育費の負担が特に大きい多子世帯において、子どもが進学を諦めるケースを減らし、教育機会の均等化を図ることを目的として、2025年度から導入されました。
この制度は、2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」に基づいて導入されたものです。
どんな制度なのか?
多子世帯の大学無償化は、「高等教育の修学支援新制度」の一部として、大学などの授業料および入学金を減免する制度です。
国公立大学では授業料と入学金が、原則として全額免除されます。
私立大学でも減免措置を受けられますが、上限が設けられており、差額は各家庭が自己負担しなければなりません。
従来の「高等教育の修学支援新制度」は、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯を対象に、学費の減免と給付型奨学金を組み合わせた支援を提供していました。
一方の多子世帯の大学無償化には所得制限がなく、3人以上の子どもを扶養していれば大学などの授業料と入学金が減免されます。
対象となる多子世帯とは?
多子世帯とは、扶養する子どもが3人以上いる世帯のことです。
ただし、子どもが3人いたとしても、多子世帯の対象とはならない世帯もあるため注意しなければなりません。
ここでは、どのような世帯が多子世帯の大学無償化の対象として扱われるのか、詳しく解説します。
何人以上から「多子世帯」?
多子世帯とは、生計維持者が3人以上の子どもを扶養している世帯のことです。
扶養親族の数は、法令に基づき、「マイナンバー」を通じて日本学生支援機構(JASSO)が確認します。
各大学では、マイナンバーを通じた扶養人数の確認は行えません。
また、2023年12月31日時点で3人以上の扶養親族がいれば多子世帯の大学無償化の対象となり、2024年度以前に大学などに進学した方も対象に含まれます。
扶養する子どもに年齢制限はなく、高校生、大学生、専門学生、さらには大学院生も扶養親族としてカウントされます。
ただし、子どもが就職するなどして一定の収入を得て扶養から外れると、多子世帯の条件を満たさなくなる場合があるため注意しなければなりません。
具体的な例については後述します。
対象となる家族の具体例
対象となる家族の具体例を2つご紹介します。
例1:3人兄弟で全員学生の場合
3人兄弟が全員大学や高校に在学中で、親の扶養に含まれる場合は、3人全員が多子世帯の支援対象です。
この場合、世帯年収に関係なく、全員の授業料・入学金が減免されます。
例2:一人は社会人・2人が学生の場合
全員が男性の3人兄弟と仮定して考えましょう。
この場合、長男が就職して扶養から外れ、次男と三男が学生で親の扶養に含まれるケースでは、扶養されている子どもは2人と判断されます。
つまり、多子世帯の条件を満たせず、制度を適用できません。
ただし「長男が学生ではなくなった」というだけで多子世帯の大学無償化の対象外となるわけではありません。
長男が卒業したとしても、フリーターや就職浪人などで収入が一定を下回り、引き続き親の扶養となる場合は、多子世帯の大学無償化の対象となる可能性があります。
大学無償化の対象となる条件
大学無償化の対象となるためには、前提として3人以上の扶養家族がいる多子世帯である必要があります。
しかし、それだけでは大学無償化の対象とはなりません。
資産制限を受ける可能性があるほか、学生本人も所定の条件を満たす必要があります。
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
世帯年収と資産制限
先述した通り、多子世帯の大学無償化には所得制限がありません。
ただし、給付型奨学金を併用する場合は、世帯収入に応じた区分(第Ⅰ~Ⅳ区分)が適用されます。
住民税非課税世帯(第Ⅰ区分)では全額支給となりますが、それに準ずる世帯は第Ⅱ区分が3分の2、第Ⅲ区分が3分の1、第Ⅳ区分は4分の1の支援です。
また、資産制限も設けられます。
多子世帯の大学無償化を適用するためには、申請者と生計維持者の資産合計が3億円未満でなければなりません。
なお、ここでいう資産とは次のようなものを指します。
・現金
・預貯金(普通預金、定期預金など)
・有価証券(NISAを含む株式、国際、社債など)
・投資目的で保有する金や銀など給付型奨学金を併用する場合はさらに基準が厳しくなります。
具体的には、学生本人と生計維持者の資産合計が5,000万円未満に収まらなければなりません。
在学する学生本人の条件
支援を受けるには、学生の学修意欲が求められます。
大学などに入学する前の場合、学習意欲を判定するポイントは、主に高校の評定平均値や学修計画書の内容です。
学生がすでに大学などに在学している場合は、平均成績が上位4分の3以上、出席率6割以上、取得単位数6割以上などの条件を満たす必要があります。
留年となった場合も原則として支援の対象に含まれますが、出席率や取得単位数が6割未満の場合は、支援が打ち切られる可能性があるため注意しましょう。
なお、休学する場合は、大学の判断により支援が継続されるか、それとも打ち切られるかが決まります。
無償化の対象大学一覧と注意点
無償化の対象大学は多いですが、国公立大学か私立大学かによって、免除される学費の金額が異なります。
ここでは、具体的に免除される金額や対象大学として指定されている大学などの調べ方、専門学校なども無償化の対象になるのかどうかについて解説します。
国公立大学と私立大学の違い
国公立大学の場合、入学金28万円と授業料54万円が減免されます。
これは国公立大学の学費を全額カバーする内容であり、実質的に学費負担をゼロに抑えることが可能です。
一方の私立大学は、授業料は最大70万円、入学金は最大26万円が減免されます。
文部科学省の「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」によると、令和5年度における私立大学の平均授業料は約96万円、平均入学金は約24万円でした。
仮に授業料が96万円の場合、差額の26万円は自己負担する必要があります。
なお、給付型奨学金は世帯収入に応じて支給されます。
対象となる大学の具体例
無償化の対象となる大学は、文部科学省の「支援の対象となる大学・短大・高専・専門学校一覧」から確認できます。
対象となる大学数は膨大であり、この記事にすべてを掲載することは難しいため、文部科学省のHPより詳細をご確認ください。
一例として、東京都内にある無償化の対象大学をいくつかリストアップします。
・国公立大学:東京大学、東京外国語大学、東京芸術大学、一橋大学など
・私立大学:学習院大学、北里大学、慶應義塾大学、上智大学、中央大学、日本大学、明治大学、立教大学、早稲田大学など
なお、専門学校や短大、通信制大学も無償化の対象に含まれます。
ここでも、東京都内の専門学校・短大・通信制大学の中から、無償化の対象となる主な学校をリストアップしてご紹介しましょう。
・専門学校:大原簿記学校、東京医療福祉専門学校、首都医校、HAL東京、東京モード学園など
・短大:共立女子短期大学、日本大学短期大学部、桐朋学園芸術短期大学、山野美容芸術短期大学など
ただし、通信制大学や夜間課程は支援額が昼間課程の半額程度となる場合があります。
詳しくは進学予定もしくは在学している各大学の担当窓口にお問い合わせください。
大学無償化を受けるための手続き方法
大学無償化は、先述した条件に当てはまる場合でも、自動的には適用されません。
各家庭がしかるべき窓口で申請する必要があるため、手続きの方法を確認しておきましょう。
ここでは、申請先と必要書類、そして申請できるタイミングとスケジュールについて解説します。
また、在学中の継続申請や再申請を受ける際の注意点も確認しておきましょう。
申請先と必要書類一覧
多子世帯の大学無償化を受けるためには手続きが必要です。
手続きの申請先は、進学予定または在学中の大学・専門学校・短期大学といった機関の担当窓口となります。
市区町村役場などの自治体では申請を受け付けていないため、注意しましょう。
なお、必要書類は次の通りです。
・マイナンバー(扶養状況を確認するための必要書類)
・所得証明書(給付型奨学金を申請する場合に必要)
・住民票(家族構成を証明するために必要)
・在学証明書(進学先の大学により発行される)
・学修計画書(学習意欲を示すために必要)
これらの書類を、大学から配布される「奨学金確認書兼地方税同意書」とあわせて提出します。
なお、そのほかにも「戸籍謄本」や「成績証明書」「調査書」などの提出を求められる可能性があります。
必要書類は大学によって異なるため、あらかじめ必要書類を確認しておき、時間に余裕を持って収集しましょう。
申請のタイミングとスケジュール
多子世帯の大学無償化を申請するタイミングは、進学する年度の春(4月~5月)と秋(9月~10月)の年2回です。
進学先の大学などに合格・入学した後に、大学の指示に従って申請を行うことが一般的です。
入学手続きの時期から申請の受付がスタートする場合が多いため、大学側の案内を細かく確認しましょう。
大学側は受け取った書類を日本学生支援機構(JASSO)に送付し、JASSOが申請内容を確認したうえで審査を行います。
在学期間中は、4月もしくは10月に制度の申請が可能です。
申請期限は大学などによって異なり、2025年度は制度の導入初年度ということもあり、申請期限を6月まで延長する大学なども見られました。
なお、多子世帯の大学無償化の継続を申請する場合は、扶養状況や学業成績の再審査を受ける必要があります。
扶養家族が2人以下に減った場合や学業成績が一定の水準を満たさなかった場合は、支援が打ち切られる可能性があるため注意しましょう。
よくある質問と注意点
この記事の最後に、多子世帯の大学無償化に関するよくある質問にお答えします。
制度に関する注意点もまとめているため、わからないことや不安なことがある場合は、まずこちらのQ&Aをご覧ください。
この項目だけで疑問を解消できなければ、日本学生支援機構(JASSO)の担当窓口へ問い合わせることをおすすめします。
多子世帯でないと対象にならない?
はい、多子世帯の大学無償化は多子世帯(扶養する子どもが3人以上)でなければ制度の対象になりません。
現時点で子どもの人数が2人以下の場合は、制度を適用できないため注意しましょう。
ただし、多子世帯以外の子育て世帯でも、従来の「高等教育の修学支援新制度」は引き続き適用が可能です。
これにより、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯は、大学などの入学金や授業料の減免を受けられる可能性があります。
多子世帯に該当しない場合は、そのほかの支援制度を利用できるか確認しましょう。
途中で条件から外れたらどうなる?
扶養する子どもが2人以下になった場合は、その時点で多子世帯の大学無償化の適用対象から外れます。
認定された年度までに支援された学費を返還する必要はありませんが、次年度以降は本制度を適用できません。
たとえば、第1子が就職などにより所定の年収を上回り、扶養している子どもが2人に減った場合は、兄弟姉妹全員が制度の対象から外れてしまいます。
また、学業成績が基準を下回るなど、そのほかの条件を満たせなくなった場合も、同様に制度の対象から外れるため注意しましょう。
なお、一度条件から外れて制度を適用できなくなったとしても、状況により制度の適用を再開できる可能性があります。
たとえば、出産により扶養となる子どもが増えたケースが代表的な例です。
併用できる奨学金や支援制度はある?
日本学生支援機構(JASSO)による給付型奨学金は、多子世帯の大学無償化と併用できる制度です。
給付型奨学金とは、返済の必要がない奨学金のことで、高等教育の修学支援新制度の一つとして導入されました。
ただし、給付型奨学金は経済的な理由で進学・就学が困難な学生を支援する目的で作られた制度であり、以下の要件を満たさなければ受給できません。
・家計の要件:一般的に住民税非課税世帯またはそれに準ずる世帯が対象となる
・学業の要件:学業成績が一定の基準を満たしている、もしくは学習意欲が認められる必要がある
無利子の第一種奨学金や有利子の第二種奨学金も多子世帯の大学無償化と併用できますが、それぞれの奨学金貸与額が調整され、借入額が少なくなる可能性があります。
また、一部の民間や自治体による奨学金を併用できる可能性もあるため、詳しくは進学予定の大学やJASSOに確認しましょう。
まとめ
多子世帯の大学無償化は、3人以上の子どもを扶養する世帯の学費負担を軽減する画期的な制度です。
制度を適用できる場合、入学金と学費が減免され、国公立大学の場合は支援される金額で学費を相殺できます。
これまでに実施されてきた「給付型奨学金」などの制度とは異なり、所得制限が設けられることもありません。
大学のみならず、短期大学や専門学校でも制度を適用できるため、多くの多子世帯にとって学費に苦慮するリスクが少なくなります。
なお、申請にはマイナンバーや所得証明書などの書類が必要です。
文部科学省やJASSOの公式サイトで最新情報を確認し、計画的に手続きを進めましょう。










