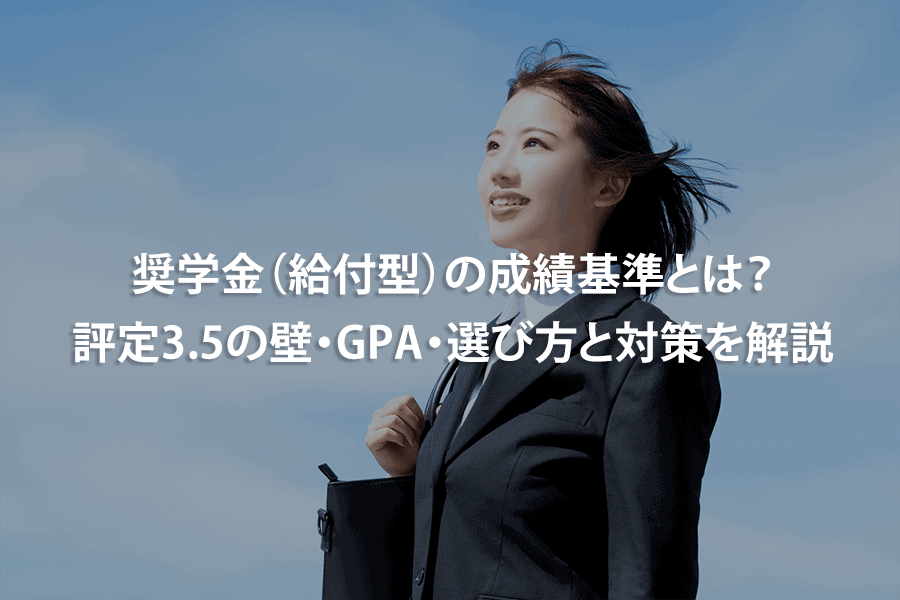
大学や専門学校への進学を考えるとき、「学費や生活費をどうまかなうか」は多くの家庭の共通の悩みです。そのなかでも返済不要の「給付型奨学金」は、とても魅力的な制度ですが、その分「成績基準」が厳しいイメージがあり、「評定が足りないと申し込めないのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。
本記事では、ファイナンシャルプランナーや教育費相談の現場で得た知見をもとに、「給付型奨学金の成績基準」をわかりやすく整理します。JASSO(日本学生支援機構)の評定3.5のラインやGPAの考え方に加え、民間財団・大学独自の給付型奨学金で求められる水準、成績が足りない場合の選択肢、打ち切りを避けるためのポイントまで、進学を諦めないために知っておきたい情報を体系的に解説します。
まず押さえたい「給付型奨学金」と成績基準の基本
給付型奨学金は、返済不要で進学を後押ししてくれる非常に魅力的な制度です。しかしその分、応募者が多く審査基準も厳しいため、「成績基準」が特に重視されます。まずは制度の仕組みや、なぜ成績が見られるのかといった根本的なポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、給付型奨学金の前提と成績基準の全体像について、初めての方でも理解できるように整理します。
給付型と貸与型の違い ― 「もらえるお金」と「借りるお金」
奨学金には大きく分けて「給付型」と「貸与型」があります。給付型は返済義務のない“もらえるお金”であり、経済的な理由で学びを諦めてほしくないという目的で設けられています。一方、貸与型は卒業後に返済する必要があり、第一種(無利子)・第二種(有利子)などの種類があります。
返済不要である給付型は、その分だけ応募者も多く、選考基準が厳しい傾向にあります。募集枠も限られているため「狭き門」と言われることが多く、成績や家庭状況、志望理由の内容などを総合的に審査されます。
- 返済義務の有無(給付型=原則返済不要、貸与型=卒業後に返済)
- 利息の有無・返済期間の違い(第一種・第二種との比較)
- 給付型が「狭き門」と言われる理由(募集枠・審査基準の厳しさ)
なぜ成績基準が設定されているのか ― 制度の目的から理解する
給付型奨学金に成績基準があるのは、「支援した学生が確実に学業を続け、卒業できる見込みがあるか」を判断するためです。奨学金は、将来社会に貢献できる人材を育てるための制度であり、支援する財団・企業・公的機関は、学習意欲や進路の明確さも含めて学生を評価します。
そのため、成績だけではなく、面談での態度、提出書類の内容、課外活動実績、家計状況なども総合的に判断されるケースが多く、単なる学力テストのような評価ではありません。「成績が全てではないが、重要な判断材料のひとつ」という位置づけです。
- 「卒業まできちんと学びきれるか」という見通しを確認する役割
- 将来の社会貢献への期待(財団・企業・公的機関それぞれの視点)
- 成績だけでなく「意欲」「活動」「経済状況」も総合評価される点
成績基準の全体像 ― 評定平均/GPA/学年順位という3つの軸
奨学金で求められる成績基準にはいくつか種類があり、制度によって評価の方法が異なります。高校生の場合は「評定平均(5段階)」「学校内での相対順位」が重視され、大学生の場合は「GPA」や「取得単位数」などが評価対象になります。また、学力だけでなく、レポートや面談などの総合評価によって判断される財団も多く存在します。
特にJASSOの給付型奨学金では、高校の評定平均3.5以上がひとつの目安となりますが、民間財団では4.0以上を求めるケースもあります。一方で、成績よりも活動実績や意欲を重視する制度もあるため、自分の状況に合った奨学金を選ぶことが重要です。
- 高校時:評定平均(5段階)の目安(3.5・4.0など)
- 大学時:GPAや取得単位数での評価
- 総合評価(書類・面接・レポート・活動実績)との組み合わせ
JASSO給付型奨学金の成績基準と「評定3.5」の意味
高等教育の修学支援新制度とJASSO給付型奨学金の概要
JASSO(日本学生支援機構)の給付型奨学金は、「高等教育の修学支援新制度」に基づく公的支援で、大学・短期大学・専門学校などへの進学を経済面からサポートする目的で設計されています。この制度は、授業料・入学金の減免と給付型奨学金の同時支援が特徴で、世帯の経済状況によって受けられる支援額が大きく変わる点が大きなポイントです。
さらに、採用基準には「世帯所得・資産基準」と「成績基準」の二本柱が設定されており、家計状況だけでなく学業への意欲や基礎学力が重視されます。どちらか一方ではなく、双方の条件を満たすことで初めて採用される仕組みになっているため、制度理解が非常に重要です。
- 対象となる学校(大学・短大・専門学校など)
- 授業料等減免+給付型奨学金がセットになっている仕組み
- 世帯所得・資産基準と成績基準の二本柱
高校時の成績基準 ― 評定平均3.5以上はどのくらいのライン?
JASSO給付型奨学金の成績基準で最もよく知られている条件が、「評定平均3.5以上」というラインです。これは高校で履修した全科目の評定平均を指し、特定科目だけで評価されるわけではありません。3.5は“平均よりやや上”のイメージで、成績上位層でなくても届く可能性のある水準です。
ただし、同じ3.5でも「ギリギリ3.5」と「4.0に近い3.8〜4.0」では、申請理由書との組み合わせによって評価のされ方が変わることがあります。より高い評定を目指すことで、採用の確度を上げることができます。
また、学校によっては成績がA〜EやS〜Cなど数値以外で表記される場合もあります。その際は5段階に換算され、概ね“平均以上”であるかどうかが判断軸になります。自分の評定方法が特殊な場合は、学校の先生や奨学金担当窓口に確認しておくとよいでしょう。
- 全履修科目の評定平均3.5以上のイメージ
- 「3.5ちょうど」と「4.0近い」場合のアピールの違い
- 5段階以外の成績(A~Eなど)の場合の考え方(平均以上かどうか)
大学入学後に見られる成績 ― GPAや単位取得状況
大学入学後に申請する「在学採用」では、高校の評定ではなく大学での成績が評価対象になります。基準の中心となるのがGPA(Grade Point Average)で、4.0満点などの方式で算出される成績指標です。GPAは試験成績だけでなく、レポート・出席・課題提出など授業全体の評価が反映されるため、日頃の取り組みが重要になります。
また、学部内での相対順位が上位2分の1に入っているかどうかを基準とする場合もあります。単位不足やGPAの低下は支給停止につながる可能性があり、留年すると奨学金が廃止されるケースもあります。奨学金継続のためには、早めの単位取得と安定した成績管理が欠かせません。
- GPA(4.0満点など)の基本的な考え方
- 学部内での相対評価(上位2分の1など)の目安
- 留年・単位不足・GPA低下による支給停止・廃止リスク
成績以外でチェックされるポイント
JASSO給付型奨学金では、成績は重要な要素ですが、それだけで採用・不採用が決まるわけではありません。申請理由書で学習意欲や進学目的を明確に示せているか、将来どのように社会貢献したいかなどが重視されます。面談がある場合は、態度やコミュニケーションも評価に含まれます。
また、欠席や遅刻が多いなど生活態度に問題があると、成績が基準を満たしていても評価が下がることがあります。家計急変や病気などやむを得ない事情がある場合は、申請書類で説明すれば審査に考慮されることも多いため、早めに学校へ相談することが大切です。
- 学習意欲・将来のビジョン(申請理由書・面談での評価)
- 欠席・遅刻・生活態度など学校側の評価
- 家計急変・病気など、やむを得ない事情がある場合の扱い
民間財団の給付型奨学金と成績基準の傾向
高い成績基準を求めるタイプ(評定4.0以上・GPA3.0以上など)
民間財団が提供する給付型奨学金の中には、成績基準が非常に高く設定されているものがあります。たとえば電通育英会や本庄国際奨学財団、G-7奨学財団のように「高校評定平均4.0以上」または「大学でGPA3.1以上」など、明確かつ高水準の成績が求められるケースが代表的です。
これらの奨学金は、将来の社会貢献や専門分野で活躍できる優秀な人材の育成を目的としているため、成績だけでなく家計基準も併せて審査されることが一般的です。世帯年収や資産額が一定水準以下であることが条件に加えられることも多く、成績と経済状況の両方を満たすことで採用の可能性が高まります。
- 電通育英会・本庄国際奨学財団・G-7奨学財団のような例をモデルに
- 「評定平均4.0以上」「GPA3.1以上」など具体的イメージ
- 世帯年収の上限と成績基準がセットになっているケース
成績基準は目安、人物・意欲重視のタイプ
近年増えているのが、成績基準を「目安」とし、人物評価や意欲、活動内容を重視するタイプの奨学金です。たとえば似鳥国際奨学財団や地域育成財団では、明確な成績基準を設けつつも、書類や面接、小論文、活動実績などを総合的に評価する仕組みが特徴です。
地域貢献や分野特化(ICT・地域創生など)を重視する財団では、学びたい内容や将来のビジョンが強く評価されるため、成績が一定以上であれば他の要素で十分に逆転が可能です。特に志望理由書の内容や活動の実績が合致していると採用の可能性が高まります。
- 似鳥国際奨学財団・地域育成財団など、分野・地域貢献重視の例
- 小論文や面接、活動実績(ボランティア・研究・作品)の評価
- 成績は「一定以上」であれば、他の要素で逆転可能なケース
成績条件なしのクリエイター・アート系給付型奨学金
クリエイター・アーティスト向けの奨学金では、成績基準を設けず、創造性や表現力、独自性などを評価軸とするタイプがあります。代表例がクマ財団で、応募者は作品やポートフォリオ、SNSでの発信内容などを通して審査されます。
「成績に自信がないが、得意な分野や作品、表現活動がある」という学生にとって、こうしたクリエイティブ系奨学金は大きなチャンスです。分野を問わず挑戦できる制度が多く、毎年多様なジャンルの学生が採用されているのが特徴です。
- クマ財団のように「創造性」「発信力」を重視するタイプ
- ポートフォリオ・作品・SNS発信が選考の中心になるパターン
- 「成績に自信はないが得意分野がある」人が狙える奨学金
大学独自・自治体・新聞社奨学金の成績基準と特徴
地方自治体の奨学金 ― 成績基準が明文化されないケースも
地方自治体が実施する奨学金は、全国的に見ると成績基準が「明確に数字で示されない」ことが多い特徴があります。JASSOのように評定平均3.5以上など具体的に決められているわけではなく、「学業優秀」「人物良好」など、相対評価で判断されるケースが一般的です。
また、自治体の奨学金は在住要件や世帯収入など、地域の事情に基づく家計基準が重視されます。さらに募集枠が限られているため、学校での活動や地域との関わり、先生からの推薦といった“地域での評価”がプラスに働くことが少なくありません。
- 評定3.5などの「数字」でなく、相対評価(学業優秀など)の場合
- 在住要件・家計状況・人物評価とのバランス
- 募集枠が小さいぶん「地域での評判・活動」がプラスになること
新聞社奨学金 ― 成績証明書なしでも挑戦できる場合
新聞社が提供する奨学金は、学費の立て替えを受けながら新聞配達などの業務を行う「労働型奨学金」が中心です。多くの制度では成績証明書の提出が必須ではなく、学力よりも働く姿勢や責任感が評価される点が大きな特徴です。
そのため、成績に自信がなくても挑戦できる一方、新聞配達・集金・集配所での業務など、毎日数時間の仕事と学業を両立する必要があります。体力や時間管理力、生活リズムの維持が不可欠であり、負担は一般的な奨学金より大きくなるケースもあります。
- 学費立て替え+新聞配達など労働型奨学金の仕組み
- 成績基準よりも「健康・責任感・時間管理力」が重視される点
- 学業と仕事の両立の負担・生活リズムなど注意点
大学独自の給付・貸与奨学金と特待生制度
大学独自の奨学金は、入試成績や入学後の成績に応じて学費の一部または全額が免除される制度が多く、特待生制度として運用されているケースが一般的です。とくに私立大学では奨学金制度が豊富で、成績優秀者向けの給付型奨学金が整備されています。
入試成績が突出している場合や、大学でのGPAが高い学生は「成績優秀枠」として学費が大幅に減額されるメリットがあります。ただし、成績が下がると特待生の資格が取り消される場合があり、GPAや取得単位などの基準を満たし続ける努力が求められます。
- 入試成績・入学後の成績に応じた学費免除・減免制度
- 「成績優秀枠」で学費が大きく減るメリット
- 成績低下で特待・奨学金が取り消されるリスクと基準
成績が基準に届かない場合の選択肢と戦略
成績条件が緩い・成績不問の奨学金を組み合わせる
「評定が3.5に届かない」「GPAが基準を下回ってしまった」という場合でも、進学をあきらめる必要はありません。奨学金には、成績条件が緩いものや、そもそも成績基準を設けていない制度も多く存在します。特に民間財団やクリエイター向け奨学金は、成績よりも意欲・作品・活動内容を重視する傾向があります。
また、自治体や地域NPOが提供する小口奨学金は、応募者が限られるため採用されやすい点がメリットです。複数の奨学金を組み合わせることで、全体として大きな支援額になる場合もあるため、「成績が不安でも挑戦できる制度」を幅広く調べることが重要です。
- 成績不問の民間・財団系・クリエイター系奨学金の探し方
- 「学力よりも分野・地域・活動」を重視する制度を狙う
- 自治体やNPOの小口奨学金を複数組み合わせる発想
貸与型奨学金・教育ローンも含めた資金計画
成績が基準を満たさない場合は、給付型だけにこだわらず、貸与型奨学金や教育ローンと組み合わせて資金計画を立てる方法もあります。JASSO第二種奨学金は成績条件がゆるく、多くの学生が利用している制度です。ほかにも自治体奨学金、銀行の教育ローン、国の教育ローン(日本政策金融公庫)など、選択肢は豊富です。
貸与型やローンは成績よりも「保護者の信用・収入」が審査の中心となるため、学力の影響を受けにくい点が特徴です。ただし、利息や返済期間によって総返済額が大きく変わるため、事前のシミュレーションは必須です。返済開始時期や負担の大きさを理解したうえで、最適な組み合わせを検討しましょう。
- JASSO第二種/自治体奨学金/銀行・国の教育ローンの比較
- 成績に関係ないが「保護者の信用・収入」が見られる点
- 返済期間・利息・総返済額をシミュレーションする重要性
今からできる「成績の立て直し」― 申請までに何をするか
奨学金申請までに時間がある場合は、成績を立て直す取り組みを進めることも重要です。評定平均は「提出物」「授業態度」「小テスト」などでも加点されるため、テストだけでなく日常の努力で改善できる要素が多くあります。提出物を欠かさず出す、苦手科目を補習で克服するなど、小さな積み重ねが評定アップにつながります。
また、先生に相談して追試制度や補習の利用方法を確認しておくと、より確実に成績向上を狙うことができます。さらに、成績がギリギリの場合でも「直近の努力」「学びたい分野への意欲」を志望理由書に反映させることで、総合評価でプラスに働くケースもあります。
- 評定を上げやすい科目・レポート・提出物での加点を意識
- 先生への相談・補習・追試など活用できる制度を確認
- 「直近のがんばり」や分野の得意を志望理由書に反映する方法
奨学金採用後の成績基準:打ち切り・停止・警告のライン
「廃止」「停止」「警告」「激励」とは何か
奨学金を受給した後も、成績や単位取得状況に応じて「適格認定」が行われます。JASSOでは毎年、学生が奨学金を継続するのにふさわしい状態かどうかを判断し、その結果が「廃止」「停止」「警告」「激励」の4段階で通知されます。これは、学生が学修を継続する意思や能力を維持できているかを確認するための仕組みです。
特にGPAや取得単位数は重要な判断材料で、留年や単位をほとんど取得できていない状態は「廃止」に該当する可能性があります。「停止」は改善が見込まれるものの基準を満たしていない場合、「警告」は基準ギリギリの状態、「激励」は基準を満たしているがさらなる努力を促す意味で通知されます。
- GPA・取得単位数に応じたJASSOの適格認定の考え方
- 留年・単位0に近い状態など「廃止」になるケースのイメージ
- 「停止」「警告」「激励」ごとの成績水準と処置の違い
奨学金が止まるとどうなる?家計・学業への影響
奨学金の支給が停止されると、学生本人だけでなく家計に大きな影響が出ます。通常、支給停止期間の授業料や生活費は自分や家族で負担する必要があり、場合によっては学費の未納が発生することもあります。そのため、家計シミュレーションをして早めに対策を立てることが重要です。
退学や休学を避けるためには、教育ローンの利用や一時的なアルバイト増など複数の選択肢を組み合わせることが現実的です。また、奨学金窓口や学生支援センターに早めに相談することで、分納制度や家計急変の特例を利用できる可能性があります。
- 支給停止期間の学費・生活費のやりくり(家計シミュレーション)
- 退学・休学を避けるための選択肢(ローン・一時的なアルバイト増など)
- 家族・学校・奨学金窓口への早めの相談の重要性
成績不振になったときに取るべき行動
成績が基準を下回りそうな時期は、焦りや不安が大きくなります。しかし、状況の改善に向けて冷静に行動することが大切です。まず、なぜ成績が落ちたのかを客観的に整理し、出席状況、レポートの提出状況、テスト勉強の方法など、要因を細かく分解するところから始めましょう。
その上で、学内の相談窓口や学生支援センター、カウンセリングルームを積極的に利用することをおすすめします。学習計画の立て直しや生活習慣の改善など、専門スタッフの支援を受けることで成績回復の道筋が見えることがあります。早期対応こそが、奨学金の継続と学業維持の鍵になります。
- まずは「なぜ成績が落ちたのか」を一緒に整理する
- 出席・レポート・試験のどこでつまずいているかを分解
- 学内相談窓口・学生支援センター・カウンセリングの活用例
成績基準をクリアするための勉強・生活・志望理由の整え方
高校時代の評定平均を上げるコツ
給付型奨学金の審査で最も重視されるのが、高校時の評定平均です。評定は定期テストだけで決まるのではなく、提出物、ノート、授業態度、発表など多くの要素が加点対象となります。日々の積み重ねを意識することで、評定は十分に引き上げることが可能です。
- 定期テスト対策+提出物・ノート・発表で点を取りこぼさない
- 苦手科目の底上げで評定全体を押し上げる
- 「授業態度」や「出席状況」も成績に響くことを理解する
大学でGPAを維持するための単位戦略
大学の成績(GPA)は奨学金継続の鍵となる指標です。特に1年次の成績はその後のGPAを大きく左右するため、最初から計画的に単位を取得していくことが重要です。科目ごとの評価基準を早めに把握し、テスト・レポートのどちらが重視されるのかで勉強のスタイルを変えることも効果的です。
- 1年次から基礎科目を計画的に取り、落単を防ぐ時間割の組み方
- テスト・レポートの配点比率を把握して勉強時間を配分する
- グループワークやプレゼン科目での評価ポイント
志望理由書・面接で「成績以外の強み」を伝える方法
給付型奨学金の申請では、成績だけではなく「何を学びたいか」「将来どう社会に貢献したいか」といった姿勢が重視されます。志望理由書や面接で、自分の経験と奨学団体の理念をつなぎ、説得力あるストーリーとして伝えることが採用の決め手となります。
- 将来の夢・進学目的・学びたい分野の具体化
- ボランティア・部活動・アルバイトなどの経験を整理しておく
- 奨学団体の理念・募集要項を読み込み、自分の言葉で結びつける
給付型奨学金の探し方と情報収集のチェックリスト
まずはここから ― 学校・JASSO・公的な情報源
給付型奨学金を確実に見つけるには、まず公的な情報源から調べるのが最も安全で正確です。 高校の進路指導室や奨学金担当窓口では、最新の募集情報や学校推薦が必要な奨学金について詳しい案内が受けられます。 また、JASSOの公式サイトは全国共通の奨学金情報がまとまっており、「進学資金シミュレーター」で世帯状況から受給可能性を自動計算できるため必ず確認したいところです。 文部科学省・自治体の奨学金情報ページでは、地域限定の給付型制度も見つけられます。
- 高校の進路指導室・奨学金担当窓口で聞けること
- JASSO公式サイト・進学資金シミュレーターの活用
- 文科省・自治体の奨学金情報ページの読み方
企業・財団・大学独自の情報をどう集めるか
民間企業や公益財団法人、そして大学独自の給付型奨学金は種類が豊富で、成績基準・所得基準・対象分野が大きく異なります。 大学の奨学金ページや入試要項には、高校成績や入試成績に紐づく学費免除制度などが掲載されています。 財団系の奨学金は募集要項に「成績」「活動実績」「志望理由」などの評価ポイントが細かく書かれているため、必ず条件を読み込みましょう。 検索の際は、単に「奨学金」だけでなく、分野名や地域名、目的と組み合わせることで見つけやすくなります。
- 大学の奨学金ページ・入試要項のチェックポイント
- 企業財団・公益財団法人の募集要項の読み方
- 「分野名+奨学金」「地域名+奨学金」での検索のコツ
募集要項で必ず確認したい「成績」「所得」「併用可否」
給付型奨学金は制度ごとに条件が大きく異なるため、募集要項の細部まで確認することが重要です。 特に成績基準(評定平均・GPA・順位)、世帯所得(年収制限・非課税条件・資産要件など)、そして他制度との併用可否は最初にチェックすべきポイントです。 併用不可の制度も多く、組み合わせによっては受給額が調整されるケースもあるため、早い段階で全体の資金計画を立てておくと安心です。
- 成績基準(評定・GPA・学年順位)の項目
- 世帯所得・資産の条件(年収〇万円以下、非課税世帯など)
- 他の給付型や貸与型との併用可否・支給額調整の有無
ケーススタディ&Q&A:成績と給付型奨学金のリアル
ケース1|評定3.4でJASSO給付型を諦めかけた高校生の場合
評定3.4で「基準に届かない…」と不安を抱えていた高校生のケースです。この学生は、提出物・発表・ノート評価で加点できる科目を重点強化し、最終的に評定を3.5まで引き上げました。また、JASSOだけに依存せず、民間財団の人物重視型奨学金や自治体の小口奨学金も併願。志望理由書では「将来の目標」「進学の必然性」「経済状況」を具体的にまとめ、面談でしっかりアピールしました。
- どのように成績を立て直し、どんな奨学金を組み合わせたか
- 志望理由書でアピールしたポイントの例
- 最終的な資金計画(給付+貸与+家計+アルバイト)
ケース2|大学入学後にGPAを落として「警告」を受けた学生の場合
大学1年の後期でGPAが急落し、JASSOから「警告」を受けた学生のケースでは、まず学内の学生支援センターに相談し、履修計画と学習方法を見直しました。特に、出席率の改善・レポートの提出期限管理・試験対策の方法づくりが大きな改善ポイントに。先生への相談では評価基準を再確認し、グループワーク科目での役割貢献など加点要素を意識することで、翌学期にはGPAが回復し支給継続につながりました。
- どのように状況改善し支給継続につなげたか
- 先生・学内窓口への相談内容とサポート例
- 時間の使い方・生活リズムの見直しポイント
よくある質問Q&A(成績と成績基準に関する疑問)
- Q:成績はいつまでの期間が見られる?
A:予約採用は高校1年〜申込時まで。在学採用は高校最終2年間の成績が評価対象になります。 - Q:5段階評価でない高校の成績はどう扱われる?
A:A〜Eなどの場合は5段階相当に換算されます。難しい場合は「平均以上か」で判断されることもあります。 - Q:成績が3.5に届かないと給付型や第一種は絶対無理?
A:救済措置あり。家計状況、分野別の優れた能力、学習意欲などで採用されるケースがあります。 - Q:一度落ちた奨学金に、成績を上げて再チャレンジできる?
A:可能。多くの奨学金は翌年以降の再応募が認められています。成績改善や活動実績の追加が有利に働きます。
まとめ:成績基準を正しく理解し、自分に合った奨学金選びを
給付型奨学金は「返済不要」という大きなメリットがある一方、成績基準・所得基準・志望理由など、多面的な審査が行われる制度です。特に評定平均3.5やGPAなど、具体的な成績ラインは多くの学生がつまずきやすいポイントですが、成績だけで全てが決まるわけではありません。活動実績、将来のビジョン、意欲、家計状況などを総合評価する制度も多く、成績が不安でも挑戦できる奨学金は数多く存在します。また、民間財団や自治体、大学独自の奨学金は成績基準や評価軸が多様で、組み合わせることで必要な進学費用を十分に確保できるケースも少なくありません。
大切なのは、「自分の現状に合った制度を早くから探すこと」と「改善できる成績は今から上げていくこと」です。定期テストや提出物の工夫で評定は引き上げやすく、大学では履修戦略と生活習慣の見直しがGPA改善につながります。さらに、志望理由書や面接で自分の価値を言語化することで、成績以外の強みが大きなアピール材料になります。奨学金は進学の可能性を広げる重要な制度です。迷った場合は学校や窓口に早めに相談しながら、あなたに最適な奨学金を見つけ、学び続ける未来を着実に実現していきましょう。










