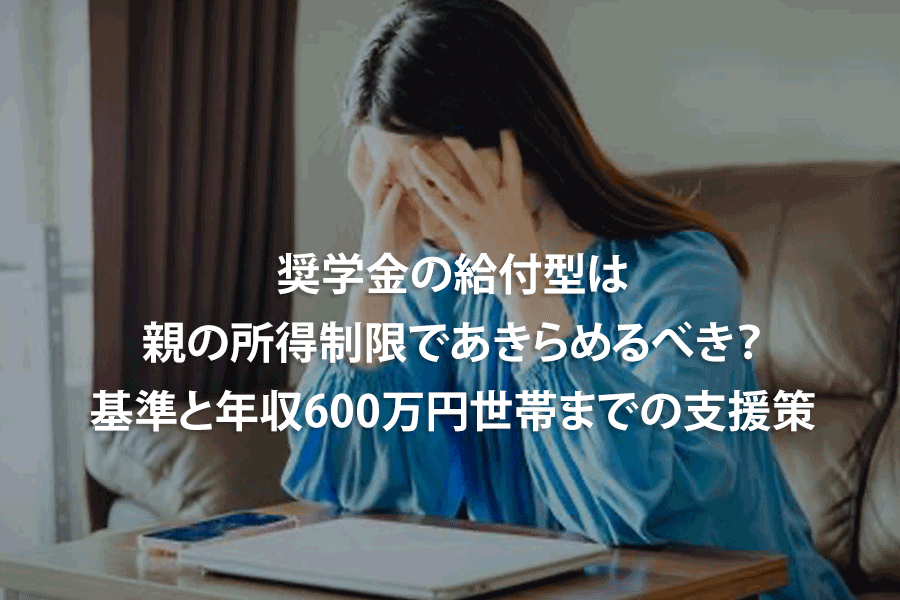
「給付型の奨学金を利用したいけれど、親の年収がネックになりそう」「所得制限にひっかかっていたらどうしよう」──そんな不安から、「うちは無理かも」と最初から給付型奨学金の検討をやめてしまうご家庭も少なくありません。
しかし実際には、日本学生支援機構(JASSO)のように明確な所得基準がある制度もあれば、親の年収に関係なく応募できる給付型奨学金、ひとり親世帯や母子家庭を対象にした制度も存在します。大切なのは、「どの制度なら利用できるのか」「基準に近い場合、どう準備しておくべきか」を正しく理解することです。
本記事では、進学・家計相談に携わってきた専門家の立場から、給付型奨学金の所得制限の考え方、公的・民間それぞれの制度の特徴、審査で重視されるポイント、もし落ちてしまった場合の代替策まで、保護者と高校生・大学生が知っておきたいポイントを整理して解説します。
まず押さえたい:奨学金の「給付型」と「貸与型」の違い
奨学金には大きく分けて「給付型」と「貸与型」があります。どちらも進学を支えるための制度ですが、 返済の有無や利用の考え方が異なります。「なんとなく給付型の方が良さそう」「貸与型は借金だから不安」と感じている方も多いですが、 まずはそれぞれの仕組みを正しく理解するところから始めましょう。この章では、奨学金の基本的な種類と、 近年なぜ給付型奨学金への関心が高まっているのか、そして本記事が扱う「給付型×所得制限」の範囲を整理していきます。
奨学金は大きく「給付型」と「貸与型」の2種類
奨学金は「返済不要の給付型」と「卒業後に返済が必要な貸与型」の2種類に分かれます。 給付型奨学金は、その名のとおり返す必要がない支援で、家計が厳しい世帯や成績優秀者を対象とした制度が多く見られます。 一方、貸与型奨学金は、将来の返済を前提に在学中の学費や生活費を支える仕組みで、卒業後に毎月の返済が発生します。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金でいえば、貸与型は第一種(無利子)と第二種(有利子)に分かれます。 第一種奨学金は利息がつかない代わりに学力や家計の基準が比較的厳しく、第二種奨学金は利息はつくものの、 対象が広く設定されているのが特徴です。「給付だから絶対に安心」「貸与だから危険」という単純なものではなく、 それぞれの特徴を理解したうえで、家計や進路に合った組み合わせを考えることが大切です。
なぜ今、給付型奨学金への関心が高まっているのか
近年、給付型奨学金に注目が集まっている背景には、「経済的な理由で進学をあきらめさせない」という国の方針があります。 日本学生支援機構の給付型奨学金の創設や拡充、住民税非課税世帯だけでなく、一定の収入がある世帯まで対象を広げる動きなど、 公的な支援は少しずつ手厚くなってきました。
一方で、学費や生活費の負担は依然として重く、世帯収入が大きく伸びているわけではありません。 私立大学への進学や自宅外通学が増えるなかで、「奨学金なしでは進学が難しい」という家庭も多く、 そのなかで返済不要の給付型奨学金は家計にとって非常に重要な選択肢となっています。 こうした状況が、「奨学金 給付型 とは」「親の年収がどこまでなら給付型を利用できるのか」といった情報ニーズの高まりにつながっています。
解説する「給付型×所得制限」の範囲
本記事で主に対象とするのは、大学・短大・専門学校への進学時に利用できる給付型奨学金です。 高校や小中学生向けにも給付型の支援制度はありますが、家計基準や目的が異なるため、 ここでは「高等教育(高校卒業後)の進学費用をどう支えるか」という視点に絞って解説していきます。
あわせて、「親の年収」「家計基準」「所得制限」といった言葉の整理も行います。 給付型奨学金には、明確な所得制限が設けられている制度もあれば、年収にかかわらず応募できる制度もあります。 「うちは年収が高いから給付型は無理」「所得制限が厳しそうだから最初からあきらめる」と決めつけてしまう前に、 どのような種類の給付型奨学金があり、自分たちの世帯がどこに当てはまりそうかを、一緒に確認していきましょう。
給付型奨学金の「所得制限」とは?親の年収がどう関係するのか
所得制限=「誰を優先的に支援するか」を決める線引き
給付型奨学金の多くには「所得制限(家計基準)」が設けられています。これは、家計が厳しい世帯を優先的に支援するための仕組みであり、 不公平さではなく、限られた予算を必要とする家庭に届けるための線引きです。 そのため、世帯年収だけで判断されるわけではなく、扶養人数・世帯人数・住居形態(持家/借家)など複数の要素が影響します。
また、自分の世帯がどの位置に当てはまるのかを知ることは非常に重要です。「年収だけで判断して諦めてしまったが、本当は対象だった」 というケースも少なくありません。まずは制度ごとの家計基準を確認し、自分たちが該当する可能性を把握しておくことが大切です。
よくある勘違い①「年収○○万円を1円でも超えると絶対にムリ?」
「年収○○万円以上は対象外」と思い込んでしまう方は多いですが、実際には年収の“目安”と最終的な判定は一致しないことがあります。 判定は住民税情報や課税標準額をもとに行われ、世帯人数や扶養している子どもの人数、住居形態などによって変動します。
さらに、自治体や大学独自の給付型奨学金には、国の制度とはまったく異なる家計基準を採用しているケースもあります。 「うちは対象外だろう」と早い段階で決めつけてしまうのではなく、まずは制度の募集要項を確認することが重要です。
よくある勘違い②「成績がそこまで良くないと給付型は対象外?」
給付型奨学金の中には、たしかに「成績上位者のみ」を対象とする制度も存在します。しかし、日本学生支援機構(JASSO)のように、 家計基準と「学ぶ意欲」を総合的に評価する制度もあり、必ずしも成績だけで判断されるわけではありません。
特に近年では、経済的な理由で学びを諦めないよう、レポート・面接・志望動機などを通じて学生の意欲を確認する制度が増えています。 成績に不安がある場合でも、諦めずに応募できる奨学金は存在します。「家計状況+意欲」が判断材料となるため、適切に準備すれば 給付型奨学金のチャンスは十分にあります。
公的な給付型奨学金(JASSO)の所得基準と年収目安
JASSO給付型奨学金の基本構造(区分と支援内容)
日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金は、世帯の家計状況に応じて「第一区分〜第三区分」の3つに分けられています。 第一区分は住民税非課税世帯、第二区分・第三区分は住民税の課税額に応じて決定され、区分に応じて受け取れる支給額が変わる仕組みです。
さらに、給付型奨学金は授業料等減免制度とセットで運用されるのが特徴です。学費の支援を「奨学金の給付」と「授業料減免」の2本柱で行うことで、 進学に必要な実質負担を大きく引き下げられるよう設計されています。
重要なのは、判定は「年収」だけでなく、住民税の課税情報をもとに行われる点です。給与所得かどうか、世帯構造、扶養人数などによって 同じ年収でも判定結果が変わる場合があるため、単純に「年収だけ見ても判断できない」点を理解しておく必要があります。
世帯人数・給与所得かどうかで変わる「年収の目安」
JASSOの給付型奨学金は、「世帯人数」「給与所得者かどうか」「扶養人数」によって年収の目安が大きく変わります。 たとえば4人世帯の場合、第一区分(住民税非課税)であれば年収270万円前後、第二区分で300万円台、第三区分で380万円台が目安とされています。
また、平均年収450万円の世帯でも扶養人数や家計条件によっては給付型の対象になり得るケースがあります。 共働き・片働き・自営業など、働き方によって住民税の課税額が異なるため、単純に「年収○○万円だから対象外」と判断するのは危険です。
このように年収の目安はあくまで「参考値」であり、実際の判定は住民税額によって行われるため、正確な確認が必要になります。
2024年度以降広がった「年収600万円世帯までの支援」
2024年度から、給付型奨学金の対象が一部拡大されました。これまで対象外だった「年収600万円前後の世帯」でも、以下のいずれかに該当する場合は 支援が受けられる可能性があります。
- 扶養する子どもが3人以上いる世帯
- 私立大学の理工農系に進学する学生がいる世帯
これにより、「うちは年収が高いから給付型は無関係」と思い込んでいた家庭でも、実は対象になる可能性が出てきました。 制度変更は頻繁に行われるため、最新情報を必ずJASSO公式サイトで確認することが不可欠です。
JASSOの給付型と貸与型をどう組み合わせるか
JASSOでは、給付型奨学金と貸与型奨学金(第一種・第二種)を併用することができます。 給付でまかなえなかった分を無利子(第一種)や利子付(第二種)で補う形で、進学に必要な費用を柔軟に確保できます。
ただし、重要なのは「借りすぎない」ことです。卒業後の返済まで見据え、月々の返済額が家計を圧迫しない範囲に収まるよう、 事前にシミュレーションしておく必要があります。JASSOが提供している返還シミュレーションツールを利用し、借りる額と返済計画を 家族でしっかり検討しておくことをおすすめします。
親の年収が関係ない/所得制限が緩い給付型奨学金の例
年収にかかわらず応募できる民間の給付型奨学金の特徴
給付型奨学金の中には、親の年収による明確な上限を設けていない「所得制限が緩いタイプ」も存在します。 代表例としてキーエンス財団の奨学金があり、経済状況は参考にされるものの、明確な年収上限はありません。 そのため、「家計基準では対象外になる」と思っていた家庭でも応募できる可能性があります。
こうした奨学金は、学業成績やレポート、小論文、人物評価などを総合的に判断して選抜するのが特徴です。 家計だけでなく「どれだけ学びたいか」「社会にどう貢献したいか」といった意欲が重視されるため、 成績や活動実績をしっかりまとめておくことが重要です。
また、学費免除制度や大学の特待生制度と混同されやすいですが、民間財団の給付型奨学金は独立した支援制度です。 貸与型奨学金や授業料減免制度と併用できるケースもありますが、団体ごとに併用可否が異なるため、 必ず応募前に募集要項を確認することが欠かせません。
一括給付型・高額給付型のメリット・注意点
「30万円一括給付」のようなタイプの奨学金は、教材費・生活費・留学準備費用など、一度にまとまった支出をカバーしやすいという大きなメリットがあります。 月額支給よりも自由度が高く、自分のタイミングで費用を使いやすい点も魅力です。
ただし、高額給付型は応募者が多く、選考の難易度が高い傾向にあります。書類の不備やレポートの質は合否に直結するため、 丁寧な準備が必須です。また、他の奨学金や学費減免制度と併用できるかどうかは制度によって異なるため、 「併用不可」の場合は受給額の総合バランスを考える必要があります。
特に給付型奨学金は返済不要であるため、受給できれば家計負担を大幅に減らせる一方、 採用枠が限られている点や選考基準の厳しさを理解したうえで挑戦することが大切です。
私立大学独自の給付型・特待生制度も視野に
民間財団だけでなく、多くの私立大学が独自の給付型奨学金や特待生制度を設けています。 入試成績によって学費が大きく減額されたり、評定平均が一定以上であれば授業料の半額〜全額が免除される制度も珍しくありません。
「私立大学は学費が高いから無理」と思われがちですが、逆に私立だからこそ奨学金や特待生制度が充実しているケースも多くあります。 入試成績に応じた減免制度や、学部独自の給付型奨学金が用意されている大学もあり、国公立より実質負担が軽くなるケースもあります。
志望校が決まっている場合は、必ず大学公式サイトの「奨学金」「授業料減免」「特待生制度」のページをチェックしましょう。 制度の内容・募集枠・併用可否・成績条件は大学ごとにまったく異なるため、早めに情報収集しておくことが合格後の選択肢を広げるポイントです。
ひとり親世帯・母子家庭など家計が厳しい家庭向けの給付型奨学金
ひとり親・母子家庭を対象とした民間給付型奨学金の概要
ひとり親家庭・母子家庭を対象とする給付型奨学金には、収入の多寡よりも「生育環境」や生活状況を重視して選考する制度があります。 代表例として明光教育研究所の奨学金があり、年収上限ではなく、家庭環境や学習環境に困難を抱える子どもを支援する仕組みが特徴です。
対象学年が小学生から大学生までと幅広く設定されている制度もあり、「進学だけでなく、学びそのもの」を支えてくれる点が魅力です。 給付金を塾・予備校・通信講座・家庭教師などに活用できる制度も多いため、将来の進学準備にもつながりやすいのがポイントです。
一方で、所得制限が明確に設定されているケースも
ひとり親家庭向け奨学金の中には、みずほ農場教育財産のように「年収○○万円以下」「評定平均4.5以上」など、 明確な家計基準や学力基準を設けている制度も存在します。こうした奨学金は支給額が大きい分、選考要件が厳しくなりやすい傾向があります。
成績要件が高めに設定される理由として、「支援が確実に学業成果につながる学生を支えたい」という制度設計上の意図があります。 ただし、条件を満たしている場合は非常に価値が高く、応募の手間をかけるメリットは十分にあります。
必要書類が多い制度もあるため、応募前に必ず募集要項を確認し、早めに準備を進めることが成功のポイントです。
自治体独自のひとり親世帯向け奨学金・助成制度
自治体が提供する支援には、「奨学金」という名称がついていなくても、実質的には教育費を補助する制度が多くあります。 たとえば、就学援助、入学準備金、高校生向けの修学支援金、大学進学時の入学金助成などが挙げられます。 自治体によって金額も対象条件も異なるため、お住まいの地域の情報を必ずチェックする必要があります。
情報源としては、役所(市役所・区役所)の子育て支援課や教育委員会、社会福祉協議会などが代表的です。 「何をどう調べればいいかわからない」という場合でも、窓口に直接相談すれば制度の一覧や申請方法を教えてもらえます。
また、学校の進路指導室やファイナンシャルプランナー(FP)に相談することで、複数の制度を組み合わせた資金計画のアドバイスを受けることもできます。 ひとりで抱え込まず、専門家や公的機関を活用しながら進学準備を進めることが、最終的にスムーズで確実な方法につながります。
給付型奨学金の審査で見られるポイント:所得制限以外に大事な3要素
①親の年収・家計状況
給付型奨学金の審査では、まず「親の年収」や「家計状況」が土台となります。JASSOの区分(第1〜第3区分)は住民税の課税状況を基準に構成されており、 各団体ごとに独自の家計基準を設けている場合もあります。単純な年収ではなく、扶養人数・住居形態・世帯人数など複数の要素から審査される点が特徴です。
また、一時的な収入減や災害・病気など、家計悪化の理由が明確な場合は別途証明書を提出することで考慮されるケースもあります。 「うちは基準をギリギリ超えている」という家庭でも、まずは高校・大学・奨学金窓口に相談することで、利用できる制度が見つかることも少なくありません。
②子どもの学力・日頃の学習態度
給付型奨学金の選考では、学力の基準が設定されていることがあります。代表例として「5段階評定で3.5以上」「学校内で上位○%以内」などが挙げられます。 成績水準が高いほど有利になる傾向はありますが、成績だけが評価軸ではありません。
一部団体では、課外活動・ボランティア・部活動・資格取得など、学校外での取り組みも評価対象になることがあります。 「学力は平均的でも、意欲的な活動実績を積んでいる」という学生が採用される例もあり、多面的に見てもらえる点が特徴です。
③「学ぶ意欲」を示すレポート・志望理由書
近年多くの給付型奨学金で重視されるのが、「なぜ学びたいのか」「将来どう社会に貢献したいのか」といった意欲の部分です。 これは経済的に厳しい家庭の子どもが、支援を受けることでどのように将来に活かすかを見極めるために設けられています。
注意が必要なのは、ありきたりな文章や抽象的な表現、インターネットの文章をコピペしたような内容はマイナス評価になる点です。 具体的なエピソードや学びたい理由を自分の言葉で書くことが合否を左右します。 高校や大学の先生、進路指導室、FPなどに添削を依頼すると、より説得力のある志望理由書に仕上がり、採用率アップにつながります。
保証人・機関保証の考え方(貸与型との違いも含めて)
給付型奨学金は返済不要であるため、基本的には保証人を求められない制度がほとんどです。一方で、貸与型奨学金(第一種・第二種)は返済が前提のため、 連帯保証人や保証人が必要になります。家族に頼みにくい場合は、保証料を支払うことで利用できる「機関保証」を選択することも可能です。
機関保証は、返済が遅れた場合に保証機関が代わりに返済する仕組みですが、後から本人がその金額を返済する必要があります。 貸与型を利用する可能性がある場合は、保証人を立てるのか、機関保証にするのか、事前に家族と相談しておくことが大切です。
うちの世帯年収で給付型奨学金は狙える?自己チェックとシミュレーション
ステップ1|世帯の「年収」ではなく「課税情報」を確認する
給付型奨学金の判定で重要なのは、「年収額」そのものではなく、住民税の課税情報です。 そのため、まずは源泉徴収票・確定申告書・住民税決定通知書を用意し、どの項目が審査に使われるのかを確認しましょう。
- 源泉徴収票:支払金額(年収)・所得控除後の所得額
- 確定申告書:課税標準額や控除額
- 住民税決定通知書:非課税かどうか、課税額はいくらか
給与所得者と自営業では記載項目や計算方法が異なるため、同じ年収でも課税額が大きく変わるケースがあります。 そのため、単純に「うちは年収○○万円だから対象外」とは判断できません。
また、ネット上にあるシミュレーションはあくまで「参考値」であり、最終判定とは異なることがあります。 正確な判定を知りたい場合は、必ず公式情報を基準に確認する姿勢が大切です。
ステップ2|JASSOの区分に当てはめてみる
次に、世帯の課税情報をJASSOの「第1区分〜第3区分」に照らし合わせてみます。 この区分は、住民税非課税世帯を中心に、課税額に応じて支援内容が大きく変わる仕組みになっています。
ただし、年収の目安は世帯人数や働き方によって変動するため、「微妙なライン」にある家庭は早めに相談することが重要です。 高校や大学の奨学金担当窓口、もしくは進学費用に詳しい専門家であれば、具体的な判定方法を教えてくれます。
また、支給額は子どもの進学先によっても大きく異なります。
- 国公立か私立か
- 文系か理工農系か
- 自宅通学か自宅外通学か
これらの条件で支援額が変わるため、「どれくらい給付される可能性があるか」を早い段階で把握しておくと安心です。
ステップ3|公的+民間+大学独自を組み合わせて全体設計
最後のステップは、利用できそうな奨学金を「組み合わせて」全体の資金計画を作ることです。 公的な給付型だけに頼るのではなく、民間財団や大学独自の奨学金も併用することで、総合的に負担を軽減できます。
たとえば、
- 給付型奨学金で○○万円
- 貸与型は最大△△万円まで
と上限を決めることで、卒業後の返済負担を見据えた無理のない設計ができます。
それでも不足する場合は、教育ローンの活用や家計全体の見直しで補うという選択肢もあります。 進学は大きな投資だからこそ、早めに情報を整理し、複数の制度を組み合わせて最適なプランを作ることが重要です。
もし所得制限や審査で落ちてしまった場合の4つの選択肢
狙いキーワード例:給付型奨学金 落ちた/奨学金 審査 不合格 どうする
選択肢1|他の奨学金・翌年の再申請を検討する
- 制度ごとに基準が違うため、「ダメ元」で諦めないことが重要
- 成績・家計・書類不備など、落ちた理由をできる限り把握する
- 改善できる点(評定アップ・レポートのブラッシュアップなど)
選択肢2|貸与型奨学金や教育ローンを組み合わせる
- 貸与型奨学金のメリット・デメリット(返済負担・金利など)
- 教育ローンで保護者が一部を肩代わりする考え方
- 「借り方を間違えなければ進学の選択肢は広がる」という視点
選択肢3|アルバイトや節約で必要額を減らす
- 学業とのバランスを崩さないアルバイトの時間・職種イメージ
- 奨学金・授業料減免と組み合わせて「借りる額」を下げる発想
- 生活費のシェア・実家からの通学など現実的な工夫例
選択肢4|進学時期・進路の再検討もタブーではない
- 一度社会人を経験してからの進学、地方大学への変更など
- 「今すぐ行くか」「1年準備してから行くか」を冷静に考える
- 第三者(学校・FP・進路相談窓口)に話すことで見える選択肢
給付型奨学金だけに頼らない「進学費用プランニング」のすすめ
学費+生活費の全体像を家族で共有する
進学に必要な費用は、授業料や入学金だけではありません。教材費、交通費、家賃、光熱費、食費などを含めると、年間の総額は想像以上に大きくなります。特に自宅外通学の場合、家賃だけで年間60〜100万円ほど増えることも珍しくありません。
まずは「自宅通学」「一人暮らし」それぞれのケースで必要になる年間コストをざっくりと家族で共有し、どこまでを奨学金で賄い、どこから自己負担を考えるのか位置づけを明確にすることが、プランニングの第一歩です。
給付型・貸与型・教育ローン・貯蓄のバランス設計
進学費用を準備するうえでは、「返済不要のお金」と「将来返すお金」のバランスをどう取るかが鍵になります。給付型奨学金が受けられれば負担は軽くなりますが、それだけで全てをまかなえるケースは多くありません。そのため、貸与型奨学金や教育ローン、自宅からの支援や既存の貯蓄などを組み合わせ、無理のない総額を設計していきます。
特に貸与型奨学金を利用する場合は、社会人になったときの想定年収や生活費を踏まえ、「月にいくらなら無理なく返済できるか」を逆算しておくことが重要です。さらに、奨学金には併用の可否や上限額など細かなルールがあるため、事前に全体像を把握してポートフォリオを組むイメージで計画しておきましょう。
専門家(FP)や学校の進学相談窓口を活用するメリット
奨学金や進学費用の計画は、家計の状況・進路・将来の進学先まで複雑に関係するため、家族だけで判断するのは難しい場合があります。そんなときは、学校の進路指導担当、大学の奨学金窓口、またはファイナンシャルプランナー(FP)など第三者の視点を取り入れることで、見落としていた選択肢に気づけることがあります。
最近は無料で相談できるオンラインサービスも増えており、家計の見直しから奨学金の組み合わせまで専門的なアドバイスを受けられる環境が整っています。自分たちだけで抱え込まず、必要に応じて相談機関を活用することで、より現実的で後悔のない進学費用プランを立てることができます。
まとめ|給付型奨学金の所得制限を正しく理解し、最適な進学費用計画を立てよう
給付型奨学金は「親の年収」や「家計基準」をもとに支援の優先順位を決める制度であり、正しく理解すれば多くの家庭にチャンスがあります。JASSOのように住民税情報を基準とする制度もあれば、民間財団のように所得制限が緩かったり、生育環境や学習意欲を重視する奨学金も存在します。「年収が高いから無理」「成績がそこまで高くないから対象外」という思い込みで可能性を狭めないことが大切です。
また、給付型だけでは進学費用のすべてを賄えないケースも多いため、貸与型奨学金や教育ローン、大学独自の学費減免、貯蓄などを組み合わせた総合的な費用設計が必要です。学費と生活費の「全体像を見える化」し、将来の返済負担も見据えた現実的なプランを作ることで、進学後の家計への影響を最小限に抑えられます。
奨学金制度は複雑で、家庭ごとに最適解が異なります。迷ったときは学校や奨学金窓口、ファイナンシャルプランナーなど専門家に相談し、第三者の視点を取り入れることが、後悔のない進学を実現する最短ルートです。正しい情報と準備が、子どもの学びの機会を最大限に広げる力になります。










