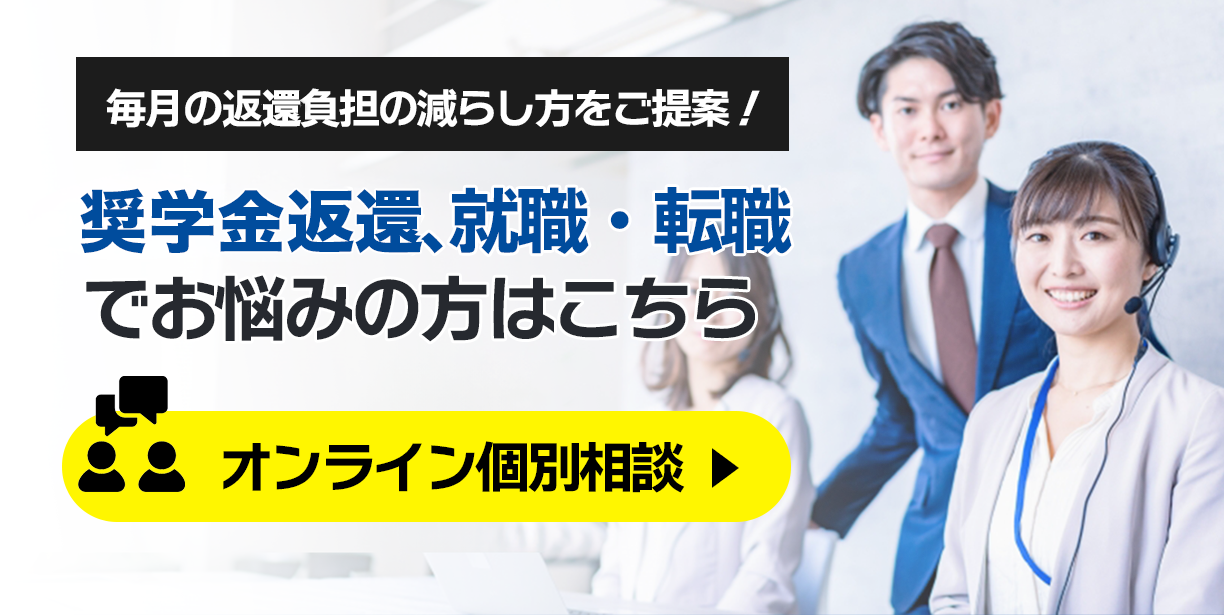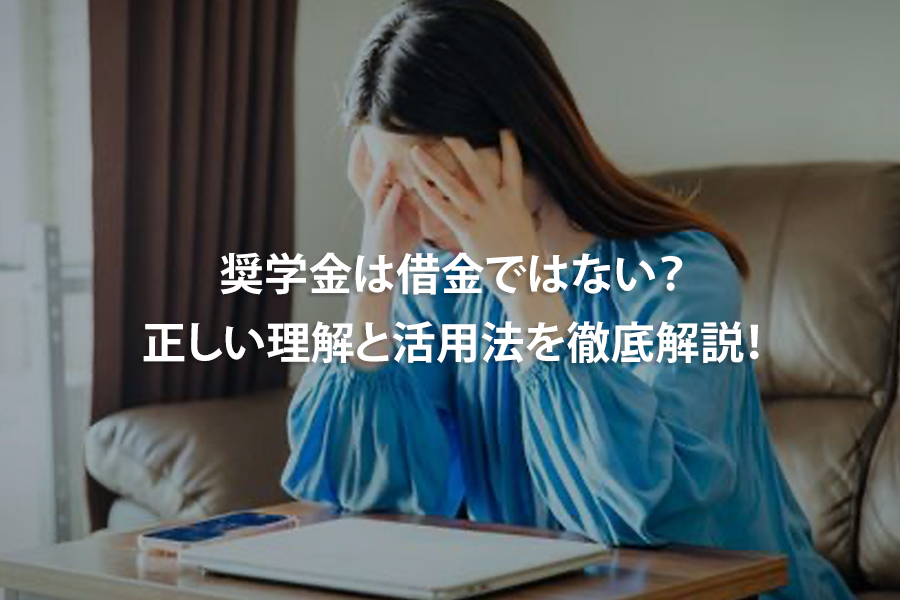
大学進学には入学金や授業料、教材費、生活費など多額の費用が必要です。
経済的な理由で進学を諦めざるを得ない学生も少なくありません。
そんな学生を支援するために設けられているのが奨学金制度です。
しかし、「奨学金=借金」と誤解されることもあります。
本記事では、奨学金の仕組みや種類、正しい活用法について詳しく解説します。
奨学金の基本を理解しよう
奨学金を利用したことがない親世代や、これから進学を考えている学生にとって、
「そもそも奨学金とは何なのか?」が分からないこともあるでしょう。
ここでは、奨学金の目的・提供元・返済義務の有無など、基本的な知識を解説します。
奨学金とは?目的と役割
奨学金とは、経済的な理由で進学が難しい学生を支援するための制度です。
例えば、学業優秀でありながら家庭の事情で大学進学が困難な学生がいるとします。
その学生が大学に進学できないのは、社会にとっても大きな損失です。
奨学金は、こうした学生が経済的負担を理由に進学を諦めないよう設けられています。
また、奨学金には大きく分けて「給付型」と「貸与型」の2種類があり、返済義務の有無が異なります。
奨学金の提供元は?どこから支給されるのか
日本の奨学金制度には、主に以下の提供元があります。
1. 日本学生支援機構(JASSO)
- 文部科学省の管轄下にある独立行政法人で、日本国内最大の奨学金機関
- 奨学金の財源は、税金だけでなく、過去の返済金や財投機関債(財政投融資)によっても支えられている
- 貸与型奨学金(第一種・第二種)と給付型奨学金の2種類を提供している
2. 地方自治体(都道府県・市区町村)
- 各自治体が独自に設ける奨学金制度
- 居住地や進学先に条件がある場合が多い
- 例)東京都の奨学金は、都内の大学進学者のみ対象など
3. 民間団体・企業
- 企業や財団が提供する奨学金
- 寄付を財源とし、特定の分野や条件を満たす学生を支援
- 例)大学独自の奨学金や、特定の業界・職種向け奨学金など
奨学金の返済義務について
「奨学金は借金と同じ」と思われがちですが、すべてに返済義務があるわけではありません。
奨学金には、以下の2種類があります。
1. 給付型奨学金(返済不要)
- 返済の必要がなく、支給された金額は返さなくてOK
- 経済的に厳しい家庭の学生が対象
- 受給には学力・家計状況などの条件あり
2. 貸与型奨学金(返済必要)
- 卒業後に分割で返済する奨学金
- 無利子(第一種)と有利子(第二種)がある
- 団体によって返済期限や月々の返済額が異なる
奨学金の種類:給付型奨学金
先ほど、奨学金には給付型と貸与型の2種類があると解説しました。
まずは、返済不要の給付型奨学金について詳しく見ていきましょう。
給付型奨学金は、返済義務がないため、一見すると非常に魅力的な制度に思えます。
しかし、誰でも利用できるわけではなく、厳しい審査基準が設けられています。
給付型奨学金の対象者
給付型奨学金は、一定の学力基準を満たし、経済的に困難な状況にある学生が対象となります。
具体的には、
- 学業成績が優秀であること
- 家計が厳しいこと(一定の所得基準以下)
- 向学心を持ち、学業を継続する意思があること
これらの条件を満たす必要があります。
「大学には通いたいが、家庭の事情で進学が難しい」「将来的に奨学金の返済が負担になりそう」という学生を支援するための制度です。
給付型奨学金の受給条件
給付型奨学金の受給条件は、提供元によって異なりますが、ここでは代表的な給付型奨学金であるJASSO(日本学生支援機構)の基準を例に紹介します。
JASSOの給付型奨学金の主な条件は以下の通りです。
- 学業成績の基準:高校での全履修科目の評定平均値が3.5以上
- 所得基準:世帯の収入や資産が一定額以下(親の資産が2,000万円以下、片親の場合は1,250万円以下)
※ 具体的な基準は年度ごとに変更される可能性があるため、最新情報はJASSOの公式サイトで確認してください。
給付型奨学金の代表的な制度
JASSO以外にも、地方自治体や大学、企業・財団などが給付型奨学金を提供しています。
代表的な給付型奨学金の例
- JASSO(日本学生支援機構)
- 国公立・私立問わず対象
- 受給額は進学先(自宅通学・自宅外通学)によって異なる
- 地方自治体の奨学金
- 各自治体が独自に設ける奨学金制度
- 居住地や進学先により条件が異なる
- 大学独自の奨学金
- 例:東京大学「さつき会奨学金」(女子学生限定、月額5万円)
- 企業・財団の奨学金
- 例:キーエンス財団奨学金、三菱UFJ奨学財団 など
給付型奨学金は返済不要ですが、その分審査が厳しく、成績維持や活動報告が求められる場合もあります。
奨学金の種類:貸与型奨学金
ここまでは給付型奨学金について解説しました。
次に、貸与型奨学金について詳しく見ていきましょう。
貸与型奨学金の仕組み
貸与型奨学金は、一定の学力基準と所得条件を満たした学生が利用できる制度です。
給付型と異なり、卒業後に返済が必要となる点が大きな違いです。
貸与型奨学金の返済方法には、以下の2種類があります。
- 定額返還方式:毎月一定額を返済する方式
- 所得連動返還方式:卒業後の収入に応じて返済額が変動する方式(一定の条件あり)
JASSOでは、家計の負担を軽減するために、所得連動返還方式を導入しています。
無利子と有利子の違い
貸与型奨学金は、さらに**第一種奨学金(無利子)と第二種奨学金(有利子)**に分かれます。
第一種奨学金(無利子)
- 返済時に利息が発生しない
- 受給には厳しい成績基準と所得基準がある
- 受給額に上限がある(例:自宅生は最大月額4.5万円、自宅外生は最大月額6万円)
第二種奨学金(有利子)
- 返済時に利息が発生(上限年利3%、実際は低めに設定されることが多い)
- 第一種よりも審査基準が緩やか
- 月額最大12万円まで選択可能
「できるだけ返済負担を減らしたい」場合は第一種奨学金を、「借入額を増やしたい」場合は第二種奨学金を選ぶケースが多いです。
貸与型奨学金の代表的な制度
貸与型奨学金の代表的な制度として、JASSOの第一種・第二種奨学金が挙げられます。
また、JASSO以外にも、金融機関が提供する教育ローンという選択肢もあります。
JASSOの貸与型奨学金
- 名義人は学生本人
- 卒業後、決められた期間内に返済
銀行・信用金庫の教育ローン
- 名義人は保護者
- 返済義務は保護者が負う
- JASSOの奨学金よりも借入上限額が高い
教育ローンは、奨学金とは異なり、審査基準が異なるため、家計の状況を考慮しながら選択することが重要です。
奨学金の申込方法
ここまで、給付型奨学金と貸与型奨学金の特徴について確認してきました。
それでは、実際に奨学金を申し込むにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは、奨学金の申請時期や必要書類について詳しく解説します。
奨学金の申請時期とスケジュール
奨学金の申請は、高校在学中に予約する方法(予約採用)**と、**大学入学後に申し込む方法(在学採用)の2種類があります。
どちらの方法でも、年2回の申請期間しかないため、スケジュールを事前に確認することが重要です。
- 予約採用(高校在学中の申請)
- 申請期間:4月~7月 または 10月(学校による)
- 注意点:高校によって秋の申請を受け付けない場合がある
- 在学採用(大学入学後の申請)
- 申請期間:4月~7月 または 10月
- 対象:大学進学後に奨学金が必要になった学生
高校在学中に申し込む場合、在学中に手続きが必要になるため、担任の先生や進路指導室に相談しておきましょう。
奨学金の申請に必要な書類
JASSO(日本学生支援機構)の奨学金を申請する場合、主に以下の書類が必要になります。
- スカラネット申込書(オンライン申請用の情報を記入する書類)
- 奨学金確認書(給付型・貸与型の別に必要)
- 成績証明書(高校から交付される)
- 保護者の所得証明書類(給与所得者は源泉徴収票、自営業者は確定申告書の写しなど)
申請する奨学金の種類によって必要書類が異なるため、JASSOの公式サイトで最新の情報を確認することをおすすめします。
予約型奨学金(高校在学中の申し込み)
高校在学中に奨学金を申し込める「予約採用」についても詳しく見ていきましょう。
高校在学中に申し込める奨学金とは?
JASSOの奨学金は、高校在学中に給付型奨学金と貸与型奨学金の両方を予約することが可能です。
また、文部科学省が提供する高等学校等就学支援金制度もあり、これは高校在学中に給付型奨学金を受けられる制度です。
予約型奨学金を活用することで、大学入学前から経済的な準備がしやすくなるというメリットがあります。
予約型奨学金の対象と条件
予約型奨学金の受給条件は、大学在学中に申請する場合とほぼ同じです。
- 学業成績の基準:高校2年生時の評定平均が3.5以上
- 家計の基準:世帯収入が一定額以下
なお、大学進学後に奨学金を更新する場合、高校3年生時の成績も考慮されるため、学業をおろそかにしないことが重要です。
申込手順とスケジュール
予約型奨学金の申込手順は、大学入学後の在学採用と大きな違いはありません。
- 申請期間:5月~6月
- 審査結果の通知:10月ごろ
在学採用では審査結果が比較的早く通知されますが、予約採用では結果が出るまで時間がかかるため、早めに申請しておきましょう。
奨学金は何に使える?
奨学金を受給した場合、そのお金はどのような用途に使えるのでしょうか?
結論として、奨学金には厳密な使途制限はなく、学業に関する費用だけでなく、生活費などにも利用できます。
ここでは、奨学金の一般的な使い道について解説します。
授業料・入学金
大学進学時に最も費用がかかるのが、授業料と入学金です。
- 国公立大学の授業料(2025年現在):年間約53万5,800円
- 国公立大学の入学金:28万2,000円
私立大学の場合、授業料・入学金はさらに高額になるため、奨学金を活用する学生も多くいます。
教材費・学習用品費
大学の講義では、教科書や参考書の購入が必要です。
- 教科書代:1冊あたり数千円~1万円
- 理系の場合、実験用具や専門機器の購入が必要なこともある
奨学金の一部を教材費に充てることで、学習環境を整えやすくなります。
生活費
大学生の多くは、一人暮らしを始めるため、毎月の家賃や光熱費、食費が発生します。
- 家賃:都市部で月5~7万円程度
- 光熱費・通信費:1万~2万円
- 食費:月2万~3万円
自宅から通学する場合でも、通学費や交友費などの出費がかかるため、奨学金を生活費に充てるケースもあります。
海外留学費用
近年、海外の大学に留学する学生も増えています。
しかし、海外留学には通常の学費に加えて、渡航費や生活費が必要です。
- 留学先の授業料
- 渡航費・滞在費
- 生活費
奨学金の種類によっては、海外留学費用を支援する専用の奨学金(JASSOの「海外留学支援制度」など)もあります。
奨学金のメリット
奨学金は、大学進学を経済的に支援する重要な制度です。
実際に奨学金を利用して4年間大学に通えたという学生も多くいます。
特に返済不要の給付型奨学金は魅力的ですが、**貸与型奨学金(返済義務あり)**を利用するかどうか悩む人も少なくありません。
ここでは、奨学金の主なメリットについて詳しく解説します。
経済的負担の軽減
奨学金の最大のメリットは、大学生活にかかる経済的負担を軽減できることです。
大学進学には、学費・生活費・教材費・交通費など多くの費用が発生します。
- 国公立大学:授業料 約53万5,800円/年 + 入学金 28万2,000円
- 私立大学:学部によるが、年間100万円以上かかることも
これらの費用をすべて自己資金で賄うのは難しい家庭も多いため、奨学金を利用することで進学の選択肢が広がります。
また、奨学金を活用することで、親の負担を軽減し、家計を安定させることも可能です。
学業に専念できる
大学生の多くはアルバイトをしていますが、学費や生活費を稼ぐために長時間のアルバイトに追われると学業に支障が出る可能性があります。
- 長時間のアルバイト → 学業に集中できない → 単位を落とすリスク
- 奨学金を活用することで、無理なく学業に専念できる環境を作ることができる
経済的な理由で大学進学を諦めたり、学業とアルバイトの両立が難しくなる前に、奨学金を利用して勉強に集中できる環境を整えることも重要です。
将来のキャリア形成に有利
大学に進学することで、専門的な知識やスキルを身につけ、就職の選択肢が広がるというメリットがあります。
- 大学のキャリアセンターを活用できる(就職相談・企業紹介・インターンシップ支援)
- 専門的な資格の取得が可能(医師・弁護士・公認会計士などは大学進学が前提)
- 大学の人脈が将来の仕事に活かせる
大学を卒業することで、初任給や生涯年収が高くなる傾向もあり、奨学金を活用して大学進学を実現することは、将来的なキャリアにも大きく影響します。
また、奨学金を利用することで留学や資格取得のための費用を確保しやすくなるというメリットもあります。
奨学金のデメリット
奨学金には多くのメリットがありますが、特に**貸与型奨学金(返済義務あり)**を利用する場合は、慎重に検討する必要があります。
ここでは、奨学金のデメリットについて解説します。
返済の負担
貸与型奨学金を利用した場合、大学卒業後に返済が必要になります。
特に有利子の奨学金(JASSOの第二種など)を利用した場合は、返済額が増えるため注意が必要です。
- 第一種奨学金(無利子):借入額と同額を返済
- 第二種奨学金(有利子):借入額+利息を返済
例:月額5万円×4年間(48か月)の場合
- 無利子:5万円 × 48か月 = 240万円
- 有利子(年利1%の場合):約250万円以上になる可能性
また、卒業後の就職状況によっては、奨学金の返済が経済的な負担になることも考えられます。
そのため、奨学金を利用する際は、返済計画をしっかりと立てることが重要です。
返済滞納のリスク
奨学金を適切に返済できないと、信用情報(クレジットスコア)に影響を与える可能性があります。
- 返済を滞納すると、信用情報に傷がつく
- クレジットカードの発行や住宅ローンの審査が通らなくなる可能性
- ブラックリストに載ると、新たな借入ができなくなる
このようなリスクを避けるために、奨学金を借りる前に返済可能な金額を計算し、適切な資金計画を立てることが重要です。
まとめ|奨学金を賢く選び、計画的に活用しよう
奨学金は、大学進学の強い味方になる制度ですが、貸与型奨学金には返済義務があるため慎重に検討する必要があります。
奨学金を利用する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
- まずは給付型奨学金を優先的に検討する
- 貸与型奨学金を利用する場合は、無利子(第一種)をできるだけ選ぶ
- 返済シミュレーションを行い、卒業後の負担を考慮する
奨学金は、適切に活用すれば将来のキャリアを大きく広げる手助けとなる制度です。
計画的に選び、無理のない範囲で活用しましょう。