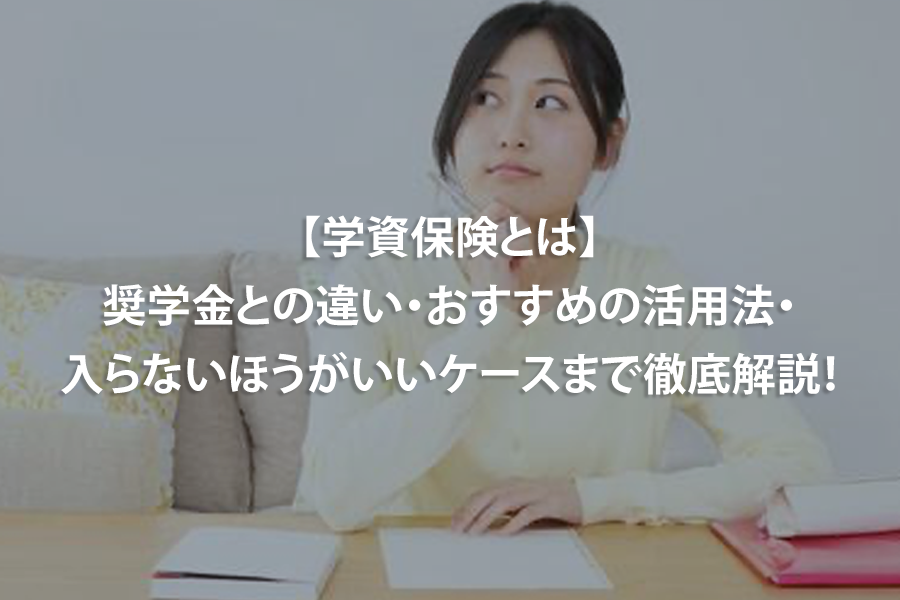
子どもの進学や出産を間近に控えている方にとって、今後かかる高額な教育資金は悩みの種かもしれません。
教育資金に関する不安を抱えている方から注目されているのが学資保険です。
学資保険とはどのような仕組みの保険で、加入するメリット・デメリットはなんなのか気になる方も多いでしょう。
この記事では、そのような疑問にお答えしつつ、学資保険を奨学金やその他の資産形成手段とも比較します。
また、学資保険に入らないほうが良いケースもお伝えするため、ぜひ参考になさってください。
学資保険とは?仕組みと基本を解説
学資保険とは、子どもの教育資金を計画的に準備するために用いる貯蓄型の保険商品です。
毎月決まった保険料を支払うことにより、子どもの成長後にまとまった教育資金を受け取れます。
まずは学資保険とは何か、その仕組みと基本について詳しく見ていきましょう。
学資保険とは何か?
学資保険は、保険と貯蓄を組み合わせた教育資金準備手段です。
貯蓄機能と保険機能を組み合わせた保険に加入し、月々の保険料を支払うことにより、子どもの進学時や満期時にまとまった資金を受け取れます。
学資保険は主に民間の生命保険会社が商品として提供しており、子どもが生まれてから小学校を卒業するまでの間のいずれかのタイミングで加入することが一般的です。
文部科学省の「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」によると、2023年度の平均授業料は私立大学で約93万円、国公立大学は約53.58万円と高額です。
また、進学時には別途入学金を用意する必要もあり、これらの学費は多くの家庭にとって悩みの種となるでしょう。
このような背景により、学資保険は計画的な資金準備手段として人気を集めています。
一般的な学資保険の場合、保険の契約者は親、被保険者は子どもです。
つまり、親が保険料を支払い、満期金は被保険者である子どもが受け取ることになります。
学資保険の満期は、子どもが進学するタイミングに設定することが普通です。
ただし、一部のプランでは、中学入学や高校入学のタイミングに合わせて、保険金の一部を受け取れる場合があります。
支払い・受け取りの流れ
学資保険における月々の保険料は数千円~数万円で、加入する時の子どもの年齢や満期金額、契約期間によって異なります。
たとえば、18歳満期で300万円の満期金を受け取る学資保険に0歳から加入する場合、保険料が月々15,000円~20,000円が目安です。
支払方法は月払いが基本ですが、年払いなどを選べる場合もあります。
学資保険の特徴は、子どもが進学するタイミングに合わせて保険金を受け取れることです。
18歳の大学進学に合わせて数百万円の満期金を一括で受け取れるプランもあれば、中学・高校・大学それぞれの進学時に分割で保険金が給付されるプランもあります。
また、プランの内容により、契約者が死亡または重度障害状態により働くことが難しい状況に陥った場合は、その時点で保険料の支払いが免除され、満期金は通常通りに受け取れる場合もあります。
奨学金と学資保険の違い
奨学金と学資保険は、どちらも子どもの教育資金を目的とする点では一致しています。
しかし、誰がお金を負担するかなど、その性質には大きな違いがあるため、それぞれの特徴を整理しておきましょう。
ここでは、そもそも奨学金とは何か解説したうえで、学資保険との違いをご紹介します。
奨学金とは?
そもそも奨学金とは、学生が学費や学生生活中に必要となる生活費に苦心しないように設けられた資金支援制度です。
日本学生支援機構(JASSO)による奨学金を指すことが一般的ですが、一部の自治体や民間企業が独自に奨学金を提供することもあります。
奨学金の種類は、大きく分けて「給付型」と「貸与型」の2つです。
・給付型奨学金:返済不要ながら利用するための条件がやや厳しい
・貸与型給付金:将来的に返済する必要があるものの、借入の条件は給付型よりも緩い
JASSOによる奨学金の場合、貸与型奨学金はさらに「第一種」と「第二種」の2つに分かれます。
・第一種奨学金:無利子ではあるものの利用するための条件がやや厳しい
・第二種奨学金:有利子となる一方で第一種より審査が緩い
奨学金は主に大学進学時に申請する制度で、返済義務の有無は利用する奨学金のタイプによって異なります。
貸与型給付金の場合、卒業から20年以内に完済することが一般的です。
一方の学資保険は、子どもの幼少期に契約して積み立てをスタートします。
満期金は大学などへの進学時に受け取り、返済義務は一切ありません。
学資保険と奨学金の比較表
学資保険と奨学金をいくつかのポイントで比較してみます。
まず、お金を受け取るタイミングですが、学資保険は進学時または18歳や22歳などの満期に受け取ることが基本です。
一方の奨学金は、給付型の場合は大学進学後に毎月または年2回、貸与型の場合は大学進学後に毎月受け取ります。
親子の負担については、学資保険は親が支払い、子どもに負担がかからないことが特徴です。
一方の奨学金は、給付型の場合は親子双方に負担がかかりません。
しかし、貸与型は卒業後に子どもが返済することになり、条件により親が連帯保証人となる場合があります。
また、緊急時の対応を比較すると、学資保険は契約者の親が死亡または高度障害に陥った場合は保険料が免除され、満期金は予定通りに受け取れます。
一方の奨学金は、親の状況に関係なく支給されることが特徴です。
ここまでの比較をまとめると、学資保険は計画的な学費の準備に適しており、親の死亡など万が一のリスクにも対応できます。
一方の奨学金は進学後の資金繰りに適していることが特徴で、特に給付型は低所得世帯が学費の負担を軽減するために活用する制度として有効です。
学資保険のメリットとおすすめのケース
学資保険を契約すべきかどうかで現在も悩んでいる方は多いでしょう。
そのための判断材料として知っておくと良いのは、学資保険ならではのメリットです。
ここでは、学資保険の主なメリットをご紹介したうえで、学資保険がどのような家庭におすすめできるのかを解説します。
学資保険の主なメリット
学資保険のメリットについて、3つのポイントから解説します。
メリット1.強制的な積み立てによる貯蓄効果がある
学資保険は保険料の支払いが毎月義務付けられるため、貯蓄が苦手な家庭でもコツコツと教育資金を準備できます。
積立方法としては、銀行預金が最も身近ですが、銀行預金は好きなタイミングで引き出しができてしまうでしょう。
一方の学資保険は、原則として途中引き出しが不可能なため、目的外の出費を防いで確実に教育資金を確保できます。
メリット2.契約者に万一の事態が起きても満期金を受け取れる
契約者となる親が万が一死亡もしくは高度障害状態に陥ったとしても、それ以降の保険料の支払いが免除されることに加えて、満期金は予定通りに受け取れます。
学資保険には、生命保険に似た保障機能が付帯するため、親に何があっても子どもの教育資金は確実に守れるのです。
なお、保険会社大手のメットライフ生命「高度障害状態とはどのような状態ですか。」によると、高度障害状態とは主に以下の状態を指します。
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったものなど
契約する保険の内容によって異なるため、詳しくは契約時の約款を確認しましょう。
メリット3.返済不要な教育資金を確保でき安心感がある
第二種奨学金(貸与型)とは異なり、学資保険は返済不要な教育資金です。
大学などへの進学時に満期金を全額使ったとしても、卒業後に子どもがその資金を返済する必要がありません。
子どもが将来の不安を抱えずに勉強に集中できることは、親にとっても大きな安心材料と言えるでしょう。
こんな家庭におすすめ!
学資保険への加入をおすすめできるのは、主に次の家庭です。
・貯蓄が苦手でコツコツ続けられない
・子どもがまだ小さい(0~6歳)
・教育費に確実に備えたいがローリスクで運用したい
つい浪費しがちで、貯蓄する習慣がない家庭には、将来の学費を半強制的に積み立てられる学資保険がおすすめです。
仮に月1万円の保険料を18年間にわたって支払い続けた場合、約216万円を積み立てられる計算になります。
数百万円単位のお金を計画的に積み立てる自信がない方は、学資保険への加入を検討すると良いでしょう。
次に、子どもが未就学児の方にも学資保険がおすすめです。
学資保険は加入時の子どもの年齢が若いほど保険料が安い傾向にあります。
仮に0歳から学資保険に加入すると、18歳時点で受け取れる満期金は支払総額に対して105~110%程度になる場合が多く、長い目で見れば早期加入がお得です。
また、投資に抵抗がある家庭や元本割れリスクを避けたい家庭にも、安定性がある学資保険が適しています。
つみたてNISAや投資信託と比べるとリターンは少なめですが、確実に教育資金を準備できます。
学資保険のデメリットと注意点
学資保険には先述したメリットがある一方で、デメリットと注意点もあります。
特に途中解約をする可能性がある場合は、元本割れのリスクにも警戒しなければなりません。
ここでは、学資保険を契約する前に知っておくと良い注意点について解説します。
途中解約リスクと返戻率
学資保険を途中解約すると、返戻金が払込保険料を下回り、元本割れを起こすリスクがあります。
特に加入後数年以内の解約では、保険会社の事務手数料や運用コストが差し引かれ、返戻率が80~90%程度になることもあるため要注意です。
契約前に解約時の返戻率を確認しておきましょう。
また、学資保険の満期金は契約時に固定されるため、インフレが進むと実質的な価値が下がる可能性があります。
たとえば、2023年度の私立大学授業料は約93万円ですが、将来的には100万円を超える可能性もあるでしょう。
学資保険契約時に固定された満期金では、入学時の学費が不足するリスクがあります。
運用効率が悪い場合も
学資保険の返戻率は、利用する保険会社やプランにより異なります。
現状は低金利であるため、将来の返戻率が100%を下回る商品もあり、銀行預金やほかの投資手段と比べて運用効率が悪い可能性があるため注意しましょう。
仮に105~110%程度の返戻率だとしても、つみたてNISAの期待利回りである年3~5%と比べると低いです。
つみたてNISAやジュニアNISAは、年利3~7%程度の成長が期待できます。
学資保険ほどの安定感はありませんが、リスクを取ることに抵抗がない場合は、投資信託などそのほかの手段で資金を運用したほうが、教育資金を増やせる可能性があるでしょう。
学資保険は「入らないほうがいい」って本当?
SNSをはじめとするインターネットでは「学資保険には入らないほうがいい」といった声も多く投稿されています。
学資保険に入らないほうがいいケースや学資保険への加入前に確認しておきたいことを見ていきましょう。
入らないほうがいいケースとは?
学資保険に入らないほうがいいケースは、具体的に次の3つです。
・教育費以外の目的でも資金が必要になる家庭
・高リターンを求める投資志向の家庭
・家計に余裕がなく月々の保険料支払いが苦しい場合
そもそも学資保険は教育資金に特化した商品です。
たとえば、「マイホームを購入するために住宅ローンを組みたい」と考えている家庭には向いていません。
学資保険は流動性が低く、急な出費に対応しにくいため、月々の保険料の支払いが苦しい家庭も、慌てて契約しないほうがいいでしょう。
また、先述したように、学資保険は安定性が高い一方で利回りが低い商品です。
投資に対して高リターンを求める家庭は、つみたてNISAなどに投資したほうがメリットを感じやすくなります。
加入前に確認しておきたい3つのこと
学資保険に加入する前に確認しておきたいことが3つあります。
それぞれを詳しく見ていきましょう。
1.ほかの資産形成手段との比較
学資保険を検討する前に、つみたてNISAや教育ローン、貯金などほかの選択肢を比較しましょう。
金融庁の「資産運用シミュレーション」ツールを活用すると、投資と保険の違いを確認しながらシミュレーションできます。
2.保険の種類・保障内容の把握
学資保険には「貯蓄重視型」「保障重視型」「複合型」などの種類があります。
保障内容や満期金を受け取るタイミングが異なるため、保障内容を把握したうえで、理想に合った種類を選びましょう。
3.契約期間と解約条件
契約期間や解約時の返戻率も確認します。
早期解約による元本割れリスクや保険料免除特約の条件を保険会社に問い合わせましょう。
学資保険と他の教育費準備手段を比較 この記事の最後に、学資保険とその他の教育費準備手段を比較します。
「教育ローン」「つみたてNISA」とは何が違うのか、それぞれのポイントを見ていきましょう。
教育ローンとの違い
教育ローンとは、進学時に学費を借り入れる制度で、銀行や日本学生支援機構(JASSO)が提供しています。
返済期間は5~15年、金利は1~3%程度が相場です。
教育ローンは借金ですが、学資保険は積み立て+保障の2段構えとなることがポイントです。
また、教育ローンは借金のため、契約者の返済能力が求められます。
学資保険は返済が不要であり、親の死亡・高度障害時に資金が確保されるためリスクが低いです。
つみたてNISAとの違い
つみたてNISAは、投資信託やETFを積み立てる投資商品で、年間40万円まで非課税で運用可能です。
学資保険は保険会社が運用するほぼ元本保証の商品ですが、利回りは低めに設定されています。
つみたてNISAは年利3~7%の成長が期待できますが、一方で市場変動による元本割れリスクがあるのです。
そのため、学資保険は安定性を重視する家庭に、つみたてNISAはリスクを取れる家庭に向いています。
たとえば、月1万円を18年間積み立てた場合、学資保険の満期金は約250万円でしょう。
一方、つみたてNISAで年利5%を確保できた場合は、18年間で400万円のリターンを得られる場合があります。
まとめ
学資保険とは、子どもの教育資金を準備するための保険です。
強制的に積み立てられるほか、親が死亡または高度障害に陥った際の保障が充実しており、将来の返済も不要です。
ただし、途中解約すると元本割れするリスクがあるほか、運用益も少なめになります。
つみたてNISAや教育ローンとも比較しながら、最適な手段を選んで子どもの教育資金を確保しましょう。










