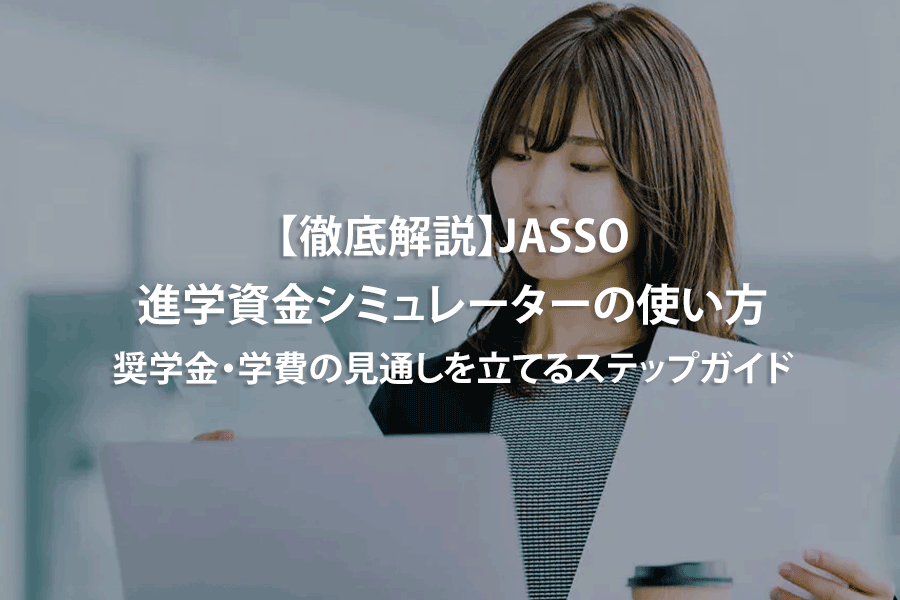
子どもの教育費にかかる費用は高額なため、慎重に資金計画を立てなければなりません。
この際に役立つのが、JASSO(日本学生支援機構)が提供する進学資金シミュレーターです。
この記事では、進学資金シミュレーターの目的や特徴といった概要や具体的な使い方などについて解説します。
この記事を参考に、進学に必要な資金や奨学金との組み合わせ方などについてお考えいただければ幸いです。
JASSO進学資金シミュレーターとは?
JASSO進学資金シミュレーターについて、提供されている目的や特徴を見てみましょう。
進学資金シミュレーターの概要
進学資金シミュレーターは、JASSO(日本学生支援機構)が公式サイトで無償提供している公式ツールです。
https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
進学にかかる費用の目安を計算し、その費用を賄うために必要な奨学金などの支援金がどの程度の金額になるのか見積もることを目的としています。
JASSOは、貸与型奨学金や給付型奨学金などを提供する、国の奨学金制度を担う主要機関です。
提供されるツールは国の基準に基づいて設計されており、高い信頼性があります。
利用できる対象
進学資金シミュレーターは利用者を限定しておらず、誰でも利用できます。
たとえば、以下のような方が利用可能です。
・高校生(学生本人)
・保護者
・教員など学校関係者
自身の進路選択や子どもの教育資金の準備、生徒の進路指導への対応などを行えます。
できること一覧
進学資金シミュレーターでできることは次のとおりです。
・学費の概算
・生活費の概算
・奨学金の概算
・返済額の概算
・費用総額の把握
利用するメリット
進学資金シミュレーターを利用する最大のメリットは、進学費用の全体像と自己資金との間に生じる不足額を把握できる点です。
学費に対する漠然とした不安の解消や過剰な借り入れの回避につながることがメリットと言えます。
進学資金シミュレーターでわかる3つのこと
ここでは、進学資金シミュレーターを使ってわかることを3つご紹介します。
① 学校種別ごとの学費
進学資金シミュレーターは、文部科学省の統計データなどに基づき、学校種別ごとの平均的な学費の概算を算出します。
国公立大学、私立大学、短期大学・専門学校と学校種別を分けて、平均的な学費を把握することが可能です。
② 生活費・家計支出のシミュレーション
学費に加えて、生活費や家計支出のシミュレーションも可能です。
自宅通学をする場合、アパートを借りる場合、寮生活をする場合など、シチュエーションごとに支出の全体像を把握できます。
③ 奨学金や給付型支援金の受給額・返還額の見通し
世帯の年収や家族構成、進学先の学校区分を入力することにより、奨学金・給付型支援金の受給額の目安を確認できます。
これにより、将来的に発生する支出の総額が見えるでしょう。
進学資金シミュレーターの使い方
進学資金シミュレーターの使い方はシンプルです。
ここでは、基本的な操作方法を6つのステップに分けて解説するため、この項目を見ながらシミュレーションを進めてみましょう。
STEP1:シミュレーター画面にアクセス
まずは、JASSO(日本学生支援機構)の公式サイト内にある「進学資金シミュレーター」のページにアクセスします。
サイト内のナビゲーションに従い、試算を開始してください。
STEP2:学校区分・学部系統を選ぶ
次に、以下の中から進学を予定している学校の区分を選択します。
・大学(昼間または夜間)
・短期大学
・高等専門学校
・専門学校
私立大学の場合は、さらに文系・理系・医療系など「学部系統」を選択します。
これは、学部系統によって学費が大きく異なるためです。
STEP3:自宅・下宿などの生活形態を入力
生活形態は「自宅通学」と「自宅外通学」のいずれかを選択しましょう。
下宿やアパート暮らしなどの自宅外通学を希望する場合は、家賃や光熱費などが別途かかるため、生活費の概算が大きく変わります。
STEP4:学費・生活費の想定金額を調整
試算の精度を大きく左右するポイントです。
進学資金シミュレーターが表示する学費や生活費は平均的な概算額となるため、微調整して実際にかかる費用に近付けましょう。
学費は、進学予定先の大学・専門学校のHPなどで確認できます。
生活費は、想定される家賃や仕送り額を考慮して調整してください。
特に家賃は、生活する地域によって数万円単位の差が生じる可能性が高いです。
STEP5:奨学金・給付金・教育ローンを入力
世帯年収や家族構成などを入力することにより、奨学金の受給資格の有無や概算額が表示されます。
借り入れを検討している奨学金・給付金や教育ローンの金額、用意できる自己資金を入力して、さらに詳しい金額を確認しましょう。
STEP6:試算結果を確認
ここまでの情報入力が完了すると、進学にかかる費用の合計や月々の負担額といった試算結果が表示されます。
自己資金で総額を賄えるのか、奨学金はいくら必要なのか、卒業後の月々の奨学金返済負担がどのくらいになるのかといった試算結果を確認しましょう。
試算結果の見方と活用方法
先述した6つのステップで試算結果を確認した後は、その結果を有効活用しながら資金計画を立てましょう。
ここでは、試算結果の見方と活用方法を解説します。
グラフ・表の読み方
グラフは、進学にかかる学費+生活費の総額と、それを賄う自己資金、奨学金等、不足額のバランスを確認するうえで役立ちます。
不足額が0円またはマイナスの場合、あくまでも計画上ではありますが、自己資金と奨学金の組み合わせだけで進学費用を賄うことが可能です。
一方で、不足額が発生している場合は、教育ローンを活用したり、奨学金の金額を増やしたりして、学費を確保する必要があります。
返還シミュレーションの読み方
貸与型奨学金を利用する場合、その総額に基づいた返還シミュレーションが表示されます。
月額返済額は、卒業後毎月返済する最低限の金額です。
返済期間は最長20年間となり、返済期間が長いほど月々の返済額を安く抑えられますが、長期にわたり家計に負担がかかります。
給付奨学金・貸与奨学金のバランスを比較する
試算結果により給付型奨学金を受け取れる可能性があると示された場合は、優先的に給付型奨学金を活用しましょう。
給付型奨学金とは、返済不要の奨学金であり、活用すると返済が必要な貸与型奨学金の借入額を減らせます。
進学先別の資金計画を立てるポイント
進学資金シミュレーターは、進学先などの条件に合わせて複数回利用して、進学先ごとの試算結果をそれぞれ確認しましょう。
たとえば、同じ国公立大学に通う場合も、自宅から通うのか、アパートから通うのかによって、進学資金には大きな違いが生まれます。
国公立と私立大学を併願する場合、私立大学の進学資金も把握しておくことにより、資金計画上の誤算をなくしやすくなるでしょう。
よくある質問(FAQ)
ここでは、進学資金シミュレーターに関するよくある質問4つにお答えします。
Q1:試算結果に表示される金額は確定値ですか?
いいえ、確定値ではありません。
表示される金額は文部科学省の統計に基づく「概算の平均額」であり、奨学金の受給資格も目安です。
実際の学費や奨学金の確定額は、進学先の大学・専門学校、そしてJASSOへの正式な申し込みと審査によって決まります。
Q2:途中で入力をやり直したい場合はどうすれば?
いつでも最初からやり直せます。
進学資金シミュレーターは、利用者の情報をサーバーに保存する仕組みではありません。
そのため、ブラウザを閉じたり、最初に戻るボタンを押したりすれば、何度でも異なる条件で試算できます。
Q3:スマートフォンからも利用できますか?
はい、利用可能です。
JASSO公式サイトの進学資金シミュレーターは、スマートフォンやタブレットからのアクセスにも対応しています。
外出先や移動中でも、気軽に資金計画の試算が可能です。
Q4:データ保存や印刷はできますか?
データ保存機能はありませんが、試算結果の印刷は可能です。
試算結果のページをブラウザの印刷機能で印刷するか、スクリーンショットを撮って保存することをおすすめします。
データを保存することにより、複数の試算結果を比較しやすくなるでしょう。
進学資金シミュレーターの注意点と限界
進学資金シミュレーターは便利なツールですが、あくまでもシミュレーション結果を示すものであり、精度には限界があります。
ここでは、進学資金シミュレーターの注意点を4つ見てみましょう。
シミュレーターはあくまで概算
進学資金シミュレーターが計算できるのは、最新の統計データに基づく全国平均の概算額です。
特に私立大学の学費は、進学先の学校や学部によって大きく変動します。
シミュレーターの概算と実際の学費が数百万円単位で異なる可能性があるため注意しましょう。
大学・専門学校ごとの授業料や寮費差に注意
大学や専門学校ごとに、授業料や寮費には大きな差が生じます。
特に芸術系や医療系など、専門的な学習をする教育機関の授業料は高額になりがちです。
また、都市部などの家賃相場が高い地域では、シミュレーターが提示する平均的な下宿費用と実際の生活費に誤差が生じやすくなります。
返還額は利率や返還期間によって変動する
進学資金シミュレーターで示される月額返済額は、あくまでも概算です。
実際の返還額は、借入時の利率や卒業後の返還期間によって変動します。
また、返済途中に生じる金利の変動によっても返済総額は変わるため、余裕を持った資金計画を立てる必要があります。
正確な金額を把握するには進学先への確認が必要
より正確な資金計画を立てるためには、進学先への確認が必要です。
先述したように、進学資金シミュレーターが表示する金額は平均額に過ぎません。
進学先の入学金や授業料、奨学金の金額、下宿先の正確な家賃相場などを計算に含めて、計算結果の精度を高めましょう。
奨学金や教育ローンと組み合わせて考える
進学資金シミュレーターで資金の不足額が明確になったら、その不足分をどう賄うか、具体的な支援制度と組み合わせて考えましょう。
JASSO奨学金(第一種・第二種)のシミュレーションとの関連
進学資金シミュレーターはJASSOの第一種(無利子)と第二種(有利子)の貸与月額の目安を示します。
借入額は、無利子の第一種を最大限に活用しましょう。
第一種の受給後に不足する金額を第二種で補うことにより、不足分の借入額を抑えられ、将来の返済負担を軽減できます。
給付型奨学金・授業料減免制度の確認ポイント
給付奨学金や授業料減免制度は返済が不要な奨学金・制度であり、最優先で活用すべきです。
シミュレーターで制度を利用できる見込みであることがわかったら、在学中の高校などを通じて正式な申請手続きを進めましょう。
この際の確認ポイントは2点です。
・支援区分が「第一区分」から「第三区分」のどこに該当するか
・授業料の免除額は全額、3分の2、3分の1のうちどれに該当するか
2点を確認することにより、正確な学費を計算できます。
日本政策金融公庫「教育一般貸付」との比較
有利子の奨学金を借りる予定の場合は、教育ローンの利用も検討しましょう。
特に、日本政策金融公庫の「教育一般貸付」は、比較的低金利で利用しやすい教育ローンです。
奨学金の返済は子どもが行いますが、教育ローンは保護者名義で組むため、将来的な子どもの返済負担を軽減できます。
家庭の支出バランスを考慮した現実的な計画づくり
シミュレーターで得たデータを活用して、無理のない現実的な資金計画を立てましょう。
貯金をどのくらい使えるのか、仕送り額が家計を圧迫しないかを計算すると、無理なく子どもを支援できます。
奨学金の返済額は、新卒時の想定月収の10%以内に収まると、無理なく返済できます。
家庭での活用事例【シミュレーターをどう使うか】
進学資金シミュレーターの使い方について、具体的な家庭での活用事例を4つ見てみましょう。
ケース① 国公立大学 自宅通学の場合
このケースでは、私立に比べて学費を安く抑えられるため、総費用も低く見積もられます。
生活費も少ないため、奨学金の借り入れが不要になる場合があるほか、借りるとしても第二種奨学金の少額で済む可能性が高いです。
自己資金で大部分を賄う計画が現実的と言えます。
ケース② 私立文系 下宿生の場合
学費と自宅外生活費が大きく加算され、総費用が大幅に増加します。
不足額が大きくなるため、給付奨学金や第一種奨学金に加え、第二種奨学金や教育ローンの利用を検討せざるを得ないケースが多いです。
ケース③ 専門学校 2年間通学の場合
修業年限が短い分、総費用は大学4年間よりも抑えられますが、専門学校の種類によっては学費が高額になる場合があります。
奨学金の総貸与額は少なくなるため、卒業後の返済期間が短くなりやすいでしょう。
ケース④ 給付奨学金を受ける家庭の資金計画例
給付型奨学金と授業料減免が適用されるため、学費の負担がほぼなくなります。
不足するのは生活費のみとなるため、貸与奨学金は生活費として必要な最低限の額に絞ることができ、将来の返済負担を大幅に軽減する計画が立てられるでしょう。
奨学金バンクによる奨学金返還支援サービスの紹介
進学資金シミュレーターで資金計画を立てても、実際に奨学金を借りた学生にとって、卒業後の返済負担は大きな課題となります。
その課題を解消するために役立つのが、奨学金バンクによる奨学金返還支援サービスです。
ここでは、奨学金バンクについて詳しく解説します。
奨学金バンクとは?
奨学金バンクとは、奨学金返還支援の仕組みを全国の企業と学生に提供する日本初のプラットフォームです。
奨学生の奨学金返済負担を軽減するため、企業による「奨学金返還支援制度(代理返還制度)」の導入と運用をサポートしています。
企業・学生・社会にとってのメリット
制度の活用により、企業は優秀な人材の獲得競争率が向上するほか、社員の定着率向上を実現しやすいでしょう。
学生は月々の返済負担を軽減でき、結婚や出産といったライフイベントに備えやすくなります。
また、若者の可処分所得が増えて消費が活性化され、経済の好循環が促進されることは、社会全体のメリットです。
まとめ
JASSOの進学資金シミュレーターは、進学にかかる費用と、奨学金や自己資金のバランスを明確にできる便利なツールです。
シミュレーターで概算を把握したうえで、借り入れを最小限に抑える現実的な資金計画を立てることが将来の経済的自立への第一歩となります。










