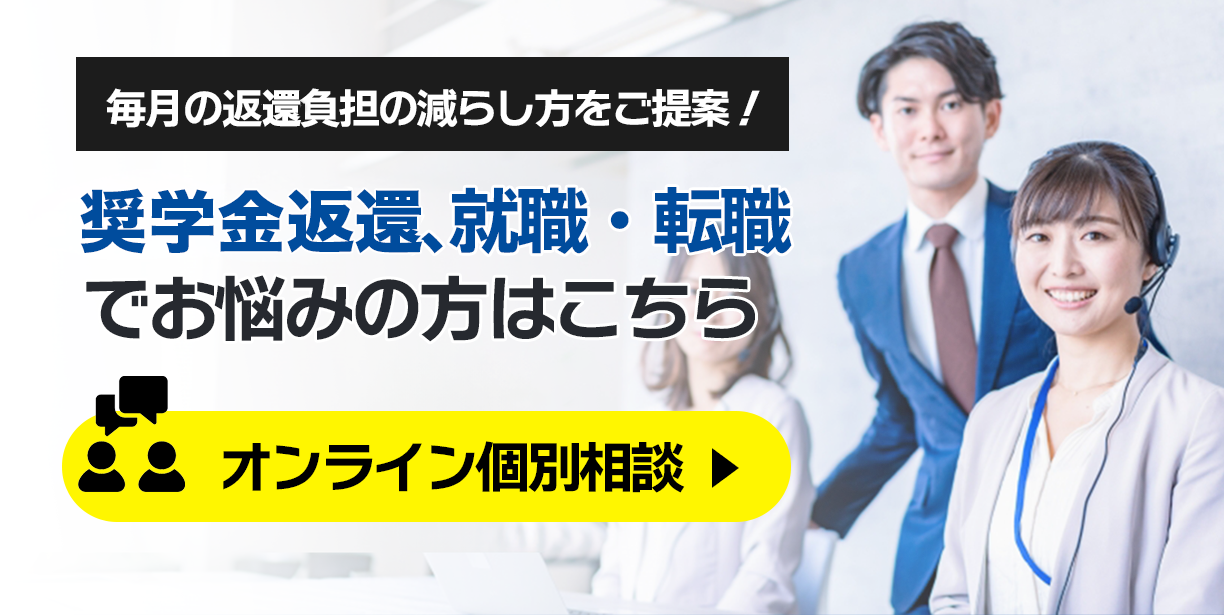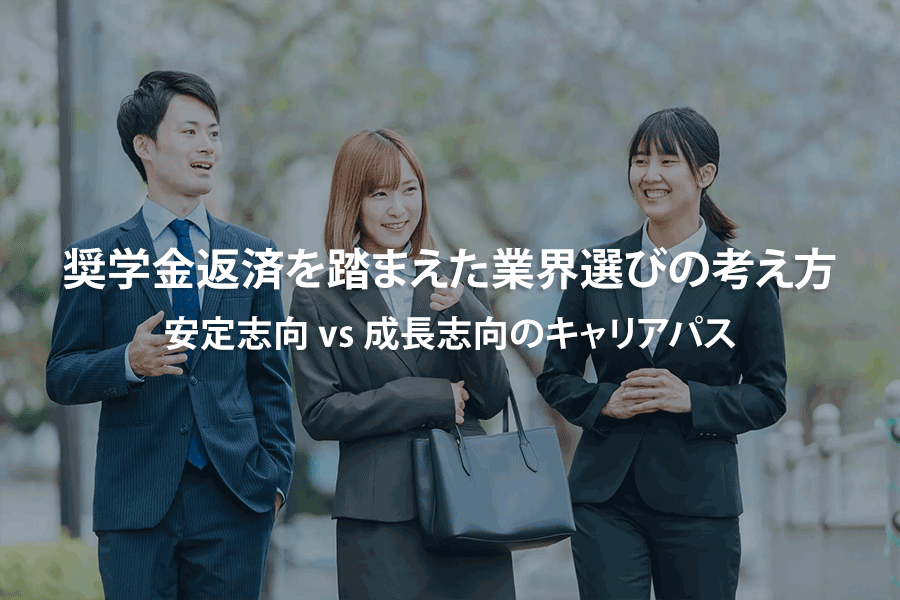
JASSO(日本学生支援機構)によると、学生のうち約半数以上が奨学金を利用しており、就職後は多くの方が奨学金を返済する必要に迫られます。
奨学金返済を念頭に置くと、就職における業界選びにおいて、何を重視すると良いのか迷ってしまいがちです。
この記事では、奨学金返済という現実的な制約を踏まえた上うえで、キャリア設計をより戦略的に行うための考え方をご紹介します。
この記事を読むと、自身が「安定志向」と「成長志向」のどちらを優先して業界選びを行うと良いか見えてくるでしょう。
奨学金返済とキャリア選択の関係
まずは奨学金返済とキャリア選択の関係性について整理します。
奨学金返済の平均額などを整理したうえで、ライフプランに与える影響などを確認しましょう。
奨学金返済の平均額と返還年数
JASSOの公式データ(令和4年度 学生生活調査)によると、奨学金の平均額は第一種のみの利用で230.8万円、第二種のみの利用で308.8万円です。
返還年数の公的なデータはありませんが、第一種の場合は13年~18年、第二種の場合は18年~20年ほどの返還年数になると考えましょう。
第二種奨学金には利息が付くため、たとえ同じ金額を借り入れたとしても、第一種奨学金と比較して返済総額が多くなります。
そのため、月々の返済額を無理のない金額に抑えた場合、第一種奨学金のほうが返還年数が長引きやすいのです。
返済額がライフプランに与える影響
毎月の奨学金返済額は、固定費として必ず支払わなければなりません。
奨学金の返済義務があるために、生活費の切り詰めを余儀なくされたり、自由に使える可処分所得が大きく減少したりするケースが目立ちます。
これにより、「留学や資格取得といった自己投資ができない」「結婚資金や住宅の頭金がなかなか貯まらない」など、経済的な制約により将来の選択肢が狭められてしまいがちです。
現代の日本において、奨学金返済は社会問題の一つとして捉えられています。
「返済があるから安定を選ぶ」という傾向と課題
奨学金返済を一種の負債として考える方が多いため、就職活動においては「安定志向」が強くなる傾向があります。
具体的には、公務員、大企業の事務職、インフラ系企業など、倒産リスクが低く、給与が安定している業界・企業を選ぶ学生が多いです。
しかし、このような選択を余儀なくされたせいで、中には「本当にやりたい仕事ではない」という不満を抱えたり、「収入の伸びが遅く、早期完済が困難になる」といった長期的な課題を抱えたりしながら働く人も少なくありません。
奨学金返済を“キャリア設計の一部”として捉える視点
奨学金返済を単なる負債として捉えるのではなく、「教育という投資を回収するためのコスト」と捉え、キャリア設計に組み込む視点を持つことが重要です。
「奨学金返済をあと何年で終わらせるか」「返済を終えた後にどのような生活を送りたいか」という目標から逆算して、業界選びを戦略的に進めましょう。
中長期的な目標を持ち、それを叶えられる業界選びを行うことが、キャリア設計の初期フェーズとして最も重要なポイントです。
「安定志向」と「成長志向」それぞれの特徴とリスク
就職活動における業界選び・会社選びは、大きく「安定志向」または「成長志向」に分類して進められます。
ここでは、それぞれの特徴とリスクを整理しましょう。
安定志向の定義
安定志向とは、「予測可能性の高さ」と「リスクの低さ」を最も重視するキャリアの選び方です。
たとえば公務員や大企業、インフラ系など、倒産リスクが少ない企業への就職が該当します。
これらの就職先は、景気変動の影響を受けにくいことに加えて、給与体系や評価制度、福利厚生が明確なことが特徴です。
そのため、長期にわたる安定雇用が見込めます。
成長志向の定義
成長志向とは、「市場価値の向上」と「高いリターン」を重視するキャリアの選び方です。
具体的にはIT・Web系企業、コンサルティングファーム、外資系企業、ベンチャー企業・スタートアップ企業への就職が該当します。
これらの業界は、変化のスピードが速く、実力主義・成果主義を取り入れている場合が多いです。
能力に応じて年収が大きく伸びる可能性があることに加えて、短期間でのスキルアップを目指せます。
安定業界のメリットと限界
安定志向で業界選びを行うメリットは、解雇のリスクが低く、福利厚生が充実していることです。
退職金制度が用意されている場合も多く、奨学金返済も計画的に進めやすいでしょう。
しかし、収入が伸び悩みやすいという限界があります。
年功序列の傾向が強いため、若いうちは劇的な昇給が見込めず、奨学金の早期完済が難しくなるでしょう。
また、異業界への転職の際に、専門的なスキルが不足しているとみなされやすく、キャリアアップを図りにくいこともデメリットです。
成長業界の可能性とリスク
成長業界の可能性は、高年収を早期に達成し、奨学金返済を短期間で完了できる可能性が高まる点です。
また、変化の激しい環境で身につけた専門スキルは、自身の市場価値を飛躍的に高め、将来的なキャリアの選択肢を大きく広げます。
一方で、不安定さは成長業界ならではのリスクです。
企業の成長が止まると給与が伸び悩みやすいほか、倒産リスクも孕みます。
また、プロジェクトベースの働き方を導入する企業が多く、厳しい労働環境にさらされるリスクがあることにも注意しなければなりません。
奨学金返済を踏まえた“安定志向”の業界選び
奨学金返済を踏まえて安定志向の業界選びをする場合は、これからご紹介する4つのポイントを意識しながら、業界選び・会社選びを進めましょう。
① 安定した給与・福利厚生が魅力の業界
安定志向で業界選びをする場合は、以下のように安定した給与・福利厚生が魅力の業界を選びましょう。
・国家公務員や地方公務員
・銀行や保険などの大手金融機関
・電力やガスなどのインフラ系企業
・世間的な知名度が高い大手メーカー
これらの企業は倒産リスクが低く、給与が安定し、福利厚生も充実する傾向にあります。
安定的な昇給も見込めるため、奨学金の長期的な返済計画が立てやすいでしょう。
② 住宅補助や奨学金返還支援など福利厚生重視で探す
安定業界を選ぶ場合は、給与の額面だけでなく、福利厚生を重視して会社選びをすることが重要です。
たとえば、住宅補助や社宅制度が充実した企業を選ぶと、固定費の中でも特に負担が大きい家賃を削減できます。
奨学金返還支援制度がある企業を選ぶと、奨学金の返済負担が減り、経済的な安心感がさらに向上します。
③ 長期雇用・昇給制度が明確な企業を選ぶ
長期雇用を前提としており、昇給制度が明確な企業を選ぶことも大切です。
安定業界は年功序列の給与システムを取り入れている場合が多く、特に大きな成果を残せなくても、毎年確実に基本給が上昇します。
そのため、経済的な安心感を得やすく、奨学金返還のプレッシャーを減らせるでしょう。
④ リスクは「収入の伸び悩み」と「転職難易度」
安定業界ならではのリスクは、収入の伸び悩みと転職のしにくさです。
先述したように、安定業界は年功序列を重んじる場合が多く、めざましい成果を残したとしても、若手時代から劇的に給与が上がる可能性は高くありません。
そのため、奨学金の繰上返還がしにくくなります。
また、専門性よりも組織内部の知識や経験が重視される傾向にあるため、将来的な転職活動が不利になる場合があります。
転職を視野に入れる場合は、在職中から専門的な勉強をするなどして、自己研鑽を重ねましょう。
奨学金返済を踏まえた“成長志向”の業界選び
奨学金返済を踏まえて成長志向の業界選びを進める場合は、これからご紹介する4つのポイントを意識しましょう。
① 高年収を狙いやすい業界
成長志向で高収入を狙うならば、IT・Web業界、外資系、コンサルティングファーム、そして総合・専門商社といった業界が有力な候補です。
これらの業界は実力主義を取り入れている場合が多く、新卒の若手社員だとしても、実力に応じて高収入を得やすい環境が整っています。
② スキルアップによる市場価値向上が収入を左右する
成長業界では、年功序列ではなく市場価値が収入を左右します。
特定のプログラミング言語、プロジェクトマネジメント、データ分析など、普遍的な専門スキルを身につけることにより、給与水準の高い企業への転職や独立といったキャリアの選択肢が広がるでしょう。
奨学金返済を終えた後も、常に高い収入を維持できる能力が身につくことが成長業界を選ぶ最大の魅力です。
③ 成長業界は「返済を早期完了」できる可能性も
高年収を早期に実現できれば、毎月の返済額を増やしたり、ボーナスや臨時収入を繰上返還に充てたりして、奨学金の返済を前倒しできる可能性があります。
たとえば、20年の返済期間を15年に短縮すると、5年分の利息をカットでき、返済負担を大幅に軽減できるのです。
④ リスクは「短期離職・収入変動」だが挑戦価値あり
成長志向の業界のリスクは、厳しい労働環境にさらされることや企業の成長が鈍化した際に収入が減る可能性があることです。
また、環境に適応できず短期離職した場合、次の転職活動で不利になる可能性もあります。
しかし、このリスクは、自身の市場価値を高められるというリターンによって相殺されます。
リスク許容度が高い人にとっては、十分に挑戦する価値のあるキャリアパスと言えるでしょう。
「安定志向」と「成長志向」どちらが向いているかを見極める
安定志向と成長志向のどちらで業界選びを行うべきか悩んでいる学生の方は多いでしょう。
そこで、どちらを選ぶべきか見極めるためのポイントをご紹介します。
キャリア志向チェックリスト
自身の価値観や状況を客観的に見極めるために、以下の要素をチェックしてみましょう。
・価値観(安定した毎日を優先する性格か、新しいことにチャレンジする性格か)
・リスク許容度(一時的な低収入や長時間労働を許容できるか)
・ライフプラン(結婚、出産、住宅購入を早期に行う計画があるか)
・理想の返済ペース(無理のない金額の返還を重視するか、繰上返還を希望するか)
安定志向が合う人の特徴
安定志向は、「不確実性を極力避けたい人」や「家庭や私生活を重視し、仕事の時間は一定に保ちたい人」に向いています。
また、奨学金の借入額が大きい場合や、実家暮らしではなく家賃負担が重い場合など、経済的なセーフティネットを最優先する必要がある人にも安定志向が適しているでしょう。
成長志向が合う人の特徴
成長志向は、「自身の能力向上に高い意欲があり、努力を惜しまない人」や「プレッシャーを成長の機会と捉えられる人」に向いています。
また、奨学金をできるだけ早く完済してしたい人や自身の市場価値を最大限に高めたいというキャリア志向を持つ人にも、成長志向が適しているでしょう。
奨学金返済額と生活コストから逆算する選択基準
最も現実的な判断基準は、毎月の手取り収入と奨学金返済額+最低限の生活コストの差額です。
毎月の差額が少なくても、奨学金返還を確実に行いたい場合は、安定志向が適しています。
反対に、初期は差額が少なくても、数年後の大幅な昇給によって差額を開きたい場合は、成長志向が適しています。
奨学金返済を支援する企業・制度を活用する
安定志向・成長志向を問わず、業界選びの際に重視したいのが、奨学金返済を支援する企業を選ぶことです。
その際のポイントを、4つの項目に分けて解説します。
奨学金返還支援制度の仕組み
奨学金返還支援制度は、企業が従業員の代わりに、奨学金返済額の一部または全額をJASSOに直接送金する仕組みです。
企業がJASSOの代理返還制度を利用している場合、支援額が従業員の給与所得として課税されないため、可処分所得が増えやすくなります。
奨学金返済支援を導入する企業が増えている背景
近年、この制度を導入する企業が増えている背景には、人材獲得競争の激化と若年層の経済的負担の増大があります。
奨学金返済の負担は、若者にとって共通の課題であり、現代における社会問題の一つです。
この課題を解消する手段として奨学金返済支援を導入することにより、獲得競争を有利に進め、社員の定着率を向上させようと考える企業が増えています。
奨学金返済を支援してくれる企業の探し方
支援制度を導入する企業は、就職エージェントを利用すると効率的に見つけられます。
企業の採用サイトを見る場合は、福利厚生や手当の項目を細かくチェックしましょう。
「奨学金返還支援制度」や「代理返還制度」といった記載がある場合、支援を受けられる可能性が高いです。
また、後述する「奨学金バンク」を利用する方法も有効です。
福利厚生の確認方法と質問例
面接や説明会で制度の有無を質問する場合は「社員の経済的な負担を軽減する制度はありますか?」と尋ねましょう。
支援制度がある場合、新卒者も対象となるか、支援額に上限はあるかなどのポイントを確認してください。
奨学金バンクとは?日本初の奨学金返還支援プラットフォーム
奨学金バンクとは、奨学金返済を控える学生などの求職者と支援制度を導入する企業の橋渡し役とも言えるプラットフォームです。
ここでは、奨学金バンクの取り組みをご紹介します。
奨学金返還型人材紹介サービス
奨学金バンクは、奨学金返還支援制度を導入している企業と奨学金返済を控える求職者をマッチングさせるプラットフォームです。
求職者が奨学金バンクを利用すると、支援制度を導入する企業を効率良く見つけられるほか、諸条件がマッチする企業への応募をスムーズに進められます。
奨学金返還支援サービス
JASSOの代理返還手続きを導入する意思を持つ企業に向けて、導入・運用に向けた行政鉄付やシステム連携を代行するサービスを行うことも、奨学金バンクの特徴です。
これにより、企業は煩雑な手続きを省いて制度を導入できます。
サステナ支援サービス
奨学金バンクは、単なる福利厚生の一環として奨学金制度を支援しているわけではありません。
SDGsの達成など、社会的な課題解決に貢献するための手段として奨学金支援制度を位置付けており、企業のブランドイメージ向上をサポートしています。
奨学金返済を「社会全体で支える」仕組みづくり
奨学金バンクの活動は、奨学金返済を個人の問題に留めず、「若者の未来への投資を社会全体で支える」という新たな仕組みを構築することを目指しています。
若者が自力では解消できない社会問題にメスを入れ、すべての人が快適に働ける社会を作ることが奨学金バンクの目標です。
奨学金返済とキャリアを両立させる戦略的思考
この記事の最後に、奨学金返済とキャリアを両立させる戦略的思考を4つのポイントから解説します。
返済シミュレーションで必要な収入ラインを把握
まずは返済シミュレーションを行い、奨学金返済を無理なく続けつつ、快適な生活を維持できる収入ラインを把握しましょう。
JASSO公式サイトのシミュレーションツールを活用しながら、最低限必要な手取りを明確にして、そのラインを上回る条件を提示する企業に就職することが重要です。
スキル×業界のかけ合わせで将来の選択肢を広げる
「安定」と「成長」のどちらを選んだとしても、自身のスキルを常に磨きましょう。
安定業界に就職しても、専門性が高いスキルを習得しておけば将来的に成長業界への転職を目指しやすくなります。
これにより、将来の選択肢を広げやすくなるのです。
「安定」も「成長」も両立するハイブリッド型キャリアとは
一つの企業で一生を終える時代は終わりを告げています。
初期は安定志向の企業で基盤を固め、資金に余裕ができた5年~10年後に、自身のスキルを活かして成長志向の企業へ転職する「ハイブリッド型キャリア」の構築も検討しましょう。
奨学金返済をきっかけに“自分の価値観”を見直す
奨学金の返済は、自分自身の価値観を見直す絶好のチャンスです。
安定した生活を重視するのか、高収入を目指して猛烈に働くのかを自分に問いかけることにより、自分自身が本当に目指したいキャリアパスが明確になります。
奨学金返済という義務を果たすだけでなく、完済後にどのような人生を送りたいのかという視点を持つことにより、後悔のない業界選びができるでしょう。
まとめ
奨学金返済を抱える若者にとって、業界選びは「安定志向」と「成長志向」の二者択一となりがちです。
それぞれにメリットとリスクがあるため、自身の価値観にどちらが合うのかを検討しましょう。
また、将来の転職を前提とした「ハイブリッド型キャリア」の構築も選択肢の一つです。