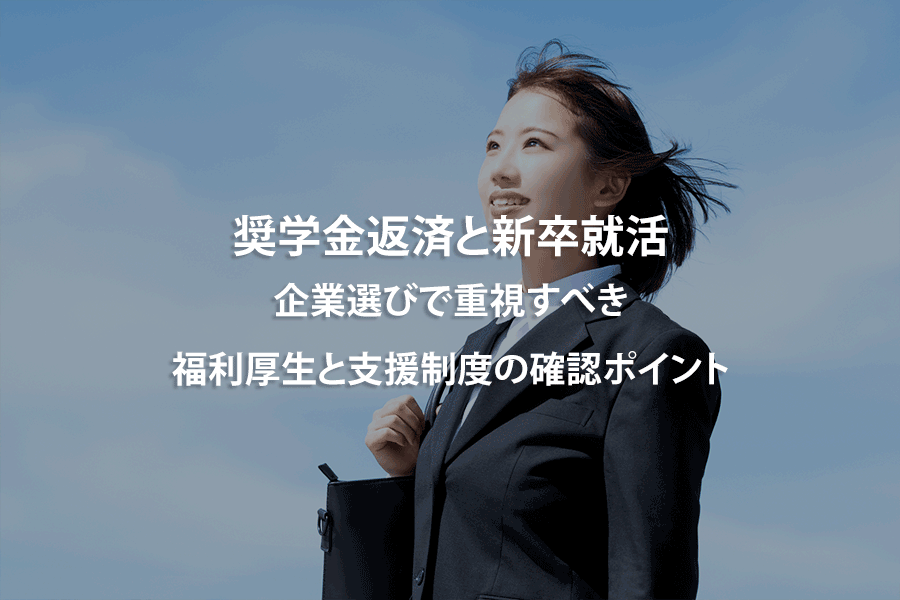
新社会人としての第一歩を踏み出す方にとって、避けられない課題となるのが奨学金の返済です。
多くの学生が奨学金を利用していますが、近年の物価高により教育費や生活費が増えており、就職後の奨学金返済に不安を抱えている方は多いでしょう。
この記事では、目前に迫った奨学金返済という現実を見据えて、新卒就活生が企業選びで重視すべきポイントを解説します。
長期的に安心してキャリアを築ける企業を選ぶためのチェックポイントを見てみましょう。
新卒就活における奨学金返済の現実
まずは、新卒就活における奨学金返済の現実を見てみましょう。
JASSO(日本学生支援機構)の統計をもとに、平均的な返済額や返済期間などをご紹介し、それに伴う負担の実態をお伝えします。
奨学金を利用している学生の割合
日本学生支援機構の「令和4年度 学生生活調査」によると、大学(昼間部)で55.0%、短期大学(昼間部)で61.5%、大学院修士課程で51.0%、博士課程で58.9%の学生が奨学金を利用しています。
多くの学生にとって、奨学金は学費を工面するために欠かせないものです。
平均返済額と返済期間の目安
日本学生支援機構の「令和4年度 学生生活調査」によると、奨学金の平均返済額は第一種のみで約230.8万円、第二種のみで308.8万円です。
第二種は有利子のため、返済額が増える傾向にあります。
なお、平均的な返済期間については、公的な資料による明確なエビデンスが示されていません。
そのため、目安となりますが、第一種は13年~18年程度、第二種は18年~20年程度が、無理なく返還できる平均的な返済期間となるでしょう。
初任給とのバランスから見る返済負担の実態
一般的な企業の初任給を見ると、社会保険料・税金を差し引いた後の手取り額では、奨学金の返済と一人暮らしの生活費を両立させるのが難しい水準です。
無理なく奨学金を返済するためには、月々の返済額を手取り月収の10%以下に抑える必要があるとされています。
「返済が不安」で就職先を選ぶ学生が増えている背景
このような厳しい経済状況と長期にわたる返済義務から、「自分のやりたい仕事」よりも「安定して返済できる仕事」を優先して就職先を選ぶ学生が増えています。
これは、学生が自身の将来的な可能性を経済的なプレッシャーによって制限せざるを得ないという、社会的な課題を浮き彫りにするものです。
奨学金返済を見据えた企業選びが重要な理由
新卒就活における企業選びでは、奨学金返済を見据えて計画を立てることが重要です。
その理由について、4つのポイントに分けて解説します。
給与だけでは測れない「手取りの実態」
求人票に記載されている「月給」や「年収」は、社会保険料や税金が引かれる前の額面です。
実際に使える手取り額は、額面の75%~80%程度になると考えましょう。
額面給与が高くても、福利厚生が乏しく、社会保険料の自己負担が大きい企業では、金銭的なゆとりが持ちにくくなります。
企業による返還支援や住宅補助が長期的負担を軽減
企業が提供する奨学金返還支援制度や住宅手当などの福利厚生は、可処分所得を直接的に増やす有効な施策です。
特に奨学金返還支援制度は、給与とは別に企業が奨学金返済をサポートする制度であり、経済的な安心感を得やすくなります。
返済と生活費の両立を支える「安定した福利厚生」
奨学金返済を抱えながら、趣味や自己投資、貯蓄といった費用を捻出するためには、給与以外の手厚い福利厚生が不可欠です。
たとえば、住宅手当や社員食堂、資格取得支援制度などにより、生活費を直接的・間接的にサポートしてくれる福利厚生があると、月々の固定費を抑えやすくなります。
「奨学金返済×キャリア形成」を両立できる企業とは
奨学金返済を抱える新卒にとって理想的な企業は、単に給与が高いだけでなく、経済的な支援と長期的なキャリア成長の機会を同時に提供する企業です。
奨学金返済の不安を解消しつつ、スキルアップや昇給を通じて、奨学金の早期完済を目指せる企業を選ぶことが重要です。
新卒が注目すべき福利厚生・支援制度5選
新卒就活において注目すると良い福利厚生・支援制度が5つあります。
それぞれの特徴を見てみましょう。
① 奨学金返還支援制度
奨学金返還支援制度とは、企業が従業員の奨学金返済の一部または全額を代理で支払う制度です。
特に、JASSOの代理返還制度を利用している場合、支援額が非課税となるケースがあり、可処分所得を増やしやすくなります。
② 住宅手当・家賃補助
住居費は、固定費の中でも特に大きな割合を占めるものです。
住宅手当や家賃補助、または社員寮の制度が充実している企業は、毎月の支出を抑えやすく、奨学金返済に充てられる金額を増やせます。
特に、家賃が高い都市部で一人暮らしをする新卒の方は、重視すべき福利厚生です。
③ 通信教育・資格取得支援
奨学金返済を早期に終わらせるためには、自身の市場価値を高めて昇給することが不可欠です。
資格取得支援や通信教育制度など、自己啓発を支援する制度が充実している企業を選びましょう。
在職中のスキルアップにより、数年後の昇給や、キャリアアップを前提とした転職を実現しやすくなります。
④ 財形貯蓄・社内積立制度
毎月の給与から自動的に貯蓄ができる財形貯蓄制度や社内積立制度は、計画的な資金管理に役立ちます。
これにより、将来的な繰上返還のための資金を無理なく貯蓄でき、奨学金の早期完済を実現しやすくなるでしょう。
⑤ メンタルヘルス・カウンセリング制度
多額の奨学金返済は、新卒社員にとって大きな心理的ストレスとなることがあります。
メンタルヘルス・カウンセリング制度が整備されている企業は、社員の心身の健康を重視している可能性が高いです。
これらの制度を利用すると、経済的な不安やストレスを抱えた場合、必要なタイミングで専門家に相談できます。
奨学金返還支援制度とは?【JASSO代理返還制度の仕組み】
ここでは、奨学金返還支援制度とは何か、JASSOによる代理返還制度の仕組みを解説します。
奨学金代理返還制度の概要
奨学金代理返還制度は、JASSO(日本学生支援機構)提供する支援制度です。
これは、企業が従業員の代わりに、奨学金返還金の一部または全額をJASSOに直接送金する仕組みです。
これにより、従業員は返済負担を軽減でき、企業側は若手採用を有利に進められます。
企業が従業員の奨学金返還を代行する仕組み
制度を導入する企業は、まずJASSOと「奨学金返還支援企業」としての協定を結びます。
その後、支援対象の従業員と支援額について合意した後、企業は毎月その合意額をJASSOに直接送金するのが基本的な仕組みです。
直接返還により、税制上の優遇措置を適用できます。
企業にとってのメリット
企業にとってのメリットは、優秀な新卒社員を獲得しやすくなるほか、従業員の定着率を高められることです。
また、SDGsにおける目標4「質の高い教育をみんなに」を直接的に実現する福利厚生であるため、企業のブランディングにも役立ちます。
従業員にとってのメリット
従業員にとってのメリットは、実質的な手取りが増加することです。
代理返還制度の場合、手当として奨学金返済額が支給されるケースとは異なり、企業が負担する金額は課税対象になりません。
このため、可処分所得が増えやすく、金銭的な安心感も得やすいです。
実際に奨学金返還支援を導入している企業の例
ここでは、実際に奨学金返還支援制度を導入している企業の実例をご紹介します。
地方自治体・公務員系
地方自治体では、特定の地域に定着することを条件に奨学金返還支援制度を実施するケースがあります。
医師や看護師、教員など、特定の職種への就業支援を含むケースも多いです。
移住を視野に入れている場合は、文部科学省の地方創生枠などを確認し、制度を導入する自治体を探すと良いでしょう。
民間企業による支援事例
民間企業にも支援事例が多数あります。
たとえば、「パーソナルクロステクノロジー」では、2024年度以降の新卒者を対象とする制度を導入しており、総額300万円までの奨学金返済を肩代わりしています。
「大東建託株式会社」や「株式会社リンクアンドモチベーション」でもすでに制度を導入済みです。
企業が支援制度を導入する理由
企業が奨学金返還支援制度を導入する背景には、主に以下の3つの戦略的な理由があります。
・採用力の強化
・従業員エンゲージメントの向上
・企業のブランディング
優秀な学生は複数の内定を得るため、奨学金支援制度は他社との差別化を図り、採用力を強化するうえで有効です。
従業員エンゲージメントも向上し、定着率の低下を防ぎやすくなるでしょう。
また、SDGsに貢献し、ブランディングに役立つことも制度を導入する企業が多い理由の一つです。
支援金額や条件の具体例
奨学金支援制度による支援金額や条件は企業によって異なります。
支援金額には年間・月間の上限が設けられる場合が多く、一般的には月額1万円~3万円が上限となるケースが多いです。
対象期間は「入社から5年間」「最長10年間」などに設定されます。
また、支援対象者も「新卒のみ」などに限定される場合があります。
奨学金返済に強い企業を見つけるための就活チェックリスト
奨学金返済に強い企業の見つけ方を、4つのポイントに分けてご紹介します。
求人票・採用サイトで確認すべき項目
求人票や採用サイトでは、「福利厚生」「手当」「諸制度」の欄を細かくチェックしましょう。
「奨学金返還支援制度」の有無はもちろんのこと、「住宅手当」「寮制度」「資格取得支援」「財形貯蓄」などの制度が具体的に記載されているかを確認します。
面接や説明会で質問して良いポイント
求人票などで制度の詳細を確認できない場合は、面接や説明会で質問しましょう。
この場合は「御社の福利厚生の中で、社員の生活を支えるための制度があれば教えてください」といった尋ね方をすると、失礼にはあたりません。
「奨学金返還支援」はどのように表記されているか
制度の名称は統一されておらず、「奨学金返還支援制度」「奨学金補助制度」「リスタート支援制度」など、企業独自の名称で記載されている場合があります。
具体的な制度名が見当たらない場合でも、福利厚生の内容を細かく確認することが重要です。
支援制度が明示されていない場合の見極め方
支援制度が明示されていない場合は、平均勤続年数や離職率の低さ、社員の平均年齢、教育制度の充実度などを確認しましょう。
これらの条件が優れている場合は、社員を大切にする企業体質であると判断でき、新卒就活の企業選びで失敗しにくくなります。
「給与の高さ」より「返済のしやすさ」で企業を比較する視点
ここでは、給与の高さよりも「返済のしやすさ」の視点で新卒就活を進める際のポイントを4つご紹介します。
手取り額から見る“返済可能ライン”の考え方
新卒社員が奨学金の返済可能ラインを考える場合は、手取りから奨学金返済額を引いた額が、生活費を賄える水準にあるかを確認しましょう。
返済可能ラインを明確にし、そのラインを上回る企業を選ぶことが重要です。
奨学金返済+生活費のシミュレーション方法
内定先の初任給がわかった段階で、奨学金返済と生活費をシミュレーションしましょう。
額面給与に0.75~0.80を掛けて手取り額の概算を割り出し、そこから奨学金返済額と想定される生活費を差し引きます。
ボーナス・福利厚生・支援金を含めたトータル年収で判断
シミュレーションには、ボーナスや福利厚生、支援金といった要素も忘れずに含めてください。
トータルの年収同士で比較検討すると、可処分所得が多い就職先が見つかります。
「短期的な給与」より「長期的な支援制度」を優先する理由
奨学金の返済期間は15年~20年と長期にわたります。
そのため、入社後1~2年の短期的な給与の高さよりも、長期間にわたって安定した生活を支えてくれる福利厚生や支援制度を優先することが重要です。
長期的な支援制度がある企業に就職すると、トータルの経済的負担を軽減でき、ゆとりを持った生活を送りやすくなります。
奨学金バンクとは?日本初の奨学金返還支援プラットフォーム
奨学金バンクとは、奨学金支援制度を活用して学生・社会人・企業をサポートする、日本初のプラットフォームです。
ここでは、奨学金バンクの特徴をご紹介します。
奨学金返還型人材紹介サービス
奨学金バンクは、奨学金返還支援制度を導入している企業と返済負担を抱える新卒を含む求職者を結びつける、日本初の専門プラットフォームです。
新卒就活生は、経済的な不安を解消できる企業を効率的に見つけられるため、安心してキャリアをスタートさせられます。
奨学金返還支援サービス
奨学金バンクは、企業がJASSO等の代理返還制度をスムーズに導入・運用できるよう、制度設計から手続き代行までを包括的にサポートしています。
これにより、多くの企業が制度を導入しやすくなり、奨学金返済を抱える学生の負担軽減を実現しているのです。
サステナ支援サービス
奨学金バンクは、企業による奨学金支援を「若者への投資や社会貢献」として捉えており、企業のSDGs達成やブランドイメージ向上につながるよう支援しています。
経済的課題を解決する企業の姿勢は、特に若い世代からの共感を集め、企業の価値を高めるでしょう。
奨学金バンクが目指す社会
奨学金バンクが目指すのは、奨学金の返済負担がキャリア選択の足かせとならない社会です。
奨学金利用者である新卒就活生が、経済的な不安に縛られることなく、自身の適性や目標に基づいて企業を選び、才能を最大限に発揮できる環境の創出を目指しています。
奨学金返済とキャリア形成を両立させる3つのステップ
この記事の最後に、奨学金返済とキャリア形成を両立させるステップを3段階でご紹介します。
① 返済計画を立てて「必要な収入ライン」を明確にする
奨学金の総額から、毎月の返済額を明確にして、そこから逆算して「生活に必要な最低限の手取り収入」と「余裕のある生活を送るための理想的な手取り収入」の収入ラインを設定します。
このラインを上回る企業を選ぶことにより、金銭的な不安を抱えるリスクを抑えられるでしょう。
② 奨学金返還支援制度のある企業を優先的に検討する
設定した収入ラインを満たす企業の中から、奨学金返還支援制度を導入している企業を優先的に検討します。
支援制度のある企業は、社員の生活を重視する企業である可能性が高いです。
そのため、長期的に安心して働きやすい環境が手に入るでしょう。
③ 福利厚生・ライフプランのバランスで最終判断する
最終的な企業選択は、給与や支援額だけでなく、住宅手当、昇給制度、社員教育制度などの福利厚生と5年後・10年後のライフプランとのバランスで決定します。
奨学金返済を機に、自身のキャリアを長期的な視点で捉え、安定した経済基盤のうえで成長できる企業を選びましょう。
まとめ
新卒就活では、就職後の奨学金返済も念頭に置き、就職する企業を厳選する必要があります。
求人票の給与額に惑わされすぎず、奨学金返還支援制度や福利厚生の充実度から就職先を選びましょう。
奨学金バンクを利用すると、理想的な企業を効率よく見つけられます。










