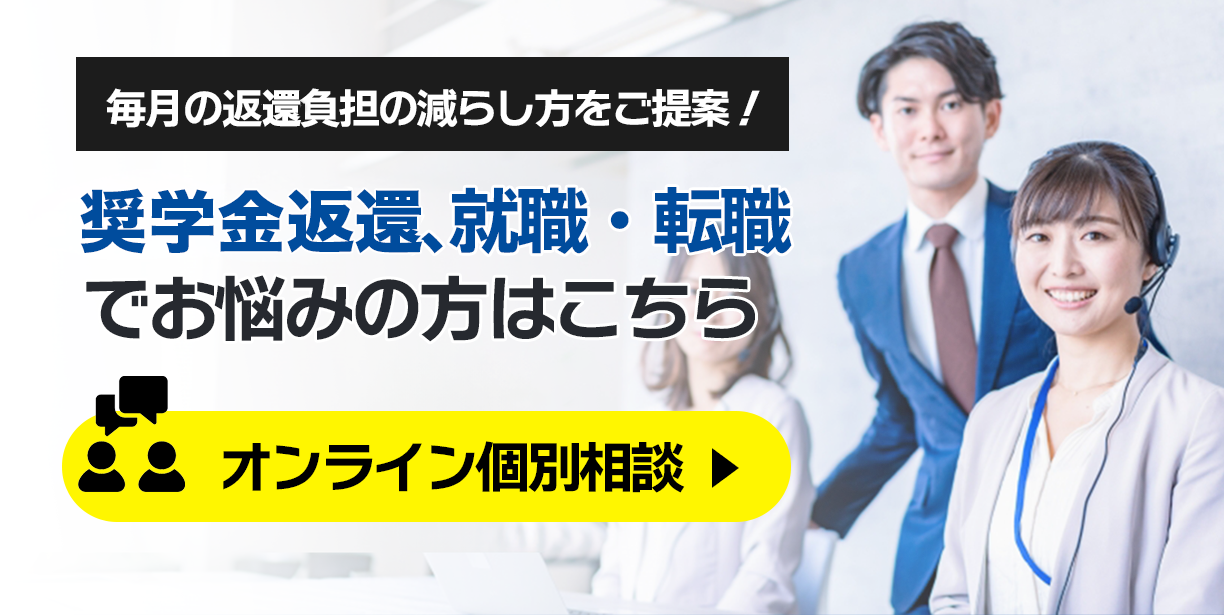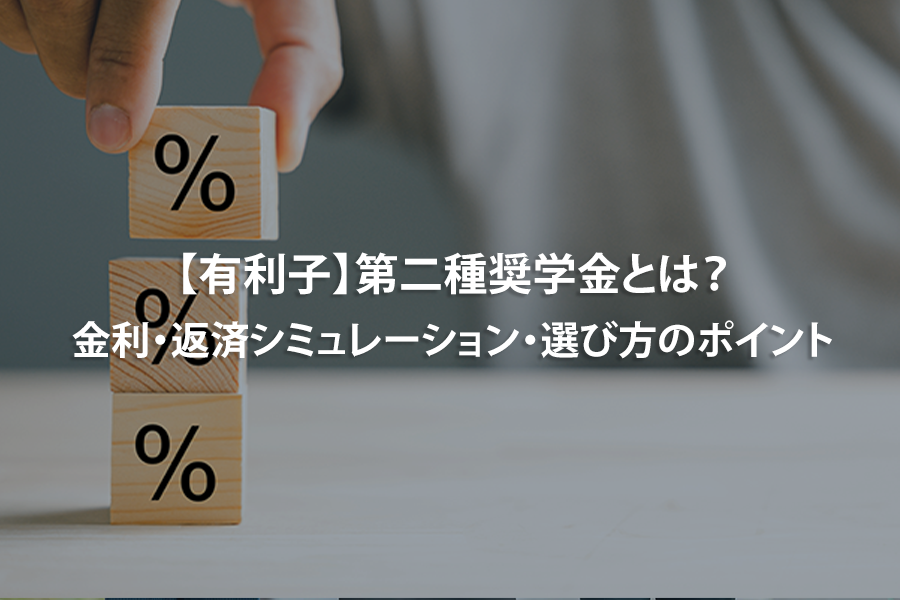
大学進学を考えているものの、学費の負担が不安で奨学金の利用を検討している方も多いのではないでしょうか。
奨学金には種類があり、その中でも 第二種奨学金 は比較的借りやすいと言われています。
本記事では、第二種奨学金の 特徴・金利・申込方法 について詳しく解説します。
また、計画的な返済方法や選び方のポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
第二種奨学金の基本を理解しよう
奨学金には 第一種奨学金(無利子) と 第二種奨学金(有利子) があります。
それぞれの違いを理解し、適切な選択をしましょう。
第二種奨学金とは?第一種との違いと特徴
第二種奨学金 は、日本学生支援機構(JASSO)が提供する 有利子の貸与型奨学金 です。
第一種奨学金(無利子) との主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 第一種奨学金(無利子) | 第二種奨学金(有利子) |
|---|---|---|
| 金利 | なし | あり(年3%上限) |
| 審査基準 | 厳しい(成績3.5以上) | 緩め(平均水準以上) |
| 貸与金額 | 制限あり | 選択肢が多い |
| 併用可否 | 可能 | 可能 |
第二種奨学金のメリット
- 第一種奨学金よりも審査基準が緩い
- 選べる貸与額の幅が広い
- 第一種奨学金と併用できる
デメリット
- 金利がかかるため、返済総額が増える
- 固定金利 or 変動金利を選択する必要がある
もし 第一種奨学金だけでは学費が足りない場合、第二種奨学金との併用も可能です。
ただし、 両方の条件を満たす必要がある ため、申請時に注意しましょう。
金利がかかるとは?金利の仕組みを解説
金利 とは、借りたお金(元金)に対して発生する 利息 のことです。
金利の種類には 固定方式 と 見直し方式(変動) があります。
第二種奨学金の金利の仕組み
- 固定方式 :借入時に決まった金利が返済完了まで変わらない
- 見直し方式 :約5年ごとに金利が変動(市場金利に影響される)
現在の金利(2025年の見通し)
2025年時点では、政策金利が0.5%に引き上げられた影響で、奨学金の金利も上昇する可能性があります。
金利が高くなると、返済額も増えるため、金利タイプの選択は慎重に行いましょう。
金利による返済額の違い(例)
| 借入額 | 固定金利1% | 固定金利3% |
|---|---|---|
| 300万円(15年返済) | 約3,500円/月 | 約4,200円/月 |
| 500万円(15年返済) | 約5,800円/月 | 約6,900円/月 |
金利が上がるほど、毎月の返済負担が大きくなる点に注意してください。
第二種奨学金の対象者と申込条件
第二種奨学金を利用できる人 は、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
どのような人が対象か?
- 高校の成績が平均水準以上
- 特定の分野に優れた資質がある
- 学習意欲があり、学業を修了できる見込みがある
第一種奨学金(無利子)は 評定平均3.5以上 という基準がありますが、
第二種奨学金には 具体的な評定基準はなく、比較的緩やか に設定されています。
申込条件と注意点
- 3つの条件のうち、いずれか1つを満たせばOK
- 第一種奨学金と併用可能
- 貸与開始は入学後の5月以降
- ※入学金や前期授業料には間に合わないため、別途準備が必要
入学金や前期の学費を賄いたい場合は、 教育ローンやその他の奨学金と組み合わせる 方法を検討しましょう。
第二種奨学金の金利と返済方法
第二種奨学金を利用する際に気になるのが 金利の仕組み や 返済方法 です。
ここでは、 金利の種類・返済計画の立て方・シミュレーションの活用方法 について詳しく解説します。
金利はどのくらい?有利子のメリットとデメリット
第二種奨学金では、年3%を上限とする利子 が発生します。
金利の種類には 固定方式 と 見直し方式(変動) があります。
金利の仕組み
| 金利方式 | 特徴 |
|---|---|
| 固定金利 | 借入時に決まった金利が返済完了まで変わらない |
| 見直し金利(変動金利) | おおむね5年ごとに金利が見直される |
有利子のメリット
第一種奨学金より審査基準が緩く、借りやすい
貸与金額の選択肢が広く、学費に合わせて調整可能
有利子のデメリット
長期間返済すると、金利分の負担が増える
金利の変動によって、返済額が増える可能性がある(変動金利の場合)
現在の金利(2025年)と今後の見通し
2025年時点では、政策金利が 0.5% に引き上げられた影響で、
奨学金の金利も上昇する可能性 があります。
金利が 1%台 であれば比較的負担は少ないですが、
3%近くまで上昇すると返済額が大幅に増加する ため、注意が必要です。
金利による返済額の違い(例)
| 借入額 | 固定金利1% | 固定金利3% |
|---|---|---|
| 300万円(15年返済) | 約3,500円/月 | 約4,200円/月 |
| 500万円(15年返済) | 約5,800円/月 | 約6,900円/月 |
金利が上昇すると、毎月の返済負担が増えるため、
固定金利 or 変動金利の選択は慎重に行いましょう。
返済方法の詳細
第二種奨学金は 貸与型奨学金 であるため、返済義務があります。
ここでは、返済開始のタイミング・返済期間・計画的な返済のコツ を解説します。
返済開始タイミングと返済方法
- 返済開始 : 卒業後7か月目から
- 返済方法 : 口座振替(引き落とし手数料無料)
- 返済期間 : 最大20年
- 延滞リスク : 病気・失業時には 減額返還制度 や 返還期限猶予制度 を利用可能
返済期間の選び方|長期 vs 短期
| 返済期間 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 短期(5〜10年) | 利息の負担が少なく、総返済額が少なく済む | 毎月の返済額が高くなる |
| 長期(15〜20年) | 毎月の負担を軽減できる | 返済総額が増える(利息が増加) |
返済計画の立て方|シミュレーションを活用しよう
返済額を計算するには 奨学金貸与・返還シミュレーション を活用すると便利です。
シミュレーション活用の流れ
- 借入予定額を入力
- 希望する返済期間を選択
- 固定金利 or 変動金利を選ぶ
- 毎月の返済額と総返済額を確認
日本学生支援機構(JASSO)の公式サイトで提供されている
「奨学金貸与・返還シミュレーション」を使えば、
具体的な毎月の返済額が簡単に分かります。
第二種奨学金を申し込むためのステップ
第二種奨学金を申し込む際には、必要な書類の準備・審査基準の理解・申込期限の確認 などが重要です。
ここでは、申し込みの流れやスムーズに手続きを進めるポイントを解説します。
申し込みの流れと必要書類
申し込み前に準備すべき書類と確認方法
第二種奨学金の申し込みには 複数の書類 が必要です。
書類の不備があると審査に遅れが生じるため、事前にしっかり確認しましょう。
【全員が提出必須の書類】
提出書類一覧表
申込書(スカラネットで入力)
確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書
申込に係る重要事項確認書
奨学金振込口座届(貸与決定後に提出)
在籍証明書・成績証明書(学校から発行)
【該当者のみ提出が必要な書類】
海外居住者のための収入申告書
年収等の実績計算書(自営業者の場合)
その他、家庭の状況に応じた証明書類
書類の確認方法 日本学生支援機構(JASSO)の公式サイトには、最新の申込書類一覧 が掲載されています。
申し込み前に必ずチェックし、不備がないよう準備を進めましょう。
申し込み時の注意点
書類の不備がないか複数回チェックする
期限内にすべての書類を提出する(提出先:学校 or JASSO)
マイナンバーの提出が必要な場合があるため、事前に確認
スカラネットでのオンライン申込後に受付番号を必ずメモしておく
審査基準と選考のポイント
申請時にチェックされる重要項目
第二種奨学金の審査では、家計状況・学力・信用情報 の3つが重要視されます。
【審査基準】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 家計状況 | 世帯年収・家族構成・生活費を考慮 |
| 学力基準 | 学校での成績が平均以上であること |
| 信用情報 | 連帯保証人や親の信用状況が影響することも |
特に、家計の状況が厳しい家庭は審査で優先される傾向があります。
審査に落ちる場合の原因と改善策
審査に落ちる主な理由として、「学力不足」「家計基準を超えている」「信用情報に問題がある」 などが挙げられます。
【審査落ちの原因と改善策】
| 落選理由 | 改善策 |
|---|---|
| 成績が基準以下 | 学習計画を立てて成績を向上させる |
| 世帯年収が基準より高い | 他の奨学金制度を検討する |
| 連帯保証人の信用問題 | 他の保証制度を利用する(機関保証制度) |
他団体の奨学金(地方自治体・企業奨学金など)を活用する
新聞奨学生制度を利用し、働きながら学費を確保する
申し込むタイミングとスケジュール
第二種奨学金は、年2回の募集があるため、適切なタイミングで申し込むことが重要 です。
いつ申し込むのが最適か?申込期限とスケジュール
2024年度の申し込みスケジュール(例)
| 募集回 | 申込受付期間 | 期限 |
|---|---|---|
| 第1回 | 4月下旬〜5月上旬 | 5月10日必着 |
| 第2回 | 6月上旬〜6月下旬 | 6月10日必着 |
申し込みの流れ
- 学校から第二種奨学金の申込書類を受け取る
- 必要書類を準備する(成績証明書・家計証明など)
- スカラネットでオンライン申請を行う
- 期限内に書類を学校 or JASSOに提出する
- 審査結果の通知を待つ(通常2ヶ月程度)
留学予定の学生は、前年度の7月頃から申し込みが可能 です。
最新の申込スケジュールは JASSO公式サイトで確認 しましょう。
第二種奨学金の返済を計画的に行う方法
第二種奨学金は、元金だけでなく利息も発生するため、計画的な返済が不可欠 です。
ここでは、金利負担を軽減する繰上返済・返済猶予制度・減額返還制度 の活用方法を解説します。
金利の負担を軽減するための繰上返済
繰上返済を活用すると、支払総額を減らし、早期完済を目指せる ため、金利の負担を軽減できます。
ただし、デメリットや注意点もあるため、慎重に判断しましょう。
繰上返済のメリットとデメリット
【繰上返済のメリット】
利息の総支払額を減らせる(利息は返済期間が長いほど増えるため)
借金のプレッシャーから早く解放される
長期の経済的リスク(失業・病気など)を軽減できる
【繰上返済のデメリット】
貯蓄が一時的に減る(急な出費に対応しづらくなる)
利息が低い場合、繰上返済の効果が少ない
一部の奨学金では繰上返済できないケースもある(契約内容を要確認)
返済の早期完了を目指す方法と注意点
貯蓄を増やし、余裕資金で繰上返済を行う
日々の生活費を見直し、節約して貯蓄を増やすことで、無理なく繰上返済を実現できます。
また、学業と両立できる範囲でアルバイトをするのも有効です。
繰上返済のタイミングを見極める
金利が低いうちは無理に繰上返済せず、将来のために貯蓄を優先するのも選択肢 です。
返済負担を軽減するための「返済猶予」制度の活用
収入が減少したり、就業が安定しない場合には、返済猶予制度を活用して負担を軽減 できます。
所得が低い場合や就業不安定な場合の活用方法
【こんな状況のときに利用できる】
卒業後、就職先が見つからず収入がない
非正規雇用・パート・アルバイトで安定収入がない
病気・ケガ・介護・育児などで収入が減った
このような場合、一定期間返済を一時的にストップ できるため、生活を安定させてから再開できます。
返済猶予の条件と申請方法
【返済猶予の基本情報】
- 最長10年間まで申請可能
- 災害・病気・産休・育休などの特別な事情がある場合、10年以上の猶予も可能
【申請方法】
スカラネット・パーソナル(オンライン)で申請
必要書類(所得証明書など)を提出
審査結果を待つ(通常1~2ヶ月)
⚠ 返済猶予を希望する場合、早めに申請が必要です!
返済を延滞してしまうと、申請が受理されないこともあるため、早めに相談・手続きを進めましょう。
減額返還制度で支払負担を減らす方法
収入が少なく、通常の返済額を支払うのが難しい場合 は、「減額返還制度」を活用すると、毎月の負担を軽減できます。
減額返還を受けるための要件
【減額返還の特徴】
毎月の返済額を最大で半分に減額できる
最長15年間、返済期間を延長できる
申請すれば、再度適用も可能
【利用できる主な条件】
病気・ケガで収入が減った
リストラや転職で収入が減少
家庭の経済状況が急変
申請は「スカラネット・パーソナル」で可能 です。
審査には住民税非課税証明書や所得証明書 などの書類が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
自分に合った返済計画を見つける方法
返済が計画通りに進まず困った場合は、日本学生支援機構(JASSO)に相談 しましょう。
専門スタッフが相談に応じ、適切な返済方法を提案してくれます。
【返済計画を立てるポイント】
スカラネット・パーソナルで「返済シミュレーション」を活用する
収入に合わせた適切な返済額を設定する
繰上返済・猶予・減額返還などを活用し、無理のない計画を立てる
第二種奨学金を選ぶ際のポイント
第二種奨学金を利用するかどうかは、将来の返済負担にも影響します。
ここでは、どんな人に向いているのか、他の奨学金との組み合わせ方 について解説します。
第二種奨学金が向いている人とは?
第二種奨学金は有利子であるため、慎重に検討することが重要 です。
以下のような人には、特に向いていると言えます。
必要な学費を補いたいが、返済が不安な人
学費の大部分は準備できているが、一部不足している
第一種奨学金では足りないが、多額の借入は避けたい
将来の収入を考慮し、無理なく返済できる範囲で借りたい
ポイント
必要最小限の借入に抑えることで、返済負担を軽減できる
利息の負担を減らすために、繰上返済も検討する
返済プランを自由に設定したい人
第二種奨学金では、毎月の貸与額を2万円〜12万円の範囲で選べる ため、自由度が高い です。
学費が高額な学部・学科(医学部・薬学部など)に進学予定
早めに返済したい人は高めに設定し、少額ずつ借りたい人は低めに設定できる
ポイント
収入が安定したら繰上返済を活用し、利息負担を減らす
卒業後の収入を見積もり、無理のない範囲で設定する
他の奨学金と組み合わせて活用する方法
第二種奨学金は他の奨学金と併用することで、負担を軽減できる 場合があります。
ここでは、給付型奨学金・民間奨学金との併用メリットと注意点 を解説します。
給付型奨学金と併用して負担を減らす
【給付型奨学金の特徴】
返済不要(支給された金額を返さなくてOK)
家計基準・成績基準を満たす必要がある
「高等教育の修学支援新制度」により、授業料減免とセットで受けられる可能性も
【組み合わせるメリット】
第二種奨学金の借入額を減らせる → 返済総額が少なくなる
奨学金の一部を給付型にすることで、負担を軽減できる
【注意点】
給付型奨学金は支給条件が厳しいため、事前に確認が必要
申請時期が早いため、情報収集を早めに行う
▶ 参考:JASSO(日本学生支援機構)の「給付型奨学金」
https://www.jasso.go.jp/
民間奨学金との併用メリットと注意点
【民間奨学金の特徴】
財団・企業・地方自治体などが提供
給付型 or 貸与型(無利子・有利子)の両方がある
分野別(理系・医療・スポーツなど)に特化した奨学金もある
【組み合わせるメリット】
無利子の奨学金と併用すれば、利息負担を減らせる
地方自治体の奨学金は、返済免除条件がある場合も
【注意点】
併用しすぎると、卒業後の返済負担が大きくなる
貸与型の奨学金は金利や返済条件を事前に確認する
【おすすめの民間奨学金】
▶ あしなが育英会(家庭の事情で学費負担が難しい方向け)
▶ 交通遺児育英会(交通事故で親を亡くした遺児向け)
▶ 地方自治体の奨学金(出身地限定の奨学金制度あり)
民間奨学金は、各団体の公式サイトで情報をチェックし、条件を満たすものを選びましょう。
まとめ|第二種奨学金を賢く選び、計画的に返済しよう
第二種奨学金は、第一種よりも審査基準が緩く、必要な学費を補うのに適した選択肢 です。
しかし、利息が最大3%かかるため、返済負担を考慮し、慎重に計画を立てる必要があります。
【第二種奨学金を選ぶ際のポイント】
必要最小限の借入に抑え、利息負担を減らす
繰上返済・返済猶予などの制度を活用し、無理なく返済する
給付型奨学金や民間奨学金と組み合わせ、負担を軽減する
【注意点】
借入額が大きいと、卒業後の返済が大きな負担になる
計画的に借りないと、生活に支障をきたす可能性がある