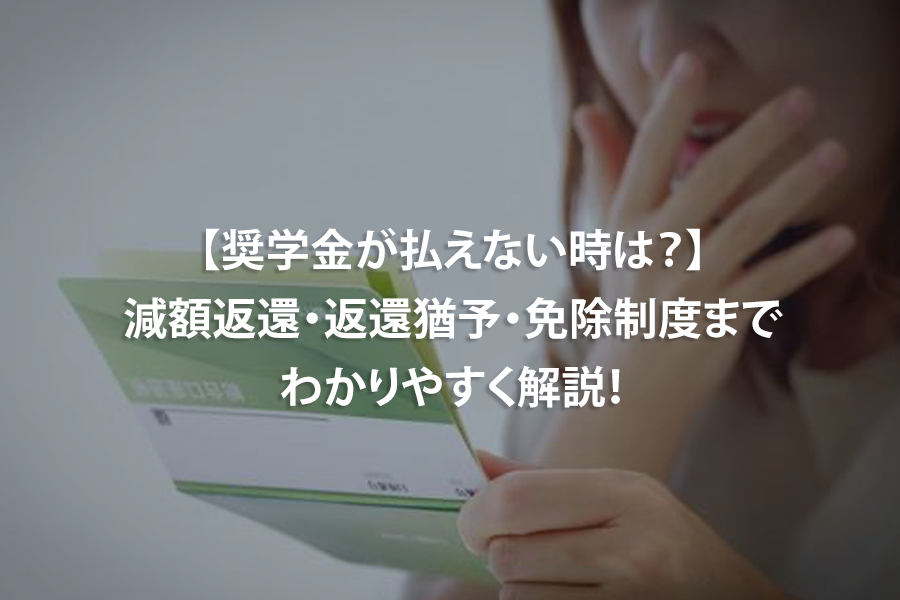
近年は物価高が続いており、生活費の捻出に苦労する方も少なくありません。
現在奨学金を利用していて将来の返済を控えている方や返済に困ったらどうしようと悩んで奨学金を利用すべきか悩んでいる方もいるでしょう。
この記事では、奨学金が払えない時はどうすれば良いのか、個々の状況に応じた適切な対処法をご紹介します。
減額返還や返還猶予、免除制度などの概要を把握して、いざというときに最適な判断ができるように備えましょう。
奨学金返済が払えない時にまず考えるべきこと
奨学金が払えない場合は、焦らずに適切な対応を採ることが重要です。
支払いができていない状態のまま放置すると、深刻な問題に発展する可能性があります。
トラブルを避けるために、しかるべき場所に早めに相談して、利用できる制度があるか確認しましょう。
ここでは、奨学金を返済せずに放置するリスクと、相談窓口をご紹介します。
支払いを放置するとどうなる?
奨学金の返済を放置すると、延滞金が発生し、返済総額が増加します。
延滞金は年度によって異なりますが、2025年の場合は年5%です。
さらに、目安として3ヶ月以上延滞を続けると、信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報として記録され、いわゆる「ブラックリスト」に入る可能性があります。
ブラックリストに入ると、一定期間は奨学金を滞納したという内容の事故情報が削除されません。
将来的に住宅ローンやマイカーローンを申し込む場合、利用する金融機関は信用情報機関の情報を参照するため、審査が不利になる可能性が高いです。
また、クレジットカードの更新ができなくなったり、新規発行の審査が不利になったりする可能性もあります。
さらに、支払いの延滞が続くと、日本学生支援機構(JASSO)から督促状が送付され、電話や訪問による催促が行われる場合もあります。
最終的には法的措置が執られ、給与などの資産を差し押さえられる可能性も否定できません。
そのため、奨学金を払えない場合は無断で滞納するのではなく、まずはしかるべき窓口に相談することが大切です。
放置する前に相談すべき窓口
JASSOは、奨学金を払えない利用者向けに相談窓口を設けています。
相談方法は次の3つです。
・電話:奨学金返還相談センター(0570-666-301、平日9:00~18:00)
・オンライン:スカラネット・パーソナル(https://www.sas.jasso.go.jp/personal/)の問い合わせフォーム
・直接相談:JASSOの地方支部(東京、大阪など)で対面相談
電話で相談する場合は、奨学金番号などの情報を準備してから問い合わせるとスムーズです。
オンラインでは、マイページの「問い合わせ」画面から返済が難しい旨を記載して送信すると、3~5営業日後までに回答が届きます。
また、JASSOの地方支部に直接相談する場合は、事前予約が必須です。
1. 減額返還制度とは?返済が厳しい人のための支援
奨学金の返済が難しい方への支援策として、JASSOはいくつかの制度を設けています。
そのうちの一つが「減額返還制度」であり、これは月々の返済額を減らしたい方に最適です。
ここでは、減額返還制度の概要やメリット、支援を受けるための条件、そして申請の流れを解説します。
制度の概要とメリット
減額返還制度は、月々の返済額を半分または3分の1に減らし、返済期間を延長する制度です。
たとえば、月々2.5万円を返済している場合、月々の返済額を1.25万円に減額し、その代わりに返済期間を10年から15年に延長します。
なお、追加の利息は発生しないため、総返済額は変わりません。
減額返還制度は最長15年間の申請が可能で、経済状況に応じて期間を毎年変更できます。
JASSOによると、2025年度時点で約5万人が減額返還制度を利用中です。
月々の返済負担を減らせば返済を続けられるという方にとって、有効な制度と言えるでしょう。
対象となる条件
減額返還制度の対象となるのは、年間所得が一定額以下の世帯です。
具体的な基準は年度によって変わる可能性がありますが、2025年時点では以下の基準に合致する場合に減額返還制度の対象となります。
・給与所得者:年収325万円以下
・非給与所得者:所得195万円以下
目安として月収27万円以下の方が対象です。
給与所得を得ていない方の場合、所得の合計が195万円以下の場合に減額返還制度の適用を申請できます。
なお所得とは、総収入から必要経費を差し引いた額です。
また、扶養人数が多いほど基準が緩和されるため、詳しくはJASSOの担当窓口にお問い合わせください。
申請手続きと必要書類
減額返還制度の申請にはいくつかの書類が必要です。
申請の前に、以下の必要書類を揃えておきましょう。
・在職証明書:勤務先が発行する証明書で、派遣やアルバイトの方も取得できる
・所得証明書:市区町村が発行する課税証明書や源泉徴収票
・奨学金番号:スカラネット・パーソナルから確認できる
・マイナンバー:収入を証明するために提出が必要
インターネットを利用した申請方法は次の通りです。
1.スカラネット・パーソナルにログインする
2.「減額返還申請」メニューをクリックまたはタップして、必要情報を入力する
3.書類をPDFでアップロードする(郵送による申請も可能)
4.1~2ヶ月後に審査結果がメールまたは郵送で通知される
なお、申請期限は毎年4月30日もしくは10月31日です。
申請期限を超過しないように、できるだけ早く必要書類の準備をはじめて、スカラネット・パーソナルから申し込みましょう。
2. 返還期限猶予とは?一時的に返済をストップできる制度
返還期限猶予とは、奨学金の返済が一時的に困難な状況に陥った場合に利用できる制度です。
返還期限猶予の概要やメリット、支援を受けるための条件、そして申請の流れを解説します。
返還期限猶予とは?
返還期限猶予とは、経済的困窮など特定の事情により奨学金の返済が困難な場合に、最大10年間にわたり返済を延期できる制度です。
猶予期間中は利息や延滞金が発生せず、信用情報への影響もありません。
そのため、いわゆるブラックリスト入りを回避できます。
JASSOによると、2025年時点で約10万人が返還期限猶予を利用しています。
利用できるケースと条件
返還期限猶予を利用できるケースは、失業や転職、災害などの理由で所得が大幅に低下した場合、病気や出産などの事情で収入が減った場合です。
具体的なケースと条件、制度を適用するために必要な書類などの情報をリストアップします。
失業:ハローワークの失業証明書が必要
低所得:年収300万円以下または所得170万円以下
病気・障害:医師の診断書や治療証明書が必要
産休・育休:出産・育児による休職証明書が必要
災害:被災証明書が必要
上記のような事情により年間収入や所得が一定未満の方が返還期限猶予の対象です。
なお、年収や所得の目安は扶養人数や医療費負担割合など個別の事情をもとに決められます。
そのため、年収300万円以上もしくは所得170万円以上の方も、返還期限猶予を適用できるか、JASSOの担当窓口に問い合わせると良いでしょう。
申請方法と注意点
返還期限猶予の注意点は、1年ごとに毎年更新が必要なことです。
「年収が元の水準に戻った」「産休・育休が明けて働けるようになった」といった状況改善後は通常通りに返済を再開する必要があります。
状況の改善に至らない場合は、必要書類を揃えたうえで再申請しなければなりません。
また、返還期限猶予の猶予期間は、返済が免除されるわけではないことにも注意しましょう。
猶予とは、すなわち「返済の先送り」であり、返済総額が減ることはありません。
たとえば、月々2万円を10年間で返済していて、猶予期間が5年間の場合は、5年後から月々2万円を10年間かけて返済する必要があります。
なお、返還期限猶予をオンラインから申請する方法は次の通りです。
1.スカラネット・パーソナルにログインする
2.「返還期限猶予申請」メニューをクリックまたはタップして、必要情報を入力する
3.失業証明書、所得証明書、診断書などの必要書類をアップロードする
4.1~2ヶ月後に審査結果がメールまたは郵送で通知される
なお、返還期限猶予の申請は随時受け付けられています。
できるだけ早く制度の適用をスタートさせたい場合は、毎月27日の返済期日前に申請を済ませると良いでしょう。
3. 死亡または精神・身体障害による返還免除制度とは?
死亡や重度の障害に陥った場合に、奨学金の返済が全額免除される制度があります。
返還免除制度の概要やメリット、支援を受けるための条件、そして申請の流れを見ていきましょう。
制度の対象と概要
返還免除制度とは、奨学金の借主本人が死亡または障害基礎年金1・2級相当の精神・身体障害に該当する場合に適用できる制度です。
申請が認められた場合、奨学金残債全額の返済が免除されます。
JASSOによると、返還免除制度の適用が認められている件数は年間約1,000件です。
返還免除制度を適用できる場合、遺族や保証人に返済義務が発生することもありません。
つまり、奨学金の借主が結婚し、子どもを設けた後に死亡したとしても、配偶者や子どもに借金を残す心配はなくなります。
申請に必要な書類
返還免除制度の申請に必要な書類は、制度を適用する事情によって以下のように異なります。
死亡の場合:死亡診断書、戸籍謄本
障害の場合:障害年金受給証明書、医師の診断書
また、死亡時・障害時いずれも提出が必要な書類は、借主の奨学金番号とマイナンバーです。
なお、障害を理由に制度を利用する場合は、JASSOが指定する形式の診断書を提出する必要があります。
診断書は3ヶ月以内に発行されたものに限られるため、診断書の取得後は速やかに申請を行いましょう。
親が保証人の場合の対応は?
親を保証人として指定していた場合でも、返還免除制度の適用が認められた場合は、保証人に残債が請求されることはありません。
JASSOが指定する保証会社を利用していた場合も同様で、免除の対象となります。
また、返還免除制度の申請は借主本人だけでなく、その家族(遺族)も行えます。
借主が死亡している場合や障害の状況により本人の申請が困難な場合は、借主の代わりに家族が申請を行いましょう。
3つの制度を比較!どの制度を使えばいい?
減額返還制度、返還期限猶予、返還免除制度はそれぞれ特徴が異なり、利用できるシーンにも違いがあります。
「結局、どの制度を利用できるの?」といった疑問を抱えている方に向けて、3つの制度を比較する表をご用意しました。
| 項目 | 減額返還制度 | 返還期限猶予 | 返還免除 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 月々の負担を減らす | 一時的に返済を止める | 完全に返済を免除 |
| 利用期間 | 最長15年 | 最長10年 | 一生涯(適用時) |
| 条件 | 所得・収入基準 | 所得・病気・育休等 | 死亡・障害等 |
| 審査 | あり | あり | 証明書類で確認 |
まずはそれぞれの制度の条件を確認して、現時点で申請できる制度があるか調べましょう。
減額返還制度と返還期限猶予のどちらを適用できるか悩んだ場合は、目的に応じて最適な制度を選ぶことがポイントです。
返済が難しい時にやってはいけないNG行動
奨学金が払えない時に誤った対応を採ると状況を悪化させます。
返済が困難になった時のNG行動とそのリスクを理解して、焦らずに正しい行動を取って対処しましょう。
放置・未連絡で延滞状態にする
返済を滞納した状態で放置すると、目安として3ヶ月以上の延滞で信用情報に記録され、クレジットカードやローンの審査に悪影響を及ぼします。
一度記録された信用情報は目安として5~7年間残り、この間の住宅ローン審査やマイカーローン審査が極めて不利になるほか、就職時の信用調査に影響する場合もあるでしょう。
また、JASSOに未連絡のまま滞納を続けると、郵送や訪問による督促を受けたり、法的措置を受けたりする場合があります。
払えないまま放置するのではなく、まずはJASSOの窓口に相談することが大切です。
闇金などに頼る
「審査なし」「即日融資」を謳う闇金は、年100%以上の高金利や脅迫などの行為を含む違法な取り立てを行う場合があります。
金銭的に困窮した際などは闇金を頼ってしまいがちですが、金融庁の許可を得ている正規の金融業者以外を利用してはいけません。
どうしても消費者金融に頼らざるを得ない場合は、金融庁の「貸金業者登録」を確認し、リストに含まれる正規業者を利用しましょう。
奨学金が払えない場合の正しい相談機関は、JASSOや国民生活センター、大学の奨学金窓口などです。
万が一闇金による被害を受けた場合は、警察や弁護士に相談しましょう。
法律相談が必要な場合は、法テラス(日本司法支援センター)に問い合わせると、無料で相談・依頼ができる可能性があります。
生活が苦しい学生・卒業生のためのほかの支援策
奨学金が払えないせいで、生活が苦しくなった場合は、JASSOの各種制度と併用できる支援策の活用も検討しましょう。
地方自治体や大学、そして職場で利用できる制度として有効なものを、いくつかピックアップしてご紹介します。
地方自治体や大学の独自支援制度
地方自治体や大学が独自の支援を提供している場合があります。
たとえば東京都の場合、多子世帯向けに月額1万~3万円を補助する制度を設けているほか、独自の奨学金返済支援事業を実施中です。
国公立大学の場合、授業料免除などの制度を適用できる可能性があるため、市区町村役場や大学の担当窓口に相談しましょう。
また、地方自治体の奨学金を、JASSOの奨学金と併用することも可能です。
ただし、総額が学費・生活費を超えないよう調整される場合があるため、大学やJASSOに確認を取りましょう。
職場の福利厚生・奨学金返済支援制度
一部企業では、福利厚生の一部として、奨学金返済支援制度を導入している場合があります。
各種制度を適用できる企業に就職したい場合は、以下のチェックポイントに注目しましょう。
・企業HPや採用パンフレットで「奨学金返済支援」の有無を確認する
・人事部に支援制度の詳細を質問する
中小企業でも支援を行っている場合があるため、福利厚生の内容を今一度確認することをおすすめします。
まとめ
奨学金が払えないで困った場合は、減額返還制度や返還猶予、返還免除制度を活用できる可能性があります。
それぞれ対象となる条件や支援の内容が異なるため、現在の状況に合った制度を活用しましょう。
返済が難しくなると焦ってしまいがちですが、JASSOに連絡しないまま放置したり、闇金に手を出したりすることはおすすめできません。
しかるべき窓口にできる限り早く相談して、担当者と一緒に最善の解決策を見つけましょう。










