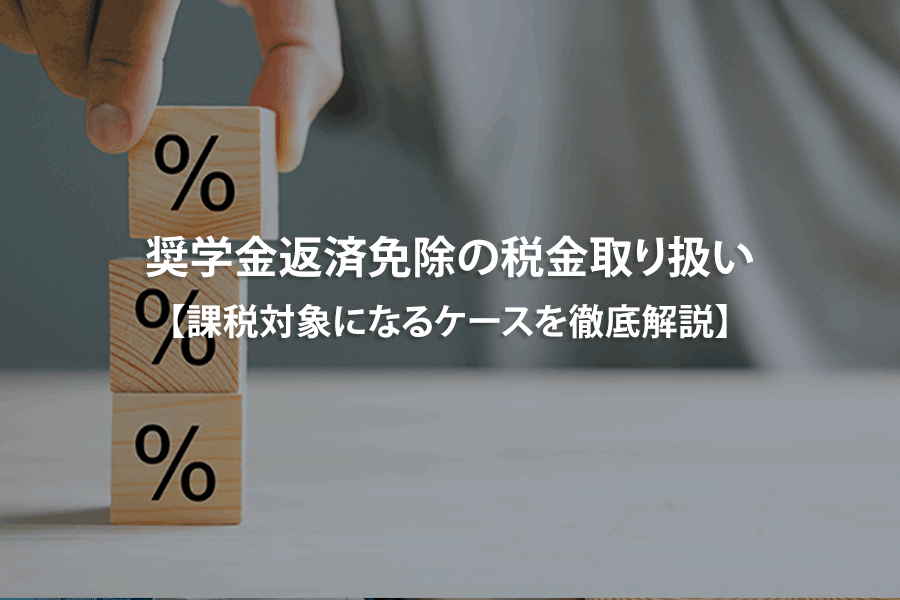
奨学金は学生の生活や将来の夢を叶える重要な制度です。
しかし返済免除を受けると「税金がかかるのでは?」と不安になる方も多いでしょう。
2025年現在、奨学金の返済免除額が課税対象になるケースと非課税ケースが混在しており、判断すると脱税を疑われるリスクもあります。
この記事では、奨学金返済免除と税金の関係について触れたうえで、課税対象となるケース・非課税となるケースをそれぞれわかりやすくご紹介します。
判断が迷った際の相談先や確定申告の手順も解説するため、将来のトラブルを防ぐためにも、内容をしっかりと確認しておきましょう。
奨学金返済免除とは?制度の基本をおさらい
奨学金返済免除とは、貸与型奨学金の返済義務を一部または全部免除する制度です。
奨学金は債務として扱われるため、返済が免除された場合、一時的な利益を指す「返済免除益」が発生します。
しかし、税法上の扱いは免除の目的によって変わるため、課税対象となるケースと非課税となるケースに分かれるのです。
奨学金返済免除の主な種類
奨学金返済免除の種類は、主に次の3つです。
・成績優秀を理由とした返済免除
・災害や死亡、障害といった問題からの救済を目的とした返済免除
・就職先の事情を勘案した返済免除
優れた成績を残した場合や地震や台風などの災害が原因で生活再建が困難になった場合、死亡・重度障害などで奨学金返済が困難になった場合などが免除の主な種類です。
過疎地における医療関係の仕事に就く場合など、就職先の事情を勘案して免除されるケースもあります。
対象となる主な奨学金制度
奨学金返済免除の対象となる主な奨学金制度は次のとおりです。
・JASSO(日本学生支援機構)による奨学金
・地方自治体による奨学金
・大学独自の奨学金
・民間企業や財団による奨学金
たとえば、JASSOの場合、成績優秀な学生や災害などが原因で返済が困難な状況に陥った方の奨学金返済を免除するケースがあります。
地方自治体の場合は特定の地域で就職した学生、民間企業の場合は特定の勤務先に就職した学生の奨学金返済を免除するケースが多いです。
返済免除が認められる条件と審査基準の例
返済免除の条件は利用した奨学金制度によって異なります。
たとえば、成績優秀を免除の条件とする奨学金制度を利用している場合、在学中の学会発表や論文といった研究結果が審査され、特に優れていると認められた場合に免除されます。
災害を理由とした返済免除の場合は、奨学生本人または家族の死亡、重度の障害、被災による家計の急変など、返済困難な事情が審査されるケースが多いです。
奨学金返済免除と税金の関係
奨学金の返済免除が決まると、奨学生にとって「利益」が発生した状態と見られます。
この場合の税法上の扱いは複雑なため、まずは返済免除と税金の基本的な関係性を整理しましょう。
免除された奨学金は「所得」とみなされる?
奨学金返済が免除された場合、免除された金額は「債務免除益」として扱われることが基本です。
これは一時所得または雑所得とみなされる利益であり、原則として課税対象となります。
しかし、奨学金は「教育の機会均等」を目的として支給される、一般的な借入金とは性質が異なるお金です。
そのため、免除の目的や条件次第では、課税が免除される特例を適用できます。
「返済免除」と「給付型奨学金」の税法上の違い
給付型奨学金とは、もともと返済する必要のない契約で受け取る奨学金です。
返済免除は貸与後の債務放棄として扱われるため、条件次第では課税されます。
一方の給付型奨学金は、学資充当として支給されるものであり、完全非課税です。
なお、JASSOの給付型奨学金は所得制限内で支給されます。
そのため、奨学金を受け取った後に税務申告する必要もありません。
所得税法における「一時所得」と「非課税所得」の定義
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得です。
労働の対価として得た金銭ではないものを一時所得と呼びます。
「総収入金額-収入を得るために支出した金額-最高50万円の特別控除×1/2」で計算した金額が課税対象です。
一方の非課税所得とは、所得税法や特別法により、課税対象から除外されている所得です。
教育費や学術奨学金などが非課税所得に該当する場合があります。
【課税対象になるケース】
ここまでにお伝えしたとおり、奨学金の返済免除は「所得」とみなされる場合があります。その場合に課税対象になるケースは、大きく次の3つです。
① 研究職・企業奨学金など、勤務条件付き免除の場合
② 自治体や企業が負担した場合(代理返還との違い)
③ 一部返済免除で、残額返済があるケースの注意点
それぞれのケースを詳しく解説します。
① 研究職・企業奨学金など、勤務条件付き免除の場合
返済免除を適用する条件として、特定の企業や研究機関に一定期間にわたって勤務するなどの義務を負う場合、免除された金額が給与所得または雑所得とみなされます。
この場合、免除された奨学金は課税対象です。
② 自治体や企業が負担した場合
自治体や企業が奨学生の奨学金返済を負担する場合は「支援金」として扱われるため、一時所得として扱われるため、課税対象となります。
ただし、JASSOによる代理返還を利用する場合は、特例措置を適用できるため非課税です。
③ 一部返済免除で、残額返済があるケースの注意点
たとえば、総返済額の2分の1が返済免除となる場合など、一部返済免除が適用される場合は、免除分の実が一時所得として扱われます。
残額分は非課税となりますが、全体額の按分計算が必要となり、これを省くと申告漏れが指摘されるリスクがあるため要注意です。
このケースでは、税理士や税務署に相談し、専門的な計算を依頼することをおすすめします。
【非課税となるケース】
特定の要件を満たす場合は非課税となるケースがあります。
具体例としては次の3つです。
それぞれの詳細を見てみましょう。
<非課税となるケース>
① 成績優秀による免除(報奨金ではない場合)
② 災害・病気・死亡による免除(救済目的のため非課税)
③ JASSOの奨学金返還免除制度の扱い
① 成績優秀による免除
学業成績が優秀であることを認められて奨学金免除となった場合は非課税となります。
ただし、報奨金という名目で奨学金が給付されている場合は課税対象となるため注意しましょう。
名目は、奨学金支給開始時などに発行された通知書などに記載されています。
② 災害・病気・死亡による免除
奨学金を受給している本人が死亡または重度障害を負った場合や災害などにより著しく返済困難になった場合に行われる返済免除は非課税です。
このようなケースは、救済または社会福祉の性質が強い免除とみなされるため、非課税となります。
③ JASSOの奨学金返還免除制度の扱い
JASSOの奨学金返還免除制度は、その設立目的や制度の趣旨から原則非課税とされています。
また、「博士課程奨学金返還免除」も非課税の対象です。
これは、所得税法の特例的な扱いであり、比較的特殊なケースに該当します。
確定申告が必要になる場合と手続きの流れ
奨学金返済免除額が課税対象となった場合、原則として自分で確定申告を行う必要があります。
ここでは、申告手順を解説することに加えて、確定申告をしないとどうなるのかを見てみましょう。
課税対象になった場合の申告手順
奨学金返済免除が課税対象になった場合、次の手順で確定申告を行います。
①所得を確認する
②申告書を作成する
③必要書類を準備する
④確定申告を行い納税する
まずは給与所得として源泉徴収票に記載されているか確認しましょう。
記載されていない場合または一時所得とみなされる場合は、自分自身で確定申告が必要です。
申告書には一時所得または雑所得として、免除額を記入します。
さらに、この後ご紹介する必要書類を添付して、税務署に申告書を提出し、納税してください。
必要な書類
確定申告において必要な書類は、主に次のとおりです。
・奨学金返済免除通知書
・源泉徴収票(勤務条件付き免除で給与として扱われた場合など)
・支払調書(企業や自治体が発行した場合など)
確定申告の内容により、その他の必要書類が増える可能性もあるため、詳しくは税理士などの専門家に確認すると良いでしょう。
確定申告を忘れるとどうなる?
奨学金免除額が課税対象となっているにもかかわらず、確定申告を忘れたり、意図的に無視したりすると、所得隠しとみなされる場合があります。
この場合は税務署から後日指摘を受ける可能性があり、追徴課税や延滞税の支払いが求められるため要注意です。
追徴課税とは、無申告加算税や過少申告加算税といったペナルティの総称で、本来収めるはずだった税金に加えて支払わなければなりません。
延滞税は、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じた金額が納税額に加算されます。
課税・非課税の判断に迷ったら?相談先一覧
奨学金免除にまつわる条件は複雑であり、課税されるのか、それとも非課税となるのか判断に迷うことは珍しくありません。
そこで、判断に迷った場合の相談先をご紹介します。
国税庁・税務署への相談
最も確実に課税・非課税を見分ける方法は、最寄りの税務署や国税庁の電話相談センターに問い合わせることです。
問い合わせの際は、利用した奨学金制度の名称と免除の条件を伝えましょう。
税法上の取り扱いについて、国税の見解を確認すると申告漏れを予防しやすくなります。
大学・奨学金機構への確認窓口
奨学金を提供した大学の担当窓口やJASSOなどの奨学金機構の担当窓口に問い合わせる方法も有効です。
利用した奨学金制度を伝えたうえで「本制度による免除は税法上どのような扱いになるか」と尋ねましょう。
専門家による見解でないことには注意が必要ですが、ノウハウをもとにした解答が得られます。
税理士・FPへの相談タイミング
税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)に相談する手もあります。
この場合は費用が発生するため、相談するタイミングやケースを見極めましょう。
一つの目安としては、免除額が50万円を超える場合を挙げられます。
この場合、一時所得の特別控除額を上回るため、課税対象となる可能性が高いです。
また、勤務条件付き免除を受け、源泉徴収票に記載がない場合も税理士やFPへの相談にふさわしいタイミングです。
この場合、企業側の税務処理が適切に行われているか判断しにくいため、専門家に見解を示してもらいましょう。
返済免除の税金トラブルを避けるための3つのポイント
返済免除の税金トラブルは、次の3つのポイントをチェックすると避けやすくなります。
それぞれの項目を見てみましょう。
① 奨学金免除の通知内容を必ず確認する
② 奨学金の種類・提供元ごとに扱いを区別する
③ 年末調整や確定申告時に「免除額」を申告書に反映
① 奨学金免除の通知内容を必ず確認する
奨学金機構などから届く「返済免除決定通知書」や「支払調書」などの文書を必ず保管し、「免除の目的」「免除額」「税法上の扱いに関する特記事項」を確認しましょう。
これらの情報は、課税の有無を判断する重要な材料になります。
② 奨学金の種類・提供元ごとに扱いを区別する
JASSOの免除は非課税特例があることが多いですが、自治体や企業の奨学金は、勤務条件があるか否かなどで課税の有無が分かれます。
自身の奨学金がどのタイプに属するか明確に区別しましょう。
③ 年末調整や確定申告時に「免除額」を申告書に反映
課税対象となった免除額は、給与所得者であれば年末調整で処理されているか源泉徴収票を確認しましょう。
処理されていない場合は、確定申告で申告書に反映させる必要があります。
免除以外の奨学金支援制度
返済免除意外にも、奨学金返済の負担を支援する制度があります。
ここでは、3つの奨学金支援制度を見てみましょう。
奨学金代理返還制度
奨学金代理返還制度は、就職先の企業がJASSOなどの奨学金を本人に代わって返還する制度です。
この制度を利用した場合、企業が直接JASSOへ返還した金額には課税されません。
給付型奨学金
給付型奨学金は、返済義務が一切ない奨学金です。
教育・学術の研究奨励を目的とするため、原則として全額非課税となります。
教育費控除・寄付控除との違い
教育費控除や寄付控除とは、支払った支出の一部から所得を差し引くことです。
控除は税金を安くする仕組みであり、そもそも課税・非課税の話とは異なります。
奨学金返済免除を受けた人の事例紹介
ここでは、実際に奨学金返済免除を受けた人の事例を3つご紹介します。
モデルケースを参考に、ご自身の奨学金免除が課税されるか、それとも非課税となるか判断しましょう。
事例① 博士課程で返還免除を受けたケース(非課税)
JASSOの第一種奨学金を借りた大学院生が、博士課程を修了する際に、成績優秀を理由に全額免除の認定を受けたケースです。
この場合、JASSOの特例措置が適用されるため、非課税となります。
確定申告も不要です。
事例② 企業奨学金で勤務義務付き返還免除(課税)
大学卒業後、5年以上の勤務をすることを条件に企業奨学金を借りたケースです。
この場合、免除額は勤務の対価とみなされるため、課税されることになります。
なお、原則として企業側が税務処理して源泉徴収を行うため、奨学金を借りた本人は年末調整のみで税務手続きが完了します。
事例③ 自治体支援型奨学金で一部免除(ケース判断)
自治体の奨学金を利用して、所定の勤務条件を満たすことを条件に、返済額の一部が免除されたケースです。
この場合は勤務義務の対価とみなされるため、基本的には課税されます。
しかし、自治体によっては「地域への貢献に対する報酬」といった特例を適用する場合があり、非課税となる場合があります。
事前に自治体の担当窓口に問い合わせて、税務上の見解を示してもらいましょう。
まとめ
奨学金の返済免除は、免除された理由や、奨学金制度の条件によって税法上の扱いが大きく異なります。
課税対象となる場合、確定申告が必要な可能性があるため注意しましょう。
税務上の扱いが不明瞭な場合は、JASSOなどの担当窓口や税理士など税金の専門家に相談することをおすすめします。










